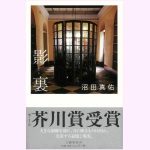崩壊の予感漂う、寄る辺のない孤独
沼田真佑(ぬまた・しんすけ)著/第157回芥川賞受賞作(2017年上半期)
唯一心を許した男の失踪
受賞作「影裏」(えいり)の舞台は、岩手県。主人公の「わたし」が唯一心を許していたのは、日浅(ひあさ)という男。事あるごとに酒を酌み交わし、豊かな水流が美しい川辺で釣りに興じる2人。だが、些細な出来事をきっかけに疎遠になり、やがて日浅は失踪。その行方を追ううちに、「わたし」は日浅の〝もうひとつの顔〟を目の当たりにし、その光と影に向き合う。岩手の豊かな水と緑の中で描かれる世界は、薄暗いひんやりとした手触りが美しく、不気味でもある。
柱となるのは、「わたし」と日浅の関わりなのだが、途中で「わたし」が過去に付き合ったゲイの恋人や、東日本大震災の話が出てくる。ただ、いずれも作品の中にひっそりと紛れ込ませるような描き方なので、それが決して作品の主題ではないことは分かる。それでも、それぞれの素材が、「影裏」というタイトルからイメージされる、人間の影の部分や裏の顔というものを浮き上がらせるのに効果的な役割を果たしている。それは、薄暗くひんやりとした情景描写と同じように、孤独で、不安げだ。
普通、芥川賞の選評を丹念に読むと、何が評価され何が不評だったか、ある程度の輪郭が見えてくるのだが、「影裏」に対する選評にははっきりした対立軸が見えない。各選考委員がそれぞれの視点で高評価し、あるいは低評価をしている。それだけ複雑で多面的な作品と言えるのかもしれない。
ただ、多くの選考委員が共通して高評価しているのは、その文章である。不必要なものを全て削ぎ落としたような引き締まった文章には、雑味がない。手取り足取り説明しないので、読み手に対しては多少不親切なのだが、一言一句見落とすことなく読み進まなければならない緊張感は心地がいい。また、そうした文章が、作品全体に漂う薄ら寒い寂しさのようなものを際立たせてもいる。
山田詠美
「ぽつりぽつりと置かれた描写をつなぐのは、主人公の背後にまとわりつく彼(日浅)の存在。まるで、きらきらと輝く接着剤のような言葉で小説をまとめ上げて行く。うまいなー」
奥泉光
「どこかハードボイルドふうの味わいのある作品で、描写に安定があって、なるほど気持ちよく読めた。が、短い。これは序章であって、これから日浅と云う謎の男を追う主人公の物語がはじまるのでないかという印象を持った」
最終的には厳しい評価をした村上龍も文章に対しては高評価。
作者の描写力は新人の域を超えている。冒頭の『釣り』の情景描写は、緻密であり、しかも饒舌ではない。主人公や、他の登場人物の心理描写も、正確で、かつ抑制されている
自然描写によって核心を描
日浅という男の本質の一面を表している描写が、次の一文である。
そもそもこの日浅という男は、それがどういう種類のものごとであれ、何か大きなものの崩壊に脆く感動しやすくできていた
ここで言う「崩壊」こそが、この作品の中に一貫して流れている不安げで寂しげな空気の要因のひとつだろう。崩壊の美を自分自身に求めた時にはそれは破綻者となるだろうし、自然に求めた時には(東日本大震災のような)大災害になるだろう。こうした崩壊は、日浅だけではなく、おそらく「わたし」自身も抱えていることなのだ。つまり、多様性に対して都会ほど寛容ではない地方の田舎町にあってゲイという特性を隠し持っている自分自身の崩壊に対する恐れでもあるし、それこそが寄る辺のない孤独でもある。
堀江敏幸
「冒頭の自然描写の、緻密なようで隙のある書き方は、語り手自身の眼の奥に映った光景を摑もうとした結果であり、日浅という男の謎は『わたし』が押し隠している崩れの予感のあらわれだろう」
小川洋子
「誰もがぽつん、ぽつんとその場に取り残され、立ち往生している。ここに立ち込める、救われようのない濃密な孤独の前で、言葉は無力だ」
吉田修一
「作者の筆は核心から離れよう離れようとするごとく、岩手の美しい自然を描写していく。そして自然を精緻に描写すればするほど、離れたはずの核心がなぜか近づいてくる。遠景としての核心が近景に、近景としての自然が遠景となるような混乱が起こる」
選考会ではこの「核心」とは何かということについて議論となったようだが、「単なるほのめかし小説」ではないかという否定的な意見も出たように、読者に等しく伝わるような明確なものはない。ただ、吉田修一は、「このほのめかしは、マイノリティである主人公の余裕から出るものではなく、余裕などからは程遠い、そのギリギリのところで絞り出された勇気から出たものと読んだ」と述べている。「核心」とは無関係と思われる自然描写を丹念に積み重ねていくことによって、その「核心」がより鮮明に浮かび上がってくるのは、まさに芸というしかない。
「影裏」は、2020年、大友啓史によって映画化されている。純文学の映画化というのは難しい面もあると思われるが、水が豊富な岩手という土地の美しさがそれを可能にしたのだろう。
「芥川賞を読む」:
「芥川賞を読む」一覧
第1回『ネコババのいる町で』 第2回『表層生活』 第3回『村の名前』 第4回『妊娠カレンダー』 第5回『自動起床装置』 第6回『背負い水』 第7回『至高聖所(アバトーン)』 第8回『運転士』 第9回『犬婿入り』 第10回『寂寥郊野』 第11回『石の来歴』 第12回『タイムスリップ・コンビナート』 第13回『おでるでく』 第14回『この人の閾(いき)』 第15回『豚の報い』 第16回『蛇を踏む』 第17回『家族シネマ』 第18回『海峡の光』 第19回『水滴』 第20回『ゲルマニウムの夜』 第21回『ブエノスアイレス午前零時』 第22回『日蝕』 第23回『蔭の棲みか』 第24回『夏の約束』 第25回『きれぎれ』 第26回『花腐し』 第27回『聖水』 第28回『熊の敷石』 第29回『中陰の花』 第30回『猛スピードで母は』 第31回『パーク・ライフ』 第32回『しょっぱいドライブ』 第33回『ハリガネムシ』 第34回『蛇にピアス』 第35回『蹴りたい背中』 第36回『介護入門』 第37回『グランドフィナーレ』 第38回 『土の中の子供』 第39回『沖で待つ』 第40回『八月の路上に捨てる』 第41回『ひとり日和』 第42回『アサッテの人』 第43回『乳と卵』 第44回『時が滲む朝』 第45回『ポトスライムの舟』 第46回『終の住処』 第47回『乙女の密告』 第48回『苦役列車』 第49回『きことわ』 第50回『道化師の蝶』 第51回『共喰い』 第52回『冥土めぐり』 第54回『爪と目』 第55回『穴』 第56回『春の庭』 第57回『九年前の祈り』 第58回『火花』 第59回『スクラップ・アンド・ビルド』 第60回『異類婚姻譚』 第61回『死んでいない者』 第62回『コンビニ人間』 第63回『しんせかい』 第64回『影裏』 第65回『百年泥』