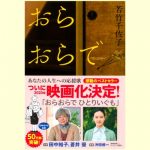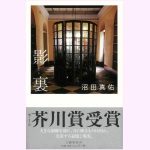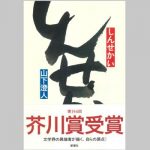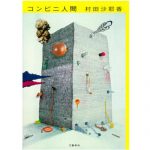孤独と老いに向き合う東北弁の老婦人
若竹千佐子(わかたけ・ちさこ)著/第158回芥川賞受賞作(2017年下半期)
老いを思弁する
芥川賞作家の受賞年齢は、だいたい30~40代が多いのだが、ダブル受賞となった第158回は、前回取り上げた「百年泥」の石井遊佳が54歳、今回、取り上げる「おらおらでひとりいぐも」の若竹千佐子が63歳と、いずれもある程度の年配者だったのがひとつの特徴だった。
若竹は、55歳の時に夫に先立たれ、長男のすすめで小説講座に通い始めたのが小説に取り組むきっかけだった。2017年に同作で第54回文藝賞を受賞してデビューし、翌年2018年に芥川賞を受賞。2020年には田中裕子の主演で映画化もされている。まさに、人生どこでどうなるか分からない。 続きを読む