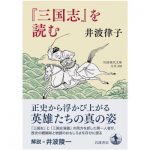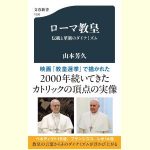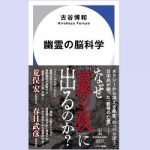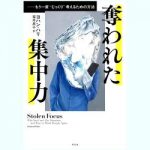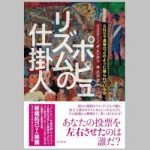正史『三国志』とは
日本で『三国志』というと、明代(1368-1644年)に書かれた小説『三国志演義』(以後、小説『演義』)が圧倒的によく知られている。しかし民間伝承を豊富にとりこみ編集したこの作品は、中国の大衆の心情や文化を伝えるものではあるが、誇張や伝説が多く紛れ込んでおり、人物の歴史的実像を伝えているとはいいがたい。
著者の井波律子氏(1944-2020年)は、正史『三国志』と『三国志演義』を翻訳したことで知られている。その他にも『水滸伝』や『世説新語』などの個人訳を成し遂げ、中国古典に関する多数の著書がある。
本書は、「正史『三国志』を読む」というテーマで行われた4回の講座を加筆、編集したものである。さらに岩波現代文庫収録にあたり、2編の文章が増補されたものだ。小説『演義』の骨子となった歴史書である正史『三国志』を読み解きながら、波瀾万丈の時代を駆け抜けた英雄たちの実像に迫っていく。
陳寿は生きている間はとかく悪口を言われどおしで、挫折つづきの不幸な歴史家でしたが、その著述はこのようにして時間を越え、脈々と生命を保ったのですから、以て瞑すべし(※)というべきでしょう。(本書50ページ、注釈は編集部)