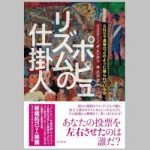インターネットの登場が政治を変えた
著者はフィレンツェ市の副市長やイタリア首相のアドバイザーを務め、現在はパリ政治学院で教鞭を執る政治学者。本書『ポピュリストの仕掛人』は、現在、洋の東西を問わず世界中を混乱に陥れている政治運動・ポピュリズム(大衆迎合主義)に鋭くメスを入れたものだ。
ポピュリズムとひとくちに言っても、その政治的主張は国によって微妙に色合いが異なる。あえて言えば、極端に過激な主張と排外主義に特徴がある。担い手となる支持者も「何かに対して怒りを抱いている人」という特徴があるが、労働者や富裕層などの社会集団に絞ることはできない。従来の分析手法では捉えることは難しいこの運動の本質を、本書では独自の観点から分析している。
新たに登場した頭のいかれた政治屋たちは、最小公倍数を割り出して人びとを団結させるのではなく、できるだけ多くの小さな集団の情念を煽り、彼らの気づかないところでそれらを足し合わせようと画策する。彼らは多数派を中道(センター)ではなく極端(エクストリーム)に収斂させようとする。(本書16ページ)
「SNSと政治」というテーマは、近年、日本でもさまざまに議論されている。
――SNSを上手く活用した政党が支持を伸ばす。SNSで拡散されたデマが選挙結果に影響を与えている、などの内容が大半を占めている。
だが、著者の視点はそれらと一線を画している。インターネットとSNSこそが現在の政治状況を生み出したというものだ。
現代のポピュリズムはイタリアの政党「五つ星運動」を起源とする。この政党はマーケティングの専門家であったジャンロベルト・カサレッジオ氏とインターネットの専門家であった息子によって立ち上げられた。SNSとアルゴリズム(コンピュータープログラミングで使用される目的を遂行するための指示や順序、計算や処理方法)の活用で支持者を拡大し、2018年には政権を奪取した。
第1次トランプ政権の誕生に貢献し、世界的なスキャンダルを引き起こした企業「ケンブリッジ・アナリティカ社」の立ち上げにも関与したスティーブ・バノン氏の事例も興味深い。彼がSNSに注目するに至ったのは、ビジネスの失敗が原因であった。当時、世界中で流行していたオンラインゲームで長時間を費やさなければ手に入れられないアイテムを、中国人を安く雇い入手し、欧米の人間に高く転売するという事業の立ち上げに関わっていた。しかし世界中のゲーマーから抗議が殺到し事業は失敗する。このときに遭遇した彼らの凄まじい怒りに驚いたバノン氏は、こうした感情を政治的エネルギーとして転化できないものかと考え、辿りついたのがSNSの政治への利用であった。
現代政治の舞台裏で暗躍するとされる彼らスピンドクター(情報を操作する者)の手法は狡猾だ。SNSでクリックされた「いいね」の数やネット上での行動動向を数値化したビッグデータを企業から買い取り、最大限かつ効率的に活用する。そこから支持者になりそうな人々を割り出し、個人向けにカスタマイズされたダイレクトメールを送信する。対象となる人数は数10万とも数100万ともいわれている。送られる内容に政治的一貫性はなく、効果的であれば陰謀論でも排外主義でも躊躇せず用いる。彼らの目的が政策実現にあるのではなく、自分たちの利益と権力奪取にのみあるからだ。
量子政治学の時代
したがって、量子政治学において各自が眺める世界は、文字通り他者には見えない。よって、合意の形成はますます難しくなる。合意するには「他者の立場になって考える」必要があるが、アルゴリズムが司る現実では、この作業は不可能だ。誰もが自分の殻に閉じこもり、殻の中では、聞こえてくるのはお馴染みの声だけであり、存在するのもお決まりの事実だけだ。(本書178ページ)
ビッグデータの利用が、政治を取り巻く条件を劇的に変えてしまった。合意を目指すのではなく、人びとを扇動するための過激な意見を組み合わせ、怒りによって人びとを結び付ける、という政治手法が主流となりつつあるという。
著者は不確実性と複雑性が増大するこうした現代の政治状況を「量子政治学の時代」と名付ける。
この時代を生きる人々の多くは、SNSを見ることに多くの時間を費やしている。サービスを提供する多くの企業は利用者の注意を引きつけるために、日々アルゴリズムを進化させている。スピンドクターたちもそれに合わせてその手法をより効率化する。「政治家になりたいのなら政治学よりも量子力学を学ぶべきだ」とうそぶく人物すらいるという。
またこうした状況に拍車を掛けているのが、情報機器の発達が生み出した個人の「原子(アトム)化」だ。スマートフォンの画面に映し出される個人向けにカスタマイズされた情報は、共通の事実という感覚を希薄にしていく。またワンクリックさえすれば欲しいものを手に入れられるという利便性は、ものごとの決定に手間と時間を要する議会制民主主義への反発を生む。かつては情報機器の発達によって世界が一体化すると考えられていた。しかし結果的には分断を生み出した。精神の閉鎖性は強まり、刺激に満ちた言説に魅力を感じるようになってしまった。
極端な時代を乗り越えるためには
前向きのメッセージや物語を生み出すことそのものは難しくない。難しいのは、それらが人びとの関心を引きつけ、さらには人びとを行動に駆り立てるだけのエネルギーをそなえているかどうかだ。(本書192ページ)
著者の分析によれば、こうした時代が到来する以前に政治家の語る言葉に大きな変化があった。かつては選挙民に対して現実を踏まえたうえで‶戦争なき世界〟や‶貧困の克服〟など理想的で前向きなメッセージを語っていた。しかし、いつのまにか現実に埋没し‶数値〟や‶利害関係〟のみを語るようになってしまった。この変化が選挙民に大きな不安と失望をもたらした。ここに今日の政治状況を生み出した遠因があるという。
現在の政治状況を打破するためには、人々を前向にする肯定的なメッセージを語る高邁な理想を持った政治家の登場が望まれる。だがなによりも重要なのは、私たち選挙民の姿勢そのものであろう。非寛容で、憎悪と分断のみを生み出す政治を求めるのか。それとも様々な人びとの熟議と合意によって問題を解決していく政治を求めるのか。
日々の生活のなかで触れる膨大な情報に流されるのではなく、自分は政治に対して何を望むのかを明確にしていく。私たちは熟考する術を身につける必要があるといえよう。
『ポピュリズムの仕掛人:SNSで選挙はどのように操られているか』
(ジュリアーノ・ダ・エンポリ著、林昌宏訳/白水社/2025年3月10日刊)
関連記事:
「小林芳雄」記事一覧