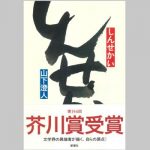ありきたりの青春小説らしからぬ青春小説
山下澄人(やました・すみと)著/第156回芥川賞受賞作(2016年下半期)
舞台は、実在した北海道の演劇塾
山下澄人の作品が初めて芥川賞候補になったのは、2012年。その後、立て続けに候補となり、2016年、4回目の候補作「しんせかい」で芥川賞を受賞。当時50歳。その20年前の1996年には「劇団FICTION」を立ち上げ、今に至るまで主宰しているので、小説よりも演劇活動の方が長い。
「しんせかい」は、有名な脚本家が北海道に設立した演劇塾が舞台だ。語り部は、作者と同名の「スミト」なので、私小説と言っていいだろう。作者のプロフィールを見ると、確かに2年間、その演劇塾に在籍している。
物語は、俳優と脚本家を夢見る若者たちが、何もない北海道の大地の中で、共同生活をするための建物を建て、生活費を稼ぐために農作業に従事し、その合間を縫うように演劇の勉強をする。そこでの生活は、周辺の地元民からは「収容所」と呼ばれるほどの過酷なものだった。
もちろん小説であるから実体験と創造が入り混じっていることは当然だとしても、実在した演劇塾に対する興味は読者としてかき立てられる。ところが、物語としての本作品は、極めて淡白なのだ。役者や脚本家を夢見て全国から集ってきた若者たちが、ある種閉ざされた環境の中で、誰もが知る有名な脚本家の下で学ぶわけだから、複雑な人間関係の中における優越感や劣等感や嫉妬等々のさまざまな感情が渦巻いているはずなのだが、そうしたものがほとんど描かれていない。描かれているのは、北海道の厳しい自然環境下における辛い労働や生活、周辺の農家の人たちとの触れ合い、たまに男女の問題、そして関西に置いてきた元彼女との手紙のやり取り程度で、青春小説の王道とも言うべき人間同士のぶつかり合いや、葛藤や苦悩や希望といったものがほとんどないのだ。
そうした作品の性質からなのか、選考会は、村上龍の選評によると、賛否両論がぶつかり合うエキサイティングな選考会とはほど遠い、「わたしの記憶と印象では、熱烈な支持も、強烈な拒否もなく」という状況だったようだ。
不支持の選評から見てみよう。まずは村上龍から順に。
村上龍
「強烈な要素が何もない。そして、わたしは、『それが現代という時代だ』と納得することはできない。(中略)『良い』でも『悪い』でもなく、『つまらない』それだけだった」
髙樹のぶ子
「モデルとなった塾や脚本家の先行イメージを外すと、青春小説としては物足りないし薄味。難解だったこれまでの候補作にも頭を抱えたが、このあっさり感にも困った。青春小説とは、何かが内的に起きるものではないのか」
宮本輝
「実際に存在した北海道の演劇塾での一年間には、もっとどろどろした人間の葛藤があったはずだが、作者はそれを避けてしまっている。その点も大きな不満だった」
青春の欠落の痛み
不支持の理由はいずれも共通していたが、支持した選考委員は、逆に、この淡白さを評価している意見が多かった。
小川洋子
「山下さんは主人公の心を一切描こうとしない。(中略)ここに文学があるはずだ、と皆が信じている場所を、山下さんは素通りする。言葉にできないものを言葉にする、などという幻想から遠く離れた地点に立っている。そこから見える世界を描けるのは、山下さん一人である」
堀江敏幸
「語り手スミトの言動には、(中略)ただの青春回顧に収まらない、はみ出したものへの、またその結果欠落したものへの凝視がある」
吉田修一
「読後、受け取ったのは壮大な空振り感だった。十九歳。たいていの十九歳は、自分がいる場所を生ぬるく感じている。そう感じるのが十九歳の特権でもある。おそらく今作の主人公もまた、この生ぬるさが厭で、例えば『俺は誰かに胸ぐらを掴まれたいんだ』くらいの気持ちになって【谷】へ向かったのだと思う。ただ、やはりそこにも胸ぐらをつかんでくれるような人はいない。しかし、それが現実であり、人生であると気づく十九歳。この空振り感。そしてこの空振り感と出会えたことが、その後の人生をどれほど豊かにしたかに気づく五十歳。この三十年余りの距離こそが、本作を一流の青春小説に成らしめている」
おそらく主人公は、役者に絶対になるのだという大望を持って塾に参加したというよりも、自分の今いる場所への違和感や、このまま大人になっていく生ぬるさに対する嫌悪感を切り捨てたいという望みをかけて、北海道に向かったのではないか。
だからこそ、演技の上手い下手や、先生からの評価などに対して他の生徒ほど敏感ではない。必然的に他の生徒との軋轢も少なくなる。けれども、決して満たされているわけではない。
むしろ、どこに行っても何をしても満たされない自分を目の当たりにして、より一層自身の「欠落」を感じたのではないか。そう考えると、本作は、ありきたりの青春小説を超えた青春小説と言える。
時折見せる、ガラスの破片が青くキラリと光るような、叙情的な美しい風景描写が、主人公の「欠落」を切なく映し出している。
「芥川賞を読む」:
「芥川賞を読む」一覧
第1回『ネコババのいる町で』 第2回『表層生活』 第3回『村の名前』 第4回『妊娠カレンダー』 第5回『自動起床装置』 第6回『背負い水』 第7回『至高聖所(アバトーン)』 第8回『運転士』 第9回『犬婿入り』 第10回『寂寥郊野』 第11回『石の来歴』 第12回『タイムスリップ・コンビナート』 第13回『おでるでく』 第14回『この人の閾(いき)』 第15回『豚の報い』 第16回『蛇を踏む』 第17回『家族シネマ』 第18回『海峡の光』 第19回『水滴』 第20回『ゲルマニウムの夜』 第21回『ブエノスアイレス午前零時』 第22回『日蝕』 第23回『蔭の棲みか』 第24回『夏の約束』 第25回『きれぎれ』 第26回『花腐し』 第27回『聖水』 第28回『熊の敷石』 第29回『中陰の花』 第30回『猛スピードで母は』 第31回『パーク・ライフ』 第32回『しょっぱいドライブ』 第33回『ハリガネムシ』 第34回『蛇にピアス』 第35回『蹴りたい背中』 第36回『介護入門』 第37回『グランドフィナーレ』 第38回 『土の中の子供』 第39回『沖で待つ』 第40回『八月の路上に捨てる』 第41回『ひとり日和』 第42回『アサッテの人』 第43回『乳と卵』 第44回『時が滲む朝』 第45回『ポトスライムの舟』 第46回『終の住処』 第47回『乙女の密告』 第48回『苦役列車』 第49回『きことわ』 第50回『道化師の蝶』 第51回『共喰い』 第52回『冥土めぐり』 第54回『爪と目』 第55回『穴』 第56回『春の庭』 第57回『九年前の祈り』 第58回『火花』 第59回『スクラップ・アンド・ビルド』 第60回『異類婚姻譚』 第61回『死んでいない者』 第62回『コンビニ人間』 第63回『しんせかい』 第64回『影裏』