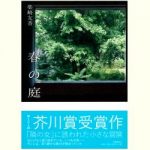移り変わる街の中に隠された人間の息遣い
柴崎友香(しばさき・ともか)著/第151回芥川賞受賞作(2014年上半期)
他人事のように淡々と描く
柴崎友香の「春の庭」は、『文學界』に掲載された170枚の作品。4回目の芥川賞候補での受賞となった。
世田谷のアパートで暮らす太郎は、同じアパートの西という女性の奇妙な好奇心に引っ張られていく。それは、アパートに隣接する個性的な一軒家の中を見てみたいという好奇心である。
「春の庭」とは、その一軒家の部屋や庭を撮影した写真集のタイトルでもある。西は、当時住人だった夫婦の生活の様子も収められているその写真集が好きで、実際に目の前にあるその家の内部を見たいと思い続けていたのである。
この作品の概要を分かりやすく説明するのはなかなか難しい。最終的には、とあるきっかけから新しく転居してきた家族に招待されたことで、その家の内部をまじまじと見ることができるようになったのだが、物語の規模は、小さく狭い。人生を揺るがすような出来事が起きるわけでもなく、喜怒哀楽がうねるわけでもない。世田谷という町のごく限られたエリアで起きる些細な出来事を淡々と書き連ねていくのだが、そこからは、どこか懐かしく切ない、けれども何か少し不気味な空気が滲み出すのである。
その正体は何なのかと考えれば、新しい人が越してきて知らぬ間にいなくなり、また新しい人が越してくるという、都会ではどこにでもありそうな風景や記憶の中にあるもの――全てのものは確実に淡々と移り変わるという時の流れの寂しさやノスタルジー、あるいはそこに眠っている過去の人間たちの歴史の欠片――などが、湿り気を伴うことなくサラリと風のように物語の中に流れているからであろう。
作家の中には自分が固執するテーマや題材を持つ者も多いが、柴崎友香は、自分の居る場所への違和感や不安感を書いてきた作家のようだ。ただ、本作は、類似のテーマではあるものの少し異なる手法で書いたことで受賞に至ったようだ。
宮本輝はこう評価する。
柴崎さんは終始一貫して、街、町、道、路地、建物といったものになにかの生命のようなものを感受して、その正体を暴こうとしてきた。その試みは対象物と自分の目線とをいつも同じ高さに保つことで繰り返し行われてきたのだ。しかし、『春の庭』では、作者の目は俯瞰的である。この大きな変化が、町や建物のあちこちで生きてうごめいている人間たちを読む者に見せたのだ
俯瞰的というのは、別の言い方をすれば客観的ということでもあろう。書き手が意図するものを伝えるためには、何らかの偏りをもって主観的に描写することが普通だが、「春の庭」における描写は、そういったものが極めて少なく、他人事のように淡々とした描写が続く。これについて島田雅彦は、こう述べている。
通例、小説では作者のフィルターを通じて、加工され、焦点化された現実が写し取られているのだが、柴崎友香はそうしたフィルターを外し、多焦点カメラに映った現実を列挙してゆく。(中略)現実の出来事は誰かの関心を惹こうとか、物語としての説得力を高めようという意図など全く入り込む余地がない。柴崎友香はそうした「ぶっきらぼう」な現実の前で謙虚でいることを選ぶ。これはなかなか真似ができないことである
意図しないものが現れる
川上弘美は、「香るもの」があったと述べているが、この「香るもの」の正体について、
書かれた言葉だけから読みとることのできる意味や雰囲気といったもの以上の、その小説を書いた作者にとっても未知の、何かが立ちあらわれてくる、そういうもののことを指します
と述べている。
言語化できないような、自分でもその正体がつかみかねているような、それでも描きたい何かを書き切るということは、難しい。
安易な表現をしようものなら一気に陳腐なものに成り下がるわけで、粘り強くしつこく手探りで積み重ねるように描く執念と、技量が求められる。その時に初めて「作者の意図しなかったものが小説から現れる」ということなのだろう。
多くの選考委員がその才能を高く評価する一方で、村上龍は不満を抱えていたようだ。長時間となった選考会だったが少しもスリリングではなかったと述べた上で、
どの作品からも、切実さが感じられなかった。この『生きづらい社会』で、伝えるべきこと、つまり翻訳すべき無言の人々の思いが数多くあると思うのだが、どういうわけか、「不要な洗練」「趣味的」という二つの言葉が、全体的な印象として残った
と述べている。
「芥川賞を読む」:
第1回『ネコババのいる町で』 第2回『表層生活』 第3回『村の名前』 第4回『妊娠カレンダー』 第5回『自動起床装置』 第6回『背負い水』 第7回『至高聖所(アバトーン)』 第8回『運転士』 第9回『犬婿入り』 第10回『寂寥郊野』 第11回『石の来歴』 第12回『タイムスリップ・コンビナート』 第13回『おでるでく』 第14回『この人の閾(いき)』 第15回『豚の報い』 第16回 『蛇を踏む』 第17回『家族シネマ』 第18回『海峡の光』 第19回『水滴』 第20回『ゲルマニウムの夜』 第21回『ブエノスアイレス午前零時』 第22回『日蝕』 第23回『蔭の棲みか』 第24回『夏の約束』 第25回『きれぎれ』 第26回『花腐し』 第27回『聖水』 第28回『熊の敷石』 第29回『中陰の花』 第30回『猛スピードで母は』 第31回『パーク・ライフ』 第32回『しょっぱいドライブ』 第33回『ハリガネムシ』 第34回『蛇にピアス』 第35回『蹴りたい背中』 第36回『介護入門』 第37回『グランドフィナーレ』 第38回 『土の中の子供』 第39回『沖で待つ』 第40回『八月の路上に捨てる』 第41回『ひとり日和』 第42回『アサッテの人』 第43回『乳と卵』 第44回『時が滲む朝』 第45回『ポトスライムの舟』 第46回『終の住処』 第47回『乙女の密告』 第48回『苦役列車』 第49回『きことわ』 第50回『道化師の蝶』 第51回『共喰い』 第52回『冥土めぐり』 第54回『爪と目』 第55回『穴』 第56回『春の庭』 第57回『九年前の祈り』