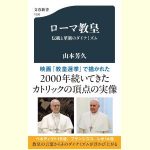脱色された日本の報道
ローマ教皇は、世界に14億人の信徒を擁する宗教・カトリックを代表する存在である。
著者の山本芳久氏は、東京大学大学院の教授で、中世の哲学者・神学者トマス・アクィナス研究の第1人者であり、またアリストテレスやイスラム教、ユダヤ教などの研究でも知られる。
本書『ローマ教皇 伝統と革新のダイナミズム』は、ベネティクト16世(在位2005年-2013年)、フランシスコ(在位2013年-2025年)、レオ14世(在位2025年-)といった現代のローマ教皇の宗教文書を読み解くことによって、これまで日本で知られていなかった実像に迫るものだ。
我が国のキリスト教の信徒は全人口の一%程度に過ぎないのであるから、キリスト教の根本精神とは何かというような観点が表に出てこないのはある意味当然のことかもしれないが、それでは教皇について的確に理解することはできない。(本書70~71ページ)
2025年に行われた教皇選挙(コンクラーベ)は、同時期に映画『教皇選挙』が上映されたこともあり、日本でもこれまでにない関心を集めた。またローマ教皇の時局に対する発言がニュースでとりあげられることも少なくない。
しかし、その発言の根に流れるカトリックの教義や伝統に目を向けられることはない。いわば「宗教的脱色」をされた形でしか報道されることはなかった。これでは教皇の発言の真意は理解されず、ミスリードがおきかねない。
海外では「バチカニスタ」や「バチカンウォッチャー」と呼ばれるカトリック報道の専門家が存在するが、日本には皆無である。このような状況ではローマ教皇の実像が伝わらないというのも、もっともな話だ。
ソフトパワーのみで世界に対峙する
教皇が「神の僕(しもべ)たちの僕」だというのは、教会全体の制度設計、教会外との交流と対話など、様々な働きを通じて信徒一人ひとりの、そして信徒であるか否かという枠組みを超えて人類全体の共通善のために働きをなすということであるが、そのなかでも最も重要な教皇の働きは、「言葉を語る」ということである。(本書72ページ)
ローマ教皇は、全世界から招集された枢機卿たちの秘密選挙によって選出される。こういうと、権謀術数渦巻く熾烈な政治闘争を思い浮かべる人も多いだろう。だが、それは想像の産物にすぎない。
フランスの著名な知識人ジャック・アタリは、選挙の直前に行われる総会に注目する。総会では、現在の世界とカトリックの直面する問題が徹底的に議論され、そのうえで、浮かび上がってきた課題を解決するために適切な人物が候補として絞り込まれていく。
候補者の中から選ばれた教皇は、カトリックでは初代ペトロの後継者であり、神の代理人として位置付けられる。また、2000年という歴史のなかで培われてきた教義と伝統を中核的に担う。そして、もっとも重視される役割が、その教えを現代の文脈で語り直すことである。
教皇が語る言葉の大きな特徴は、問題提起能力である。信仰が異なる人でも、提起された問題を共有することによって、自分なりの答えを出せるような構成になっている。そうした文書や発言は、教皇個人の独自の物ではなく、複数の専門家が多角的に検討、編集したうえで発表される。現代の最先端の知見と伝統的な知恵が有機的に結合してできたものなのだ。
さらに見逃してはならないのは、ローマ教皇が国家元首という点だ。軍隊を持たないバチカンはソフトパワーのみによって世界に影響を与えている稀有の国家でもある。その中心にあるのが教皇の語る言葉なのである。
現代の課題に応える動的伝統
これは、「伝統に対する固定的な理解をとにかく墨守(ぼくしゅ)せよ」と説く保守反動的な立場でもなければ、「伝統などどうでもよい」という伝統軽視的な立場でもない。「伝統」とは単なる過去の遺物ではなく、生きた現実として時代とともに理解が深まっていくものなのである。(本書113~114ページ)
教皇の言葉の源泉には、「信仰の遺産」と呼ばれるカトリックの伝統がある。伝統という言葉には保守的なイメージがあるが、実はそうではない。信仰的核心は保持しながら、時代の課題に応答していくことによって、伝統は表現が磨かれ成熟し、豊かさを増していくものと考えられている。このことを象徴的に表している言葉が「伝統は動く」というものだ。その分かりやすい事例が本書で紹介されている「正戦論」に関する議論だろう。
正戦論とは、正当な戦争の在り方を考察するもので、カトリックの伝統では戦争を厳しく抑止するためのものとして認められてきた。しかし広く解釈されてしまえば、全ての戦争が正当化される危険性もある。
フランシスコは、晩年に発表した文章で戦争の不支持を表明した。その際、伝統的に正戦論が由来すると考えられているアウグスティヌスの文章を用いることによって、戦争を否定する理論的根拠としたのだった。
2000年にわたる伝統といっても、歴代の教皇や多くの神学者による思考の成果によって形成されており、そこにはさまざまな思想の種子が含まれている。そこに立ち返ることによって、時代の要請に応え得る革新的なビジョンを生み出していく。保守や革新という安直な二項対立に収まることがないダイナミズムにこそ、カトリックの伝統の特徴がある。
フランシスコはまた、「教皇」という言葉にも新しい息吹を吹き込んだ。その語源へと立ち返り「橋を架ける者」という意味が含意されていると位置づけた。過去と現在に橋を架け、分断された世界や人々に橋を架ける。それが自身の使命であると考えたからであった。また環境破壊が深刻化し戦禍絶え無き現代社会において、カトリックだけではなく世界宗教が果たすべき役割をそこに見出しているからではないだろうか。
カトリック信徒の人口が全人口の0.34%しかおらず、宗教者に対する偏見が強い日本社会でローマ教皇の実像を伝えようとする本書もまた、〝橋を架ける〟という著者の信仰的実践から生まれたものであろう。
『ローマ教皇 伝統と革新のダイナミズム』(山本芳久著/文春新書/2025年8月20日刊)
関連記事:
「小林芳雄」記事一覧