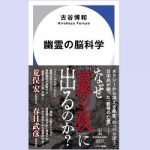幽霊を見る患者との出会い
気温が高い日々が続くと、昔から日本人は背筋が冷たくなるような怪談話を好む。現在でも、テレビのみならずYouTubeでも怪談チャンネルが人気を博している。
本書『幽霊の脳科学』は、日本各地に伝承されてきた幽霊譚や落語の怪談噺などを題材に採り、脳科学者の立場から論じたものだ。
著者はこれまで脳神経内科医として勤務し、主にパーキンソン病などの神経・筋疾患の研究を行ってきた。医師である著者が「脳と怪談」の関係を真面目に考えるきっかけとなったのは、1人の患者との出会いであったという。
この患者さんを診ていて私が思ったことは、「患者さんの体験した幻覚はまさに幽霊譚であり、同時に脳機能障害もあったということは、逆に脳神経系の部分的な機能障害に伴って幽霊を見る症状が出現する可能性は考えられないだろうか」ということでした。(本書19ページ)
患者は60歳の男性で、笑顔を絶やさぬ穏やかな人物であった。しかし最近、幽霊が見えるようになったと言い始めた。当初の診断では、視力や視野、運動機能や感覚機能に問題はなかった。しかし、詳しく検査を進めると高次脳機能障害のあることが判明し、また睡眠障害があることも分かった。治療により、その改善を試みたところ、幽霊を見ることはすっかりなくなったという。
以前から幻視や幻覚を伴う疾病はいくつか知られていた。だが、そのメカニズムは明らかではなかった。しかし、近年、脳神経科学のうち特に睡眠分野の研究の進展によって、飛躍的に解明が進んだ。これらの研究成果を用いると、一般的に心霊現象とされるものの大半が、実は幻視・幻覚の症状に当てはまり、著者によれば、少なくともその7割は医学的に説明可能であるという。
タクシー怪談の恐ろしい真実
今述べた、路傍に出現して車に乗り込んでくる幽霊の特徴は、入眠時幻覚のそれとよく一致しています。「体がぞーっとする」「ヒヤーッとする」という感覚も体感幻覚の一種と考えられます。(本書68ページ~69ページ)
よく知られている幽霊話しにタクシー怪談というものがある。人気のない一本道でタクシーを運転していると、白い洋服を着た女性が手を挙げて立っている。客だと思いタクシーに乗せてしばらくたつと、何となく寒気がする。ふり返って座席を見ると女性は消えていた――というものだ。
著者の分析によれば、これは超常現象などではなく、「高速道路催眠現象」と呼ばれるものだ。人間は肉体的、精神的に疲労をすると睡眠障害が起こりやすくなる。そうした状態で真っすぐな道で車を運転していると、一瞬睡眠状態に入ってしまうことがある。このとき本人は眠っているという自覚がなく、夢の中で存在しない客と話をしていることや、ヒヤーッとした感じを体感することがあるというのだ。
もしこのまま曲がり道にさしかかれば、大事故につながる可能性もある。著者が示すタクシー怪談の真実は、幽霊よりも恐ろしいものだ。
科学的視座から物事を考える重要性
もちろんこれも仮説の一つにすぎませんが、不思議な現象に対してはすぐに「超常現象」に逃げ込むのではなく、ありとあらゆる知識を総動員して色々な仮説を考えて、それを実証する実験や研究を考えてみることも大切です。(本書62ページ)
著者が医師として怪談に真摯に取り組むのは、幽霊を見るのは気の迷いや特別な感覚が具わっているからではなく、疾病などの原因によって脳の機能に何らかの障害が生じている可能性が高いからだ。こうした症状を放置しておけば、病気がより重症化することもあり、場合によっては生命に関わる危険性すらある。
また、幻視や幻覚という症例がある動物はじつは人間だけである。これは人間の脳が生物的に進化してきた過程と結びついている。特に高次機能と密接な関係があるようだ。これまで伝わってきた怪談を分析することによって、人類の脳が辿ってきた進化の過程を考える手がかりにもつながっていく。
さらに興味深いのは文化が異なると、幽霊の評価も異なるという点だ。日本では幽霊が出る家は気味悪がられるが、欧米では物件の価値が高まることもあるという。さらに幽霊となって現れる人物は、日本では身近な人だが欧米では歴史的人物が多い。こうした違いは、宗教による生死観によるものではないかという。
評者が特に疑問をもったのはこの「生死観」についてである。
日本ではほとんどの人が我が家の宗派を仏教系と自認している。しかし、仏教は基本的に霊魂思想を否定している。多くの人が幽霊を信じているのは、仏教思想が浸透しなかったからなのか。それとも土着の霊魂思想に飲み込まれてしまったからなのか――こうした日本人の生死観を巡る問題は極めて興味深い。
著者が一貫して訴えているのは、神秘的な現象を目の当たりにしたときに、超常現象という言葉に逃げ込むことなく、論理的、実証的に考えようとする科学的思考の重要性だ。
かつてオウム真理教による地下鉄サリン事件が起きたとき、その信者のなかに多くの理系大学出身者がいた。彼らは自らの神秘体験を超常現象と位置付け、狂信からテロ行為に走った。著者はこうした人たちには、科学的視点が欠けていたと断じている。あの悲劇を繰り返さないためにも、理系教育には単なる知識の詰め込みではなく、科学的思考を養うことが望まれる。
あらゆる物事を論理的、実証的に考えようとする冷徹な科学的な思考と、悩み苦しむ人の声を受け止めようとする温かな医師としてのヒューマニズム。一般的に非科学的とされがちな「怪談」を科学的に分析し、人間存在がもつ謎に迫ろうとする本書のユニークな視点は、この2つの思考の結合から生まれたものだろう。
『幽霊の脳科学』(古谷博和著/ハヤカワ新書/2025年8月15日刊)
関連記事:
「小林芳雄」記事一覧