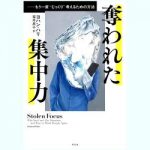集中力の衰退を招いた原因とは
著者ヨハン・ハリは、日常的な問題を綿密な調査と取材によって徹底的に掘り下げることに定評があるジャーナリストであり、世界的なベストセラー作家である。
本書『奪われた集中力』では「なぜ人々は集中できなくなったのか」という問題をとりあげている。3カ月間、インターネットを遮断した環境に身を置き、さらに世界を駆け回り、250人を超える有識者にインタビューを重ね、その核心に迫る。
ぼくらの多くにとって読書は、経験することができるもっとも深い集中が形になったものだ――人生におけるたくさんの時間を、冷静に、心を静めて、一つの話題に費やし、心に浸透させていく行為だからだ。これを手段として、過去四〇〇年にわたる思想の大きな進歩がほぼ理解され、説明されて来た。その経験が今、一気に減少しているのである。(本書90ページ)
集中力の萎縮を象徴するのが〝読書の衰退〟である。紹介されている調査によれば、現在、読書を娯楽とする米国人の割合は過去最低であり、1年間に1冊の本を読まなかった人の割合は57パーセントに達するという。
読書の衰退は社会的に波及効果をもたらす。本書で紹介されている識字学研究によれば、読書をすることによって、人間は長時間1つの話題に集中する直線的な読み方を学ぶのだという。ところが画面で読むことに馴れてしまうと、必要だと思われる情報だけを目で追う斜め読みが習慣化され、読解力が著しく減少する。これは「スクリーン劣性」と呼ばれるものだ。こうして次第に読書をする人は減少していった。
特に、小説を読むことには意外な効用がある。多くの小説を読んだ人とそうでない人を比べた社会学者の調査では、小説を読んだ人の方が他人の感情を読み取る能力が高いと判明した。さまざまな時代や文化、人物を思い浮かべながら、丁寧に文字を追う。そうした行為がことなる立場の人へ心を開き、共感する力を養う。
集中力の萎縮は、読解力だけでなく、共感する力をも萎縮させてしまう。
スマホはなぜ集中力を奪うのか
スマホの登場によって確かに、生活の中で気が散る回数がある程度増えただろう。だが、集中力が続かなくなったというダメージの大きさは、もっとひそかなことによって引き起こされている。スマホそのもののせいではなく、スマホのアプリやパソコンで見るウェブサイトがどう設計されているかということなのだ。(本書141ページ~142ページ)
スマホやタブレット端末の登場が、インターネットへの接続を容易にし、人びとの集中力を奪っている――こうした議論はよく聞かれる。しかし著者は、IT産業の中心地・シリコンバレーで働いていた元技術者へのインタビューによって、問題はより複雑なものであると気づく。
世界的な大手ウェブサイトを運営する企業は、人びとが閲覧することによって収入を得ている。少しでも長く閲覧者がサイトに留まれば、それだけ利益が増加する。そのため工学技術だけでなく心理学なども総動員して、人びとの目をくぎ付けにするための開発競争が行われるようになった。インタビューに応えた元技術者たちは、はじめは便利な機能を開発すれば社会に貢献できると考え、仕事に没頭していた。だが次第に自分たちの開発している技術が人びとの集中力を奪い生活を台無しにしているのではないかという疑念にとらわれ、その多くがシリコンバレーを去っていった。
「ウェブサイトの閲覧」というと広告収入を連想するが、それは一面にすぎない。運営企業はメールの内容や検索ワード、地図サイトの利用履歴など全てをデータ化し、そのデータを広告主に売り払い莫大な収益を上げる。また閲覧数を上げるために、より過激な関連動画などに誘導するようにあらかじめプログラミングされている。
問題は、閲覧者の注意力を利益に結び付けるウェブサイトの仕組みにこそある。大手企業への政治的規制など、具体的な措置をとらない限り、状況は変化しないと著者は考えている。
重要なのは社会のあり方を考えること
残酷な楽観主義――失敗する結果にしかならないような単純化したストーリーを語ること――に代わるものは、何も変えられないという悲観主義ではない。本物の楽観主義だ。自分の目標に向かう道筋に立ちはだかる障壁をそのまま認識し、そうした障壁を一つずつ取り除いていくためにほかの人びとと協力する計画を立てることである。(本書172ページ)
私たちから集中力を奪っているのは、テクノロジーだけではない。たとえば睡眠時間の減少と労働時間、マルチタスクを課せられる生活の在り方、子供時代の試験勉強の増加と遊びの減少なども関連している。著者は多角的に問題を検討し、その根本にあるのは現代文明の加速化であるという事実を知るに至った。
社会人類学者が示したデータによると、集中力の低下はインターネットの登場によって著しく進んだが、じつはかなり以前の1880年頃から徐々に低下してきたというのだ。
その時代に起きた社会的変化とは産業革命である。産業革命以来、経済成長を至上目標とした近代文明は約10年ごとに生活を加速化させ、そのひずみが現在、集中力の欠如という形となって、私たちの前に現れているのだ。そうした社会的課題は、昨今流行している自己啓発やマインドフルネスなどが説く、個人の行動形式や意識の変化のみで対処することは非常に難しい。こうした安易な自己責任論に基づく考え方を著者は「残酷な楽観主義」と呼ぶ。
集中力の欠如は個人のみに関わる問題ではない。政治的課題や環境問題に持続的に取り組むことが困難になってしまう。だからこそ、私たちは社会の行き過ぎた加速化を見直さなければならない。
集中力を巡る旅の果てに著者が見出したもの、それは現代文明の危機である。
『奪われた集中力:もう一度〝じっくり〟考えるための方法』
(ヨハン・ハリ著、福井昌子訳/作品社/2025年6月10日刊)
関連記事:
「小林芳雄」記事一覧