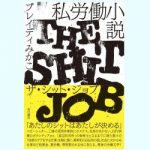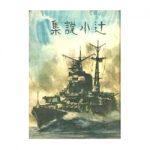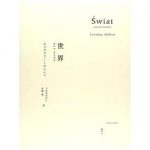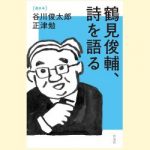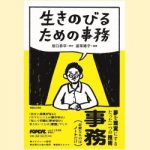人類学者のデヴィッド・グレーバーが、『ブルシット・ジョブ』という厚い本を出した。高額な報酬を得ているけれど、社会や人々にとって、あまり役に立っていない仕事を批判している。これは、コロナ禍でエッセンシャルワーカーが注目されたのとパラレルな出来事だ。
社会を営み、人が生活するうえで、不可欠な仕事が、エッセンシャルワークだ。医療従事者、介護士、教師、清掃員など、その人たちがいなければ、僕らの社会は回ってゆかない。
それに比べて、ブルシット・ジョブは、受付係、顧問弁護士、企業のコンプライアンス担当者、中間管理職など、いなかったとしても、誰も不自由を感じることのない仕事ばかりだ。
仕事本の類は少なくないけれども、多くの人がなんとなくそう思いながら、言葉にならなかったことを指摘した仕事本は、初めて読んだ。グレーバーは偉い。と、いいながら、今回取り上げるのは別の本である。
ブレイディみかこの『私労働小説 ザ・シット・ジョブ』だ。帯のコピーは本作を、「社会に欠かせぬ仕事ほど低賃金、重労働、等閑視される世に投じる、渾身の労働文学!」と銘打っている。 続きを読む