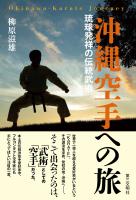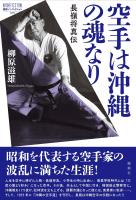毎回「自由組手」を行う
サンチンに始まり、カンシワ、カンシュウと3つの型を終えると、新城会長が何やら個別に指示を始めた。グローブをつけて出てきたのは10人中6人の門下生たち。相手を掴めるタイプの赤と青のグローブをそれぞれ着けて、「自由組手」の時間が始まる。
通常の稽古はサンチンで始まり、型の分解などを行って、小手鍛えを行い、最後に組手で締めるのが通常のパターンということだった。
ワン・ミニッツ!
新城会長が時間を宣言すると、最初に白帯と緑帯の門下生がそれぞれ「1分間」向き合う。通常の競技の試合のように、片方が気合の声を鋭く発した。現役時代、組手の試合で大きな結果を出した新城会長の道場だけあって、いまも門下生の中から組手の全国大会に出場する〝猛者〟が後を絶たない。それも小学生から中学、高校、大学、国体まで年齢層も幅広い。
上地流の実戦スタイルは、相手の攻撃を受けたままその手で相手の腕をつかみ、引っ張りながら別の手で(顔面を)叩くというのが基本パターンというが、それをそのまま全空連(全日本空手道連盟)方式の試合で使えば即〝反則〟となる。そのため本来の上地流の技法と区別する意味で、選手養成の場として稽古の中に自由組手の時間が設けられているという説明だった。

自由組手で向き合う2人の黒帯
見ていると、やはり全空連方式の組手スタイルに似て、リズムを取りつつ、間合いを一気に詰めて突きを入れるパターンが多かった。それでもそのスタイルにとどまらない人もいる。新城会長が、ポイントが入ったとみるとすぐに宣言した。
上段突き有効!
一本!
一本が入ったときは、外国人(黒帯)の上段回し蹴りが相手の顔面に決まったときだった(実際は危険防止のため寸止めだった)。
この日の自由組手は6人が相手を変えて各2セット行った。通常は、怪我をしている人を除いて全員行うという。この日は取材用に選ばれた人数で行ったということだった。
上地流の組手試合は、本土のフルコンタクトの極真空手などと違い〝顔面突き〟を有効打としてカウントする(ただしあくまで寸止めを前提とする)。だが寸止めでも顔面に有効打が入ったと判定されればポイントになるため、極真の試合は顔面の防御が疎かになりがちだが、上地流ではそうはいかない、ルール上派生する違いがある。

カンチンの小拳(人差し指一本拳)で突く場面
新城会長の説明によると、組手の競技選手を終えた後、上地流の型に沿った実戦的な姿を教えていくとの指導方針とのことだった。
県庁幹部も汗を流す流派
組手が終わると、飛び散った汗を拭きとるため数人によるモップ掛けが始まった。全員整列し、これでこの日の稽古は終わりかと思いきや、最後に全員で型を行った。
この日まだ行っていなかった残り5つの型を通して行うという。順にセーチン(十戦)、セーサン(十三)、セーリュウ(十六)、カンチン(完戦)、三十六(サンセーリュウ)の5つだ。
見ていると、セーチンが終わって白帯が1人抜け、セーサンが終わって緑帯が抜け、セーリュウが終わって黒帯1人がさらに抜けた。最後のカンチンと最も難易度の高いサンセーリュウを7人(黒帯のみ)で行った。
稽古がすべて終了し、時計の針をみると20時30分すぎ。開始から1時間20分の濃密な時間だった。
大まかな(稽古の)内容は紹介したつもりです。
新城会長が語った。拳優会の昇級昇段審査は上記の組手も必須項目となり、8種類の審査項目がある。昇級審査は年6回奇数月に行われ、昇段審査は年2回、5月と11月に開催される。

上地流で最も難易度の高い型サンセーリュウ
ちなみに道場の入り口では入るときと出るときに、怪我のない稽古を祈り、かしわ手を2回打つのが習わしになっている。
話は変わるが、拳優会では玉城デニー沖縄県知事も汗を流しており、知る人ぞ知る存在となっている。もともと知事公室長を歴任した池田竹州副知事が拳優会松崎道場(県警察ОB)の門弟で、そのつながりでデニー知事も稽古を始めたそうだ。稽古場は県庁裏手にある警察本部の武道場。教育長も稽古に励むという。
現在の拳優会は県内に11道場をもち、海外18カ国に8000人の門弟を抱える。多いのはインド、アルゼンチン、カナダという。
ちなみに新城会長は、沖縄県空手道連盟(県空連)を設立(1981年)した戦後の沖縄空手界のリーダー的存在だった長嶺将真(ながみね・しょうしん 1907-1997)から「嘉手納の新城」の呼び名で可愛がられた。長嶺が沖縄県警の嘉手納署に勤務した若き日、喜屋武長徳(きゃん・ちょうとく 1870-1945)に師事した背景から嘉手納にいた若き日の新城を懐かしい気持ちでそう呼んだと思われる。現在、その県空連で新城は副会長として後進の育成に当たる。(文中敬称略)

この日稽古に集った皆さん
※沖縄現地の空手道場を、武術的要素を加味して随時紹介していきます。
シリーズ【沖縄伝統空手のいま 道場拝見】:
①沖縄空手の名門道場 究道館(小林流)〈上〉 〈下〉
②戦い続ける実践者 沖拳会(沖縄拳法)〈上〉 〈中〉 〈下〉
③沖縄空手の名門道場 明武舘(剛柔流)〈上〉 〈下〉
④上地流宗家道場 普天間修武館(上地流)
⑤喜舎場塾田島道場(松林流)〈上〉 〈中〉 〈下〉
⑥上地流空手道拳優会本部(上地流)〈上〉 〈下〉
【WEB連載終了】沖縄伝統空手のいま~世界に飛翔したカラテの源流:
[シリーズ一覧]を表示する
WEB第三文明で連載された「沖縄伝統空手のいま~世界に飛翔したカラテの源流」が書籍化!
『沖縄空手への旅──琉球発祥の伝統武術』
柳原滋雄 著定価:1,760円(税込)
2020年9月14日発売
第三文明社
【WEB連載終了】長嶺将真物語~沖縄空手の興亡~
[シリーズ一覧]を表示する
WEB第三文明で連載された「長嶺将真物語~沖縄空手の興亡」が書籍化!
『空手は沖縄の魂なり――長嶺将真伝』
柳原滋雄 著定価:1,980円(税込)
2021年10月28日発売
論創社(論創ノンフィクション 015)