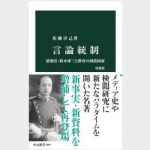鈴木庫三とはいかなる人物か
第2次世界大戦下の日本で、言論統制を行った悪名高い情報将校・鈴木庫三(くらぞう)。本書は厖大な資料を渉猟し彼の実像に迫ることによって、当時の言論界の内実を明らかにするものである。初版は2004年に発行された。それから20年が経過し、デジタルアーカイブの発達などもあり、多くの未発見資料が発見された。そうした成果を盛り込み増補・加筆されたものが『情報統制 増補版』である。
日記からも猛烈な勉強の様子がうかがわれるが、読書時間の多くが演習や講義で利用された洋書テキストに費やされている。(中略)目的に対する精力の集中投入という軍事的思考なのであろうが、そこに「知識人」鈴木庫三の限界を指摘することはできる。(本書184ページ)
鈴木庫三は1894年、茨城県の小作農の子供として生まれた。家は貧しく、幼い頃から両親の農業を手伝いながら学ぶことを余儀なくされる。軍人になってからも努力を重ね、日本大学の文学部を首席で卒業し、同大学院へと進学する。刻苦勉励(こっくべんれい)がやがて実を結び、東京帝国大学(現在の東京大学)文学部に陸軍派遣学生として送り込まれることとなった。やがて教育将校として頭角を現し、1938年から1942年まで情報将校として辣腕を振るった。「国防国家」という言葉が一般的に定着したのは彼の功績ともいわれる。戦後は熊本に隠棲し農業に従事し、1964年に死去している。
その性格は至って真面目で都会の奢侈な生活を嫌い、社会主義には生涯、共感を抱いていた。当時、日本で横行していた中国や韓半島の人々に対する差別に対して批判的であったという。仕事終わりに飲みに行く同僚や高等遊民を気取る学生には目もくれず、時間があれば自宅で机に向かった。情報官時代には週に1本という驚異的なペースで論文を執筆し、他にも多数の講演を行っていたという。だが、そうした性格が返って災いし、国防国家の建設とそのための思想戦へと彼を向かわせることになる。
出版社との協力体制
つまり、「鈴木時代」は「出版バブル時代」とぴったりと重なるわけであり、鈴木情報官の指導下で雑誌出版社はいずれも我が世の春を謳歌していた。(中略)雑誌ジャーナリズムは、国策に上手く棹(さお)さしていたわけで、そうした状況へのやましさから戦後になって自ら被害者を名乗るために「独裁者」を必要とした、とも考えられる。(本書48~49ページ)
力によって言論界を屈服させファシズムへと導いた軍人。戦後、鈴木はこうした悪評を一身に浴びた。だが戦時中の資料を検証すると実態は大きく異なる。1940年頃の日本の出版業界は「バブル」と形容できるほどの好況を呈していた。後に戦争責任を追及された講談社だけでなく、リベラル派と評される岩波書店や朝日新聞までもがこの「鈴木時代」には大きな利益を上げていた。
戦時下の統制経済では、新聞雑誌用紙の割り当ては、情報部が握っていた。出版社は少しでも多くの用紙がほしいので、自ら進んで鈴木に対し協力する姿勢を示した。
また当時は軍部への投書が盛んに行われる密告社会であった。有名な作家や企業へ嫉妬する同業者は多い。そうした人々からの取り締まりを求める告発は軍部に殺到した。こうした告発者たちと出版社とを媒介する役割を鈴木は担っていた。出版社だけでなく多くの作家たちもまた「鈴木詣で」といわれるほど、こぞって彼のもとを訪れていた。協力した人物には菊池寛や吉川英治などがおり、壷井栄や宮本百合子も彼と雑誌で対談している。
記憶を偽造し、闇に葬る
石川の記憶の中で「鈴木少佐」は、もう一人の自分なのである。とすれば、わざわざ「陸軍報道部(?)に鈴木某という少佐(?)」という持って回った曖昧な表記を用いた深層心理も理解しやすい。それは自らの過去を忘却したいという願望である。(本書56ページ)
鈴木庫三の悪評を決定的なものとしたのは、戦後になって石川達三が発表した小説『風のなかの葦』である。しかし彼もまた戦時中には鈴木に進んで協力した過去を持っていた。
石川は「反戦作家」と評されることが多い。その理由として、『生きてゐる兵隊』で凄惨な戦場の実態を描き、発禁処分にされたことが挙げられる。しかし彼は反戦を意図してこの作品を書いたのではない。このことは戦後に復刊された序文で本人が認めている。さらに彼は名誉挽回を期して武漢攻略戦に従軍文士として参加し、その体験をもとに『武漢作戦』という作品を書き、その後は文壇の要職を歴任している。
その石川が戦後に発表した作品で鈴木を佐々木という名前で登場させ、判で押したような、知性のない乱暴な軍人として描いた。なぜ石川はこのような作品を描いたのであろうか。
著者はそこに社会の風向きを読むのに長けた石川の狡猾さを見るとともに、過去に戦争協力者であったという事実を忘却したいという強い願望と自己弁明を読み取る。
しかし、こうした願望を持ったのは石川だけではない。鈴木詣でを繰り返した他の多くの編集者や作家も鈴木を酷評した。鈴木にのみ責任を負わせ、自らは言論弾圧の被害者と位置付けることによって、戦後社会での生き延びを図ったのだ。まさに自己保身のための記憶の改竄であり。歴史を闇に葬り去る行為である。
こうしたなかで学術的な観点から鈴木庫三について僅かではあるが論じた1人の研究者がいた。それは「国家悪」の著者として知られる大熊信行である。
本書を一読して理解できるのは、戦前、戦中の軍国主義体制は国民の共犯関係があって、はじめて成立したということだ。本書の表題が、権力者が上から一方的に押し付ける「言論弾圧」ではなく、権力者と国民の共犯によってなされる「言論統制」とした点に、著者の歴史観が端的にあらわれているといえよう。
戦後80年を迎えた今日、日本ではかつてない歴史健忘症が広がっている。アジア諸国への侵略行為を否定し、軍国主義を美化するような言説がネットには溢れている。さらに先の参院選では、国家神道の復活や国民主権を否定する政党が大きく勢力を拡大した。これでは亡国の歴史を再び辿る危険性すらある。私たちは同じ過ちを繰り返してはならない。
本書は、鈴木庫三という情報将校の姿を通して、国民を加害者へと変えてしまう戦争の恐ろしさ、歴史に向き合うことの重要性と過去を克服することの難しさを鋭く問いかけている。
『言論統制 増補版――情報官・鈴木庫三と教育の国防国家』
(佐藤卓巳著/中公新書/2024年5月22日刊)
関連記事:
「小林芳雄」記事一覧