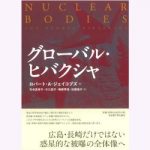惑星的な視座からヒバクシャを可視化
本書「グローバル・ヒバクシャ」では、これまでほとんど顧みられることのなかった、世界各地に存在する被曝者の歴史と実態を追求し、核抑止力の前提を鋭く問い直すことを試みている。著者はアメリカ史、科学史、核の文化史を専門とする歴史学者であり、2005年から2025年まで、19年にわたって広島の地で教育・研究に従事してきた。本書はその活動から生まれたものである。
人間の身体は人類という単一の種に属するものであり、その歴史は、地球を政治の舞台とする、種としての歴史である。グローバルな歴史として捉えたとき、放射線の影響の全貌が明らかになる――放射線の害はもはや一過性のものではなく、体系的なものとなる。我々は各国の責任を問い続け、その行動を詳細に把握しなければならない。放射性降下物の粒子が世界中に行き渡ったのと同様に、私たちも視線を世界中に行き渡らせる必要がある。(本書32ページ)
1945年、第二次世界大戦末期、広島、次いで長崎で、人類史最初の核兵器が使用された。多くの犠牲者を出した。しかし、世界の核保有国はそれ以降も核の開発を続け、冷戦終結までに2000発の核兵器を爆発させた。こうした核実験だけでなく、原料となるウラニウムの採掘や原発事故を含めると、放射能による被害を受けた人の数は世界各地で数100万人にのぼるという。
これほどの被害者がいたにも関わらず、歴史学ではこうした事実について全くふれないか、各国の歴史のなかで僅かに記述される程度だった。著者は国家を超えた惑星的な観点から、世界各地の被曝者である「グローバル・ヒバクシャ」の歴史を究明していく。疫学的な観点だけでなく、当事者の歴史的証言にも重きを置くことによって、数字に還元することができない被曝者たちの苦しみにも光を当てている。
限定戦争としての冷戦
冷戦史において、核実験に言及されることはほとんどない。だが、冷戦期に核戦争が起きなかったと言う場合、実際にはそれは、自分の身には起きなかったと言っているのであり、特権的な見方である。大気圏内核実験の実験場の近くに住む人々にとっては、実際に起こったことなのだ。(中略)限定核戦争だったのである。(本書27ページ)
グローバル・ヒバクシャがこれまで可視化されなかった原因を著者は2点指摘している。
1点目は、政治的隠蔽である。核施設や実験場が置かれた場所に注目すると、核保有国の首都から離れた地域が選ばれている。植民地や自治領が圧倒的に多く、そこには伝統的な生活を守る少数民族が暮らしていた。こうした人々はもともと政治的発言権が弱く、もしくは無きに等しい立場に置かれてきた。核実験が行われた後は故郷を失い、そして共同体は崩壊する。移住後は低賃金労働に就かざるを得ない人が多く、自然に依存していた食文化も崩れ、糖尿病などの生活習慣病に罹患する率も跳ね上がるという。
政治エリートたちは、被害を受けた人たちを〝文明から遅れた人〟〝政治的に取るに足らない人〟と判断し、その人々が住む地域で実験を行ってきたのだ。
2点目は、科学的隠蔽である。被曝の人体への影響を判断する際、通常、引き合いに出されるのは「寿命調査」である。この調査は日本に2発の原爆が落とされた直後から広島と長崎の被曝者を対象として行われた。被験者の人数の多さも他に類を見ないものだ。
しかし、この調査は原爆から発せられた放射線による外部被曝に関しては参考になるが、長い年月をかけて放射性物質を体内に取り込み起こる内部被曝に関しては参考にならない。実施当時、放射性物質を計測できる技術が発達していなかったからだ。
核爆発によって大気圏内に打ち上げられた核物質は、長い年月をかけて降下し生態系のなかに取り込まれていく。その過程も極めて複雑だ。
さらには目にも見えず、意識もできないため、被曝地域の人々は当然、不安を覚える。しかし「寿命調査」のデータを持ち出すことによって、その不安を封じ込めることができる。それでも健康不安を訴える人がいれば、「クレーマー」として扱うことができるのだ。
こうした隠蔽を取り去ったとき、東西冷戦下で第三次世界大戦が起こらなかったのは、核抑止によるとの神話は崩れ去ると著者は主張する。つまり、核保有国は自国の国民に対して、限定的な核戦争を行っていた――これが冷戦時代の平和の実態であると指摘している。
問われる道義的責任
冷戦期の核兵器が今なお人類の文明を脅かしているのと同様に、人類への放射線の影響も、二〇世紀が幕を閉じた今も存在し続けている。核兵器と原発により放出される放射性核種の多くは、世界中のあらゆるところに堆積し、我々の寿命をはるかに超えて、生態系の中を移動し続けている。今後、幾世代にもわたって、こうした粒子や何百万トンもの放射性廃棄物を地球環境から取り除くことはできない。我々はその時間軸の最前線にいるのだ。(本書10ページ)
核の問題を論じる際に避けて通ることのできないのが核廃棄物の問題である。人類が核兵器と原発を利用し始めてから80年の年月が過ぎたが、その間に排出された核廃棄物が無害化するのには10万年という長い期間が必要とされる。
こうした核廃棄物は自国の地下に保存されるという決まりになっているが、日本のような火山大国の場合、それは常に危険と隣合わせの状況を生む。
また度重なる核実験によって大気中にまき散らされた放射性物質の影響も看過できない。1945年以降、大気中に含まれる放射性物質の数は、ビンテージ・ワインや絵画の真偽判別に利用されるほど増大した。その影響は海洋生物などにはすでに表れている。
科学は万能ではないし、人間の知性にも限りがある。予想を上回る気候変動や自然災害、不慮の事故などが起これば、大惨事を招く可能性すらある。そもそも、一度でも核兵器が発射されれば、人類の生存自体が危うくなる。
本書を通して痛感することは、過去の核による犠牲者以外にも、私たちの目に不可視化され苦しみ続けているヒバクシャと、核兵器および核廃棄物という巨大な負の遺産を背負った未来の人々の存在に対する、私たちの責任の重さである。
核兵器を実戦使用された唯一の国である日本に住む私たちは、核廃絶に積極的に取り組むべきであろう。しかし、日本はいまだ核禁止条約を批准しておらず、オブザーバー参加すら実現できていない状況である。
核廃絶問題の道義的責任について、日本人として改めて深く考えさせられる一書である。
『グローバル・ヒバクシャ』
(ロバート・A・ジェイコブス著、竹本真希子・川口悠子・梅原李哉・佐藤温子訳/名古屋大学出版会/2025年3月28日刊)
関連記事:
「小林芳雄」記事一覧