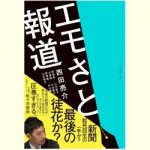「エモい記事」は必要なのか
若者言葉である「エモい」は『広辞苑』にはまだ載っていないものの、2021年12月に改訂された『三省堂国語辞典』(第8版)には収録された。
【エモい】 (形)〔俗〕心がゆさぶられる感じだ。(略)〔由来〕ロックの一種エモ〔←エモーショナル ハードコア〕の曲調から、二〇一〇年代後半に一般に広まった。古語の「あはれなり」の意味に似ている。(『三省堂国語辞典』)
さて、事の発端は2024年3月29日にさかのぼる。
朝日新聞が運営するウェブサイト「Re:Ron」に、著者である西田亮介氏(社会学者/日本大学危機管理学部教授)の記事が掲載された。
タイトルは〈その「エモい記事」いりますか――苦悩する新聞への苦言と変化への提言〉。これは、そのまま本書『エモさと報道』の第1章に収録されていて、ちなみに次のような書き出しで始まる。
昨今、「ナラティブで、エモい記事」を新聞紙面でしばしば見かける。朝日新聞だけではない。他の全国紙も同様だ。具体的には、データや根拠を前面に出すことなく、なにかを明瞭に批判するでも、賛同するわけでもない。一意にかつ直ちに「読む意味」がはっきりしない。記者目線のエピソード重視、ナラティブ(物語)重視の記事のことである。夕刊や日曜版においては、一面などに掲載されることもある。(本書)
西田氏が言わんとしたのは、そうした「エモい記事」がけしからんという話ではない。ただ、ネットと違って紙の新聞は掲載できる記事の総量が決まっている。ある記事がスペースを占有することは、その分量だけ別の記事(になり得たもの)が掲載されないことを意味する。しかも、読者は毎月4000円から5000円の購読料を支払っている。
さらに言えば、新聞は「報道事業者」として、軽減税率の適用、記者クラブへの所属、公益通報者保護法における「内部告発」の外部通報先としての「報道機関」に指定されるなど、さまざまな特権を享受している。
それは私企業ではあっても、ある種の「公益性」「公共性」を有する事業と見なされているからである。その特権は、日本国憲法21条に照らしても十分に尊重されるべきものだと司法の判断も出されている。
民主主義の基盤としての新聞の重要性
そのような社会的役割を与えられた新聞にあって、エビデンスを欠いたエピソード重視の「エモい記事」を1面にもってくることの意味を、西田氏は率直に問うたわけである。あくまで「エモい記事」を扱うバランスについて問題提起したのだ。
ところが、この寄稿が予想外の論争を巻き起こしていった。賛同の声がある一方で、「エモい記事の何が悪いのか」というような擁護論も出た。
なにより当の朝日新聞の記者や編集委員からは、やはり〝エモい記事〟の必要性を論じる声が多く出た。
その後、議論が白熱していくと、同紙の役職者からは「あなたの発言はポリシーに違反しているから気をつけろ」という趣旨のメールまで来たという。しかし、具体的にどこが違反しているのか問うても返答はない。公開の場で議論することはせず、見ず知らずの相手が「会ってお話がしたい」と言うので、西田氏は応じなかったという。
本書は、東浩紀・大澤聡・武田徹・山本章子・江川紹子・大治朋子・外山薫といった面々との鼎談形式で構成されている。
ただし本書は、この「エモい記事」論争をめぐって、単に朝日新聞社に意趣返しをしたいというような本ではまったくない。
むしろ「エモい記事」をひとつの糸口にして、今や絶滅の危機にある新聞というメディアの重要性――とりわけ民主主義の基盤としての重要性――を人々に強く喚起し、現実問題として新聞というメディアが経営的に、また機能として生き残るためには、何が必要かということを真剣に議論した一書だと言える。
共感はできても議論ができない
たとえば大澤聡氏は、昨今は文学が政治家・社会化しているとし、逆に新聞の現状を「報道の文学化」だと評したうえで、次のように語っている。
このままでは、報道の言語も文学の言語もともに弱ってしまうのではないかと危惧します。今回の論争でわたしがもっとも主張したいのはここです。
理論やオピニオンに対しては、賛成なり反対なりの議論が可能です。その議論のただなかから公共性が立ち上がります。しかしエモい記事のような感情やエピソードへは共感できるか共感できないかしかない。議論しようがありません。議論がないから炎上も少ないし、私と私との間の「絆」も生まれる。しかし絆と公共性は似て非なるものでしょう。新聞が担うべきは公共性のほうであるのは自明です。(同)
では、その「公共性」はどのようにすれば回復するのか。大澤氏は、いつでも離脱や修正が可能なブログやSNSから立ち上がる空間には公共圏は生まれず、やはりそこに新聞の役割があると語る。
それを受けて東浩紀氏は、
これは言い換えると、「中道」とはなにかという問題でもあります。(中略)
中道とは、右と左のバランスではなく多様性ということであり、その現実の確保が公共性の前提です。報道やジャーナリズムは、多様な立場や階層にはたらきかけることで、はじめて公共に開かれるのだと思います。(同)
と述べている。
この「多様な立場や階層にはたらきかける」というのは、迂闊に読み飛ばしてはならない言葉であろう。やっているつもりで、真にそれができていないから、新聞は公共に開かれることなく衰退しているのではないのか。
新聞が本来の機能と使命を回復していくカギは、そこにあるように感じた。
「新聞」を絶滅させないためには
鼎談では西田氏が具体的な部数や支局数の数字を挙げて、2010年代以降の全国紙の急速な衰退の現状を指摘している。そして、とりわけ大規模な災害時に果たす新聞の重要性に触れ、どうすれば全国津々浦々に報道の基盤を確保できるかと問題提起している。
2011年の東日本大震災に比べて、2024年の能登地震の報道量が少なかったのは、なによりも被災地の新聞各社の基盤が既に脆弱だったからなのである。
ある種の補助金を入れてでも支局網を再構築すべきではないかという案や、国が拠点だけ用意して各社が持ち回りで維持する案など、興味深い議論が交わされている。
もちろん本書が議論の前提にしているのは、公共性を持った全国紙を主としたものではあるが、〝紙の新聞〟が絶滅寸前にあることは、地方紙や業界紙、はたまた諸団体の機関紙や政党の機関紙にとっても他人事ではない。
折しもSNSなどネット上の情報を主戦場とした国際的な「認知戦」が、いよいよ日本語圏である日本国にも攻め寄せてきたことが相次いで報じられている。
たしかに「エモい記事」は一定の〝共感〟を呼ぶ。編集部にそうした〝共感〟の声も届く。電子版ではPVも稼ぐだろう。しかし、新聞の役割はそれだけでいいのか。それで読者が回復し経営基盤が上向いていくのか。
新聞は(雑誌も含まれるだろう)、もう絶滅してよいメディアなのか。もし、そうでないとするなら、新聞のとるべき道は何なのか。メディアにかかわる人々、なかんずく新聞の仕事に携わる人にとって必読の一冊だと思う。
「本房 歩」関連記事①:
書評『人はなぜ争うのか』――戦争の原因と平和への展望
書評『見えない日常』――写真家が遭遇した〝逮捕〟と蘇生の物語
書評『歌集 ゆふすげ』――美智子さま未発表の466首
書評『法華経の風景』――未来へ向けて法華経が持つ可能性
書評『傅益瑶作品集 一茶と芭蕉』――水墨画で描く一茶と芭蕉の世界
書評『もし君が君を信じられなくなっても』――不登校生徒が集まる音楽学校
書評『LGBTのコモン・センス』――私たちの性に関する常識を編み直す
書評『現代台湾クロニクル2014-2023』――台湾の現在地を知れる一書
書評『SDGsな仕事』――「THE INOUE BROTHERS…の軌跡」
「本房 歩」関連記事②:
書評『歴史と人物を語る(下)』――生命を千倍生きゆけ!
書評『ヒロシマへの旅』――核兵器と中学生の命をめぐる物語
書評『アレクサンドロスの決断』、『革命の若き空』(同時収録)
書評『新装改訂版 随筆 正義の道』――池田門下の〝本当の出発〟のとき
書評『希望の源泉 池田思想⑦』――「政教分離」への誤解を正す好著
書評『ブラボーわが人生4』――心のなかに師匠を抱いて
「池田大作」を知るための書籍・20タイトル(上) まずは会長自身の著作から
「池田大作」を知るための書籍・20タイトル(下) 対談集・評伝・そのほか
書評『創学研究Ⅱ――日蓮大聖人論』――創価学会の日蓮本仏論を考える
書評『公明党はおもしろい』――水谷修が公明党を応援する理由
書評『なぎさだより』――アタシは「負けじ組」の組員だよ
書評『完本 若き日の読書』――書を読め、書に読まれるな!
書評『新版 宗教はだれのものか』――「人間のための宗教」の百年史