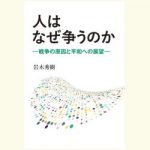戦争は人類の宿命ではない
2022年2月から始まった、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻。2023年10月のハマスによるイスラエル奇襲攻撃に端を発した、イスラエル・パレスチナ紛争。
それらの戦火が続くなかで、本書『人はなぜ争うのか』は上梓された。
著者は、平和学・中東イスラーム学・国際関係学の専門家であり、公益財団法人・東洋哲学研究所研究員の肩書も持つ。
これまで『中東イスラームの歴史と現在―平和と共存をめざして―』(第三文明社/2018)、『共存と福祉の平和学――戦争原因と貧困・格差』(第三文明社/2020)、『きちんと知ろうイスラーム』(鳳書院/2022)、『幸福平和学 暴力と不幸の超克』(第三文明社/2024)などを上梓している。
これらは本書の参考文献として関心のある人には一読を勧めたい。
本書の執筆に至った思いを、著者は「はじめに」でこう綴っている。
戦争は人類の宿命ではない。歴史的にも戦争をしない時代はあったし、地域的にも平和な地域は存在する。戦争が宿命であれば、この本の存在意義はない。戦争を低減化できるからこそ、上梓を決意した。
本書の第一部で、戦争の原因を歴史的に考察する。第二部では、最近の戦争と平和への展望として、「イスラエル・パレスチナ紛争」「ウクライナ戦争」の背景に言及したうえで、イスラームと仏教の持つ平和共存の哲学、非暴力への展望などを考察する。
なお、本書は全体として、「博(ひろし)」「泉(いずみ)」「勝(まさる)」の3人の対話編という形式で記述されている。このうち「博」は平和学やイスラームに関する研究者(主に著者の立場に近い)。「泉」と「勝」は同じ企業の同僚という設定であり、今後推進する業務のうえからも国際情勢や戦争と平和の問題について知っておく必要があった。
この設定は、平易な話し言葉でより幅広い読者に訴求するだけでなく、遠い地域で起こっていると思われがちな国際紛争が日本にとって他人事でないことを、読者に実感させてくれる。
平和は特別な専門家だけが論じればいいものではなく、まさに私たちの日常と地続きの重要な課題としてあるのだ。
宇宙的な時間軸の有効性
第一部の冒頭では「戦争の定義」について語られる。
ユニークなのは、あえて「ビッグヒストリー」という視点を入れて、「138億年前のビッグバンから40億年前の地球誕生まで」「生命の誕生から20万年前のホモサピエンスの誕生まで」「ホモサピエンスの誕生から1万年前の農耕の開始まで」「農耕の開始から200年前の近代世界の成立まで」「近代世界の成立から現代まで」という時間軸で、これらを戦争の定義を最大化した「暴力的接触」として見ていることである。
こうした宇宙的な時間軸をあえて取り込むことは、地球という星のうえで国家と国家、民族と民族が殺戮の応酬をする「戦争」というものの実像を相対化してくれる。
宇宙的なスケールでの「生命」の営みという視点から戦争を見つめることで、戦争という行為を正当化する国家間や民族間のロジックの権威性が解体され、平和への展望に積極的な意味を付与していくように思われる。
戦争がなぜ起きるのかという要因と背景について、本書では「類人猿と人間の違い」「狩猟採取から農耕牧畜へ」という人類史の流れを示し、「国民国家の成立」「経済的要請」といった近代の戦争の構造を平易に示す。
ここでのポイントは、近代において誕生した「国民国家」という概念が、ひとつにはあくまで〝フィクション〟であること。もうひとつは、所与のものとイメージされがちな「国家」という概念が、歴史的にはそれほど古いものではないことだ。
このことは、「国家」が今後も永遠に存続するとは限らないということを意味している。トランプ大統領の「自国第一主義」のような内向きのナショナリズムが席巻している一方で、感染症のパンデミックや気候変動問題など、地球全体の視点に立って対処しなければならない課題が、すでに私たちの目の前に突きつけられている。
著者は、「領土」(territory)の語源が、ラテン語の土地や大地を意味するterraであることを示し、これは「怖がらせる/脅えさせる」というterrereと密接な関係があり、現在の「テロ」(terror)の語源でもあることを紹介している。
すなわち、国民国家の基盤をなす領土という語には、暴力の行使を通して占領した土地であることが含意されているというのである。
著者が言うように、今日の紛争の大多数が相変わらず「領土」をめぐる問題に端を発していることには異論がない。その意味では「領土」は人々を「友」と「敵」に分けるものでもあるが、依然として自国民の生命と安全を守る機能を有していることも疑いようがない。
領土を基盤とする国民国家が、たとえある種のフィクションであるとしても実効的に機能している今日にあって、どのような視点と方策によって、「領土」を戦争の要因から脱却し得るのか。具体的な議論はここでは示されなかったが、今後の課題ということだろうか。
イスラームと仏教の可能性
第二部では、現在進行形の戦争である「イスラエル・パレスチナ戦争」と「ウクライナ戦争」を俎上に載せて、これらの戦争の背景を多面的な視点から捉えようとしている。
例えば、アメリカのキリスト教福音派(キリスト教シオニスト)の人びとがイスラエルを支持する構図に言及されており、またユダヤ思想を専門とするイェシャヤフ・レイボヴィツが、ユダヤ教をナショナリズムの目的に合わせて道具化することに反対している事実を紹介している点は興味深い。
もっとも戒律を厳格に守る超正統派の人々のなかにも、イスラエル建国そのものが聖書の「汝、殺すなかれ、盗むなかれ」に反していると考え、イスラエルの土地をパレスチナに返還すべきだと主張する者がいるという。
ネタニヤフ政権は「史上最右翼政権」であるわけだが、イスラエルの内部には多様な意見が存在しているというのである。
「ウクライナ戦争」に関して、著者が手厳しく批判するのは、欧米が見せる「ダブルスタンダード」である。
すなわち、「武力による現状変更は認められない」としながら、過去において米英はイラク戦争やアフガニスタン空爆を実施してきた。
また、同時並行で起きたイスラエルの国際法無視や不法占領には、欧米は目をつぶったままである。
日本の報道がともすれば欧米寄り、G7側の視点中心になりがちなのに対し、実際にはロシアを非難する西側諸国と、インドやブラジルなど中立の国と、中国やイランなどロシアに理解を示す国は、比率にして3分の1ずつだと指摘する。
トルコはNATO加盟国であるが、侵攻直後の2022年3月にトルコで実施された世論調査では、ウクライナ危機の責任の所在として最多の48.3%とされたのは「米国・NATO」であった。
こうした暴力に抵抗していく方途として、本書が最後に言及するのはイスラームの新しい潮流として萌芽がみられる宗教共存への柔軟な思考と、平和学者グレン・ペイジが言及した仏教の非殺生の視点である。
本書は、イスラームと仏教の〝類似点〟を挙げる。とりわけ日蓮仏法がイスラームと類似性を持っていることに言及している点は、読者にとっても新鮮かもしれない。
具体的には、①偶像崇拝をしていない点、②宗教と生活・政治・経済を分断しない「信心即生活」の思想、③死後の世界よりも現実のこの世界を重視する点、である。
今後の世界において、イスラームと仏教が協力することで、一神教世界と東洋思想の橋渡しができるのではないかと著者はいう。
ともかく全体として平易な会話調で構成されているので、1時間もあれば読めてしまう。
新しく大学生になった人たちに向けて、入門書としてオリエンテーション的に視点を提示することを目的にしているためか、個別の事象の詳細についての説明は最小限にとどまっている。本書で興味をもった人は、さらに学びを深めてほしい。
戦争を抑止し平和を構築していくというと、特別な分野の人々だけの仕事と思われがちだが、何よりも大事なことは、市井の一人ひとりが当事者としての意識に立つことであろう。その糸口となる一冊である。
『人はなぜ争うのか 戦争の原因と平和への展望』(岩木秀樹著/鳳書院/2025年3月27日刊)
※電子版書籍は第三文明社から発売
「本房 歩」関連記事①:
書評『見えない日常』――写真家が遭遇した〝逮捕〟と蘇生の物語
書評『歌集 ゆふすげ』――美智子さま未発表の466首
書評『法華経の風景』――未来へ向けて法華経が持つ可能性
書評『傅益瑶作品集 一茶と芭蕉』――水墨画で描く一茶と芭蕉の世界
書評『もし君が君を信じられなくなっても』――不登校生徒が集まる音楽学校
書評『LGBTのコモン・センス』――私たちの性に関する常識を編み直す
書評『現代台湾クロニクル2014-2023』――台湾の現在地を知れる一書
書評『SDGsな仕事』――「THE INOUE BROTHERS…の軌跡」
書評『盧溝橋事件から日中戦争へ』――日中全面戦争までの歩み
書評『シュリーマンと八王子』――トロイア遺跡発見者が世界に伝えた八王子
書評『科学と宗教の未来』――科学と宗教は「平和と幸福」にどう寄与し得るか
書評『日本共産党の100年』――「なにより、いのち。」の裏側
書評『差別は思いやりでは解決しない』――ジェンダーやLGBTQから考える
「本房 歩」関連記事②:
書評『ヒロシマへの旅』――核兵器と中学生の命をめぐる物語
書評『アレクサンドロスの決断』、『革命の若き空』(同時収録)
書評『新装改訂版 随筆 正義の道』――池田門下の〝本当の出発〟のとき
書評『希望の源泉 池田思想⑦』――「政教分離」への誤解を正す好著
書評『ブラボーわが人生4』――心のなかに師匠を抱いて
「池田大作」を知るための書籍・20タイトル(上) まずは会長自身の著作から
「池田大作」を知るための書籍・20タイトル(下) 対談集・評伝・そのほか
書評『創学研究Ⅱ――日蓮大聖人論』――創価学会の日蓮本仏論を考える
書評『公明党はおもしろい』――水谷修が公明党を応援する理由
書評『ハピネス 幸せこそ、あなたらしい』――ティナ・ターナー最後の著作
書評『なぎさだより』――アタシは「負けじ組」の組員だよ
書評『完本 若き日の読書』――書を読め、書に読まれるな!
書評『日蓮の心』――その人間的魅力に迫る
書評『新版 宗教はだれのものか』――「人間のための宗教」の百年史
書評『「価値創造」の道』――中国に広がる「池田思想」研究
書評『創学研究Ⅰ』――師の実践を継承しようとする挑戦
書評『法華衆の芸術』――新しい視点で読み解く日本美術
書評『池田大作研究』――世界宗教への道を追う