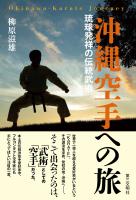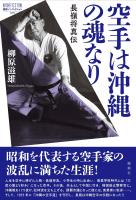100%護身目的の稽古体系
米軍倉庫跡を改築したという道場は自宅3階部分のプレハブ建て。拳武館(沖縄市)道場の入口には「沖縄剛柔流拳法」の大きな文字。マットを敷きつめた内部はかなり広く感じる。
道場主の久場良男館長(くば・よしお 1946-)は60年を超す武歴(空手歴)をもつ。中学3年のとき剛柔流の渡口政吉(とぐち・せいきち 1917-1998)道場に通ったのが最初で、高校時代はもっぱら剣道に打ち込んだ。大学時代は名古屋で和道流空手に親しみ、卒業後帰沖して再び渡口に本格師事することになる。
基本に、ものすごくうるさい先生でした。
空手の師である渡口について開口一番そう語った。剛柔流は東恩納寛量(ひがおんな・かんりょう 1853-1915)と、その直弟子であった宮城長順(みやぎ・ちょうじゅん 1888-1953)、比嘉世幸(ひが・せこう 1898-1966)の流れがメインとして残る。現在、沖縄にあるのは比嘉世幸系、宮城長順の弟子である八木明徳(やぎ・めいとく 1912-2003)系、同じく宮里栄一(みやざと・えいいち 1922-1999)系の主に3系統だ。

拳武館の道場入り口
その中でも渡口は、比嘉世幸に師事しながら戦後の一時期、宮城長順にも習った経歴があったため、純粋な比嘉系統とは異なる面があるという。
渡口の本土道場は多くが全日本空手道連盟(全空連)に所属したため、久場道場でも普通に組手稽古を行った時期がある。
若いときの競技は否定しません。
久場館長はきっぱりそう語る。現在の道場が建ったのは1989年(平成元年)。以前は、陣頭指揮で組手指導を行っていたというが、40代のとき頸椎ヘルニアで左手が動かなくなり、一時は道場を閉めようと考えたこともあったという。道場生たちの「閉鎖しないでほしい」との声に押され、動かないままで指導をつづけていたが、3年ほどして動くようになったと振り返る。以来、熱心に通ってくる少数の弟子たちを相手に79歳になる今も指導をつづける。
大人の稽古は月・水・金の午後7時から1時間半。月曜は足技中心の稽古、水曜は手技中心、金曜はそれらのコンビネーション稽古と、曜日によってメニューが分けられている。8月の水曜日、手技中心の稽古を初めて取材した。
怪我させず相手を制圧する
午後7時。夏の夕暮れ時、辺りがオレンジ色に包まれるころ、久場館長が階下の自宅スペースから上がってきた。
剛柔流の稽古はサンチン(三戦)立ちを基本に行われる。まずは正拳突きを上段、中段などで行い、さらに各種受け(上段・中段・下段)を行う。前蹴り、ミドルの回し蹴り、足刀横蹴りを軽く流したあと、各種受け+突きの動作を繰り返した。例えば、「腕受け(極真の内受け)」プラス「突き」といった動作だ。

稽古の最後に行ったサンチンは剛柔流における基本的な鍛錬型だ
その後、人差し指一本拳で上・中・下の高さで突く動作を繰り返した。さらに手刀横打ち、水平打ち、足刀での関節蹴り、かかとを落とす技など。加えて、孤拳での上段受け、掛け手刀での受けなど、さまざまなパーツごとの技を繰り返す。
これらの稽古のベースは渡口政吉の空手にほかならないが、久場自身が徹底的にアレンジして完成された実戦向きのオリジナル稽古だ。そのため他の剛柔流流派で行っている稽古とは異なる稽古体系ともいえる。
つづけてステップを入れたワンツー突きの稽古を汗だくになりながら行った。開始から1時間近くたったころ、「対人稽古」に移る。一対一になって、相手の右中段回し蹴りを逆の手(右手)で「押し受け」した後のワンツー、同じく右手で受け流してワンツー、両手で蹴り足を挟み込んで掴む稽古などを行った。回し蹴りに対する実戦的な受け方だった。

対人稽古では相手に怪我をさせずに制圧する逆技を重視
さらに対人で、「逆技」(裏技)を使い相手を制圧する稽古をつづける。約1時間。やっと休憩となる。1時間ぶっつづけで汗を流すのはいつもながらのことと道場生が説明した。
久場道場で「逆技」を重視するのは、実戦に直面した場合、空手の打撃である突き・蹴りを使ってしまうと相手に怪我をさせる可能性が高く、こちらが犯罪者になってしまいかねないからだ。そうした事態を避けるため、怪我させないで、殴ったり蹴ったりすることなく、制圧する技を身につけることに重点が置かれている。
実戦は打撃だけとは限りません。
多くがシソーチンなど剛柔流の型の動きから取り出したものという。
5分間の休憩の後、「鶴破」(カクハ)という渡口政吉が創作したオリジナル型を2回行った。上地流を思わせる開手(かいしゅ)の動きから始まり、途中、下段への関節蹴りや掌底(しょうてい)による下段受けが特徴的な型に思えた。渡口系では茶帯になって稽古する型という。

開手で行う渡口系統のオリジナル型「鶴破」。上地流の動作を想起させる
「鶴破」のあとは対人になって、全体を通した分解を行った。一人が型の動作を行い、もう片方が攻撃を受ける相手側の動きを想定し、型動作を2人で確認する稽古だ。
つづけてサイファ(最破)を2回行い、最後にサンチンを1回行ってこの日の稽古を終了した。
渡口系のサンチンは、東恩納寛量の影響が強く残る戦前のサンチンに近いという。参加者が黒帯だけの場合は、最後に「転掌」(テンショウ)を行うこともある。(文中敬称略)

「鶴破」(カクハ)の特徴的な場面の一つ。掌底を使った下段受け
※沖縄現地の空手道場を、武術的要素を加味して随時紹介していきます。
シリーズ【沖縄伝統空手のいま 道場拝見】:
①沖縄空手の名門道場 究道館(小林流)〈上〉 〈下〉
②戦い続ける実践者 沖拳会(沖縄拳法)〈上〉 〈中〉 〈下〉
③沖縄空手の名門道場 明武舘(剛柔流)〈上〉 〈下〉
④上地流宗家道場 普天間修武館(上地流)
⑤喜舎場塾田島道場(松林流)〈上〉 〈中〉 〈下〉
⑥上地流空手道拳優会本部(上地流)〈上〉 〈下〉
⑦沖縄空手道拳法会拳武館(剛柔流)〈上〉 〈下〉
【WEB連載終了】沖縄伝統空手のいま~世界に飛翔したカラテの源流:
[シリーズ一覧]を表示する
WEB第三文明で連載された「沖縄伝統空手のいま~世界に飛翔したカラテの源流」が書籍化!
『沖縄空手への旅──琉球発祥の伝統武術』
柳原滋雄 著定価:1,760円(税込)
2020年9月14日発売
第三文明社
【WEB連載終了】長嶺将真物語~沖縄空手の興亡~
[シリーズ一覧]を表示する
WEB第三文明で連載された「長嶺将真物語~沖縄空手の興亡」が書籍化!
『空手は沖縄の魂なり――長嶺将真伝』
柳原滋雄 著定価:1,980円(税込)
2021年10月28日発売
論創社(論創ノンフィクション 015)