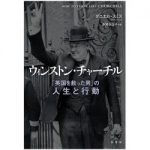逆境を追い風に変える
本書は生誕150周年を迎えたイギリスの政治家ウインストン・チャーチルの評伝である。
チャーチルといえば、第二次世界大戦でヒトラー率いるナチス・ドイツを打ち負かし、連合国を勝利へと導いたイギリスの宰相として名高い。さらにその才能を多方面で発揮した人物で、歴史的な演説を幾度も行い、ノーベル文学賞を獲得した文筆家でもある。40歳から趣味で始めた絵画は芸術家からも賞賛される数多くの作品を生み出した。またレンガ職人という顔という意外な一面も持つ。
しかし、その華やかな業績の裏には多くの苦闘があった。チャーチルほど人生の毀誉褒貶を味わった人もまれであろう。
ほかの人なら打ちのめされそうなときでも、チャーチルは逆境に立ち向かって成功し、どんなに困難なことでも最終的には自分の利益になるように変えていった。「乗り越えた困難は、勝ち取ったチャンスだ」と1943年に述べている。(本書97ページ)
名門貴族の公爵家に生まれたものの、チャーチルの人生は始まりから困難に満ちていた。
虚弱体質で肺炎を患い死線をさまよったこともある。また吃音があり人前で話すことは苦手であった。学校の成績も得意科目と不得意科目の落差が激しく、教師や級友からひどい扱いを受けた。そのようななかで、両親は子どもを突き放す教育方針をとり、家庭の温かさを与えてくれた唯一の存在は乳母だけであったという。名門大学へと進学せず軍隊の士官学校に進学したのも学力不足が原因だ。おそらく20歳ごろのチャーチルを知る人は、彼が後に歴史的偉人になるとは誰も思わないであろう。
普通の人であれば、絶望し、挫折してしまうであろう環境にあって、彼は自分自身の可能性を確信し困難を乗り越えた。この姿勢は後の人生でも一貫している。ここに彼の偉大さがある。
勇気と柔軟性
運命は勇敢な者に微笑むと、チャーチルはいささかも疑っていなかった。この哲学こそ、彼を何年にもわたって突き動かしてきたものだ。(本書45ページ)
柔軟に対処するという点において、チャーチルほど優れた者はいない(本書90ページ)
自身の可能性を信じることは勇気の行動を生み出す。後年、彼は演説のなかで「KBO(戦い続けろ)」というフレーズを幾度も口にしている。
その反面、現実を冷徹に見定め、過度に楽観しない現実主義者でもあった。
チャーチルは、学校や教師が自分の可能性を伸ばすことができなかったのなら、自分で教育すればよいと考えた。また成績不振を悔んだりせず、むしろ劣等生の教室に入れられたことが、その後の自分の母国語の才能を培ったと考えた。こうして彼は読書に励むこととなる。
チャーチルの読書の特徴は、読むスピードの速さ、重要なポイントを手早くつかむ点にあるという。また歴史や文学だけでなく極めて多岐にわたる分野の本を次々と読破していった。本書はそのなかでも特に愛読した本を彼の評価と共に紹介している。
このような読書は彼の筆力を養っただけでなく、ナチスとの戦いにおいては国民を勇気づける言論闘争の原動力となった。さらに歴史に通暁したことが、時代の動向をいちはやく読む力と独自の現実主義を生み出したのであった。
名演説家と呼ばれるチャーチル独特の話し方は吃音を克服する過程から生まれ、絵を描き始めたのは政治的失脚がきっかけであった。不屈の勇気と柔軟な現実主義こそが、逆境を追い風に変える原動力となったのである。
自身の信じる正義を貫く
私がこの国の皆さんから親切な扱いを受けているのは、近年、私が世論に従っているからではありません。やらねばならないことはただひとつ、安全な道はただひとつです。正しくあろうとすること、そして自分たちが正しいと信じることをしたり言ったりするのを恐れないこと。この困難な時代にあっては、それこそが我々の偉大な国民に値する、そして国民の信用を得る、唯一の方法なのです。(「挙国一致内閣の首相に就任したチャーチルが翌年・1941年に国民へ述べた言葉」、本書167ページ)
チャーチルは20世紀のイギリスで最も成功を収めた政治家であったといわれる。しかし、6度も落選の憂き目にあった。自身の理想に忠実であった彼は、所属政党も二度変え、鞍替え出馬さえした。そのように聞くと、人気取りに専念する節操のない政治家であるかのように思われる。だがチャーチルほど自身の理想に忠実な政治家はいない。理想が明確だからこそ実現するための妥協点を見つけ出すことができる。融通無碍な状況対応が可能になるのだ。また選挙民におもねらず、自身の信念を裏切ることは決してしなかった。
彼の信念とは、文明を守り、個人の自由、民主主義を擁護することであった。
ヒトラーに率いられたナチスがドイツで台頭した際、多くの政治家は第一次大戦からのドイツの再建として肯定的な評価を下していた。しかし、チャーチルはその危険性を見抜いて徹底抗戦を唱え、当時イギリスの首相であったチェンバレンの弱腰外交を厳しく批判した。それが災いし「戦争を煽る好戦的な政治家」というレッテルを貼られ、不遇の時代を迎えることになる。
しかし、時代はチャーチルを見捨てなかった。やがてナチス・ドイツがヨーロッパを席巻し、同盟国が次々と崩壊するようになると、イギリスではチャーチルを待望する声が高まった。彼が挙国一致内閣を率いるようになったのは65歳を過ぎていた。当時の平均年齢を考えると引退をしていても不思議ではない年齢になっていた。しかし、ここから彼の本当の偉業は始まり、輝かしい栄光の時代を迎え始める。戦況が劣勢に傾きかけた際には、鍛え抜かれた言論力を発揮し、ときには叱咤激励しながら、国民の心を奮い立たせた。
晩年に至っても果敢な挑戦は続けられる。第二次大戦後、チャーチルは総選挙で敗北を喫し退陣を余儀なくされる。このとき政治家を引退してもその名は歴史に刻まれたであろう。だが彼は政界を引退することなく粘り強さを発揮し、再び首相に返り咲き、円熟した手腕をふるい活躍を続けた。政界から引退したのは亡くなる前年、彼が89才のときであった。
〝優れたドラマのなかでも、彼のドラマは最高だった〟とはチャーチルの死去にあたりドゴールが送った言葉である。
不屈の勇気をもって自身の人生に立ち向かうとき、短所は長所へと変わり、逆境をも味方にすることができる。チャーチルの確信に満ちた言葉と波乱にとんだドラマチックな人生の軌跡は、時代を超えて、読者の心に挑戦の炎をかきたててやまない。
『ウインストン・チャーチル:「英国を救った男」の人生と行動』
(ダニエル・スミス著、多賀谷正子訳/原書房/2025年1月31日)
関連記事:
「小林芳雄」記事一覧