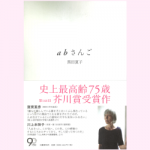読みづらい大和言葉から立ち上がる美しく静かな哀しみ
黒田夏子(くろだ・なつこ)著/第148回芥川賞受賞作(2012年下半期)
史上最高齢75歳での受賞
それまでの史上最高齢の芥川賞受賞者は、「月山」で受賞した62歳の森敦だったが、それを大幅に更新したのが、「abさんご」で受賞した75歳の黒田夏子であった。2012年に早稲田文学新人賞を受賞し、それが同年の芥川賞受賞につながった。彼女の最初の文学賞受賞は、1963年7月度の読売短編小説賞(「毬」で受賞)だったから、実にその49年後の芥川賞受賞ということになる。
その経歴もさることながら大きな注目を浴びたのは、その文体である。読者にとっては慣れない横書きのかな文字が多用され、句読点は「,」「.」で区切り、日常生活に馴染んだ名詞をあえて放棄しそれを分解した形で表現している。たとえば、蚊帳を「へやの中のへやのようなやわらかい檻」と表現し、傘を「天からふるものをしのぐどうぐ」という具合だ。
結果として非常に読みづらい。通常、私たちは漢字かな混じりの文章を読むとき、意味を形で瞬時に伝えてくれる漢字の力を借りて、あえて音に変換しない状態でも意味を理解できるのだが、かな文字が多用された文章を読むとなると、かなの音を漢字に変換して意味を受け取らなければならない。それは慣れない作業なので、恐ろしく疲れる。最初の1ページを読み終えるのに、私も何度も読みかえす羽目となった。選考委員の宮本輝もこう述べている。
じつに読みにくく、読了したときは目と頭が疲れてしまった。二度も読む気になれないにもかかわらず、なにかしら心に残るものがあって、結局、私は三回読み返した。
試しに冒頭の文章だけを掲載してみよう。
aというがっこうとbというがっこうのどちらにいくのかと,会うおとなたちのくちぐちにきいた百にちほどがあったが,きかれた小児はちょうどその町を離れていくところだったから,aにもbにもついにむえんだった.その,まよわれることのなかった道の枝を,半せいきしてゆめの中で示されなおした者は,見あげたことのなかったてんじょう,ふんだことのなかったゆか,出あわなかった小児たちのかおのないかおを見さだめようとして,すこしあせり,それからとてもくつろいだ.
音読しながら読ませる技
なぜこれほど読み手に負担をかける書き方をしたのか。当然ではあるが、理由があるはずだ。
ひとつは、漢語や外来語が入る前から日本にあった大和言葉への尊敬と挑戦であろう。言葉は、意味を伝えるものではあるが、同時にその言葉の音に秘められた感触も伝える。繊細で美しい日本語の言葉の響きを壊さぬように、可能な限りそのままそっと残し伝えようとしたのではないか。
読みづらいがゆえにスピード感を持って読み進むことができない。そうすると、私もそうだったが、一つ一つの言葉の音を確かめながら意味を受け取るために、読み手はいつのまにか音読をしながら読んでいるのに気づく。これも、作者の狙いだったのだろう。
髙樹のぶ子の選評はこうだ。
最初は行きつ戻りつで時間ばかりを取られて苛立つだろうが、おそらく後半では最初の数倍のスピードで読み進むことが出来るだろう。そのとき読者の中に何が起きているのか。大和言葉と一体になることのできる体内リズム、ひらがなを自分の感性と呼吸に沿って自由に意味づける変換力、いや想像力である。つまりは日本語ドリルでもあるのだ。
この小説は、通常の小説に見られるような、主人公の個性の描写や時系列による物語展開を描く方法をとらない。そもそも登場人物の名前さえない。「親」とか「子」とか「小児」とか「家事係」といった茫漠とした表現で登場人物が出てくる。それらの登場人物で構成されるある家族に関する回想が、断片的に脈絡もなく描かれているだけだ。
だけれども、読み進むにつれて、バラバラに存在するそれらの描写からは、美しく深い哀しみが静かに立ち上がってくるのである。
時間経過の中で因果関係を持ちながら激しく物語が変化していく小説形式をハリウッド映画に例えれば、この小説は日本の古典舞踊劇の「能」のようだ。物語展開の面白さはないが、それぞれのシーンが鮮やかに心に残るのである。
小川洋子の選評。
たとえ語られる意味は平凡でも、言葉の連なり方や音の響きだけで小説は成り立ってしまうと、『abさんご』は証明している。
最後まで薄ぼんやりとして分かりづらかったのが登場人物なのだが、宮本輝の次のような選評に深く納得した。
この小説における登場人物は、すべて影であって、影を作りだす本体は、彼らの住む家と、三十年余に及ぶ時間なのだと気づいた。物言わぬ家と長い時間が、心を持つ生き物と化して、淡く静かに人々の営みを照らしている。それが、観念的にではなく、夢のなかの確かな皮膚感覚として心のどこかで長くたゆたうのだ。
「芥川賞を読む」:
第1回『ネコババのいる町で』 第2回『表層生活』 第3回『村の名前』 第4回『妊娠カレンダー』 第5回『自動起床装置』 第6回『背負い水』 第7回『至高聖所(アバトーン)』 第8回『運転士』 第9回『犬婿入り』 第10回『寂寥郊野』 第11回『石の来歴』 第12回『タイムスリップ・コンビナート』 第13回『おでるでく』 第14回『この人の閾(いき)』 第15回『豚の報い』 第16回 『蛇を踏む』 第17回『家族シネマ』 第18回『海峡の光』 第19回『水滴』 第20回『ゲルマニウムの夜』 第21回『ブエノスアイレス午前零時』 第22回『日蝕』 第23回『蔭の棲みか』 第24回『夏の約束』 第25回『きれぎれ』 第26回『花腐し』 第27回『聖水』 第28回『熊の敷石』 第29回『中陰の花』 第30回『猛スピードで母は』 第31回『パーク・ライフ』 第32回『しょっぱいドライブ』 第33回『ハリガネムシ』 第34回『蛇にピアス』 第35回『蹴りたい背中』 第36回『介護入門』 第37回『グランドフィナーレ』 第38回 『土の中の子供』 第39回『沖で待つ』 第40回『八月の路上に捨てる』 第41回『ひとり日和』 第42回『アサッテの人』 第43回『乳と卵』 第44回『時が滲む朝』 第45回『ポトスライムの舟』 第46回『終の住処』 第47回『乙女の密告』 第48回『苦役列車』 第49回『きことわ』 第50回『道化師の蝶』 第51回『共喰い』 第52回『冥土めぐり』 第53回『abさんご』 第54回『爪と目』