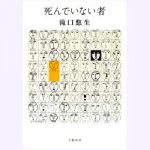葬儀場の人々の描写から、生の滑稽さや愛しさが滲み出る
滝口悠生(たきぐち・ゆうしょう)著/第154回芥川賞受賞作(2015年下半期)
各家庭に存在するさまざまな事情
滝口悠生の「死んでいない者」の舞台は、葬儀場だ。通夜会場、それに隣接する宴会場や控室、そして葬儀場近くの故人の実家とその周辺を舞台とし、多くの親族が登場する。
亡くなった老人の葬儀のために集まった親族の数は、5人の子どもとその家族、孫ひ孫まで入れると、20数人にのぼる。これだけ多くの親族が集まれば、当然、誰と誰がどのようなつながりなのか分からなくなる。しかも、物語は、特定の2、3人だけに焦点を当てるのではなくひ孫まで描いているので、スムーズに読み進めるために筆者は図を書いたほどだった。
それぞれの家庭の事情を絡めながら多くの登場人物を描くことで浮かび上がってくるのは、それぞれに懸命に生きているありのままの人の姿だ。周囲に迷惑ばかりかけて行方不明となっている男、中学時代から不登校となり、今は故人の実家の離れで無職のままひっそりと生きている若者、半ばアルコール中毒の小学生等々、それぞれの事情を抱えた血縁者たちが、一人の老人の死をきっかけに一堂に会いして、酒を飲み、話をする。日常ではありえない不思議な「場」からは、生きることの滑稽さや愛しさが滲み出てくるのである。
宮本輝は、こう評価。
死者は焼かれてどこかへ消えて、生者は葬儀が終われば去って行き、またそれぞれの新しい生を生きていく。その淡々とした営みのなかに人間というもののけなげさをさりげなく描いたとすれば、この作者は相当にしたかだと感じた
タイトルの「死んでいない者」は、〝死んで、いなくなった者〟とも読めるし、〝死んではいない者〟とも読めるが、筆者は後者だと感じた。だとすれば、「生きている者」としてもいいはずだが、あえてこのタイトルにしたのは、〝生きていること〟と〝死んでいること〟とのあいだに、圧倒的な差があるとは思えない感覚を、託したかったからだろう。それぞれに異なる厄介な生を抱えて右往左往しながら生きていくが、それでも結局皆死ぬわけだから、どう生きたっていいじゃないかというような、諦観めいた包容力のようなものを感じるのである。
不確かで揺れる語り手の位置
選考会で最大の議論になったのは、語り手が誰なのかという点についての賛否であった。一応、三人称、すなわち〝神視点〟で書かれてあるのだが、時々、登場人物が語っているようにも感じられる。つまり、視点が確定せず、揺らいでいるのだ。
小川洋子は、まさにこの点を高く評価。
語っているのは誰なのか。もしかしたら滝口さんにも正体は分からないのかもしれない。その不親切ゆえに生じるあいまいさを、私は魅力と受け取った。自在に流動する語り手は、輪郭が堅固でないからこそ、登場人物に対して何の判断も下さず、彼らの心の欠落にそっと忍び込むことができる。どんな出来事も、目に映ったままをただ見るばかりで、余計なものは何も付け加えない。こうした語り手の一貫した態度が、思い出せない、理由がない、説明できない、という否定の形でしか表現できない欠落に、生々しい手触りを与えている
定まった視点で書くということは、登場人物を語り手の視点でカテコライズし、語り手が描く人物として描くということである。そうした視点を取り外すことによって、語り手はその人物に対して、何の判断もせず、ありのままの事実だけを述べることになる。この作品のなかでは、世間一般の常識からするとおかしいとか、許されないといった感覚を抱かざるを得ない、〝欠落〟を持つ人物が何人か登場するのだが、どうしてそうなったのかは本人たちも分からないし説明もできないのである。視点を不明確にしたことによって、そうした〝欠落〟が加工されずに「生々しい手触りを与えている」というわけだ。
奥泉光も同様に評価。
自在なかたりの構成が小説世界に時空間の広がりを与えることに成功している。(中略)死者も生者も、老人も子供も、人間も事物も等しく存在の輪郭を与えられ、不思議な抒情性のなかで、それぞれが確固たる手触りを伝えてくる。傑作と呼んでよいと思います
否定的な意見だったのは村上龍。映画監督の小津安二郎のカメラワークの例を持ち出して、「曖昧な視点」に対して疑問を投げかけていた。
何を、どのように、書くか
作品とは直接関係ないが、川上弘美が「小説を書く」という行為や方法について選評の中で含蓄のある示唆を寄せていたので、最後に、長くなるがそのまま紹介したい。
「何」を、「どのように」書くのかが、大きな問題なのです。小説にとっては、いつも。
「何」と、「どのように」は、分離できません。そのうえ、確固とした「何」が最初からあるわけではない。たとえば中空に浮かんでいる煙をつかもうとするような不確かさのうちにしか、小説家は「何」をつかむことはできない。少しだけでも、つかめるならまだいい方で、何も、つかめないこともある。つかんだとたんに、形が変わってしまうことも、多い。そうやってつかんだ「何」を、自分の選んだ「どのように」の方法で書いてゆくわけですが、「どのように」の選びかたによって、さらに「何」は、変化してゆきます。極端に言うなら、小説の新しい一行を書くたびに、「何」は変わってゆき、それにつれて、「どのように」の方法も、うつろってゆくのです。うつろいつつ書いてゆくのは、ひどく心もとないことです。けれどたぶん、うつろってこその小説、なのです
「芥川賞を読む」:
「芥川賞を読む」一覧
第1回『ネコババのいる町で』 第2回『表層生活』 第3回『村の名前』 第4回『妊娠カレンダー』 第5回『自動起床装置』 第6回『背負い水』 第7回『至高聖所(アバトーン)』 第8回『運転士』 第9回『犬婿入り』 第10回『寂寥郊野』 第11回『石の来歴』 第12回『タイムスリップ・コンビナート』 第13回『おでるでく』 第14回『この人の閾(いき)』 第15回『豚の報い』 第16回『蛇を踏む』 第17回『家族シネマ』 第18回『海峡の光』 第19回『水滴』 第20回『ゲルマニウムの夜』 第21回『ブエノスアイレス午前零時』 第22回『日蝕』 第23回『蔭の棲みか』 第24回『夏の約束』 第25回『きれぎれ』 第26回『花腐し』 第27回『聖水』 第28回『熊の敷石』 第29回『中陰の花』 第30回『猛スピードで母は』 第31回『パーク・ライフ』 第32回『しょっぱいドライブ』 第33回『ハリガネムシ』 第34回『蛇にピアス』 第35回『蹴りたい背中』 第36回『介護入門』 第37回『グランドフィナーレ』 第38回 『土の中の子供』 第39回『沖で待つ』 第40回『八月の路上に捨てる』 第41回『ひとり日和』 第42回『アサッテの人』 第43回『乳と卵』 第44回『時が滲む朝』 第45回『ポトスライムの舟』 第46回『終の住処』 第47回『乙女の密告』 第48回『苦役列車』 第49回『きことわ』 第50回『道化師の蝶』 第51回『共喰い』 第52回『冥土めぐり』 第54回『爪と目』 第55回『穴』 第56回『春の庭』 第57回『九年前の祈り』 第58回『火花』 第59回『スクラップ・アンド・ビルド』 第60回『異類婚姻譚』 第61回『死んでいない者』 第62回『コンビニ人間』