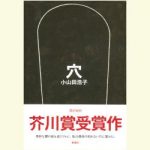ありふれた日常の中にある異界
小山田浩子(おやまだ・ひろこ)著/第150回芥川賞受賞作(2013年下半期)
語らないことで想像をかきたてる
実験的で技巧的な文章にやや食傷気味だった筆者にとって、小山田浩子の「穴」は、とても読みやすく、力を抜いて小説世界に浸ることができた。村上龍が「複雑な構造の作品ではなかったことにまず好感をもった。」と評した通りだ。
――非正規雇用の「私」は、郊外に引っ越すことになった。そこは、夫の実家に隣接する貸家で、家賃はゼロ。お金のためにあくせく働く時間は消え去り、日がな一日することがほとんどない専業主婦の生活が始まった。外を歩く人などほとんどいない強い日差しが降り注ぐ夏。車のない「私」は、コンビニに行くにも時間をかけて徒歩で移動するしかない。
それまでとは全く異なる土地と環境の中で、奇妙な出来事がいくつも起きる。得体の知れない黒い獣の後を追ううちに、背丈ほどもある穴に落ちる。人気の少ない場所と不釣り合いなほどの大勢の子どもたちが河原で遊んでいる。義祖父は、豪雨にもかかわらずひたすら庭に水を撒き、饒舌な義母は小銭をくすねる。そして、その存在など聞いたこともない義兄が、隣接するプレハブ小屋で暮らしていた…。
夢を見ているような、幻想のなかにあるような、ありふれた日常の中にある異界を鮮やかに描き出している。
思えば、近代的な都会生活からは多くの闇が締め出された。コンビニは24時間煌々と辺りを照らし続け、影を保った路地裏は減少し、使途不明な雑然とした空き地は駐車場に化けた。闇に対する恐怖が薄れる中で想像力も衰退していくのが都会生活の一面だとすれば、この世にある不思議や異界をまだ残す可能性が高いのが地方なのかもしれない。なかんずく、親兄弟など血縁の背後に潜むおどろしいものが、隠された平穏の中にひょっこりと顔を覗かせることがあるようだ。
本作品を高く評価した川上弘美の選評はこうだ。
見えているのに、見えていないものが、この作品にはたくさん出てきます。『幻想的な』という言葉では処理できないものとして、それらを書きとめたのが、この作品の素晴らしさだと思いました
ちなみに、得体の知れない黒い獣の後を追って落ちた「穴」とは何なのか、また黒い獣とは何を暗喩しているのか、作品の中では一切語られていない。想像するに、「穴」は、心の中の闇だったり、人生におけるいわゆる落とし穴かもしれない。得体の知れない黒い獣は、人間の業を引き出す誘惑の象徴なのかもしれない。いずれにしても、語らないことによって、なお一層読み手の想像をかき立てる。
芥川賞において「感動」は重要ではない?
なお、今回の選考会では、岩城けいの「さようなら、オレンジ」が宮本輝や小川洋子や高樹のぶ子から非常に高い評価を受けたにもかかわらず、受賞に至らなかった。
この作品は、アフリカ難民としてオーストラリアへと渡ってきた女性が、生きるためにその国の母語である英語を習得しなければいけないことに気づき挑戦を始める物語だ。
宮本輝は、
私は一読して深く感動した。文学の感動、人間の感動というものに心打たれた。しかし、この作品に反対する委員たちの意見は辛辣で厳しくて、受賞には一歩至らなかった
と述べている。
小川洋子も同様だ。
既視感がある、感動があらかじめ用意され、それに人物を当てはめている、(中略)……等々、『さようなら、オレンジ』に向けられた否定的な意見に、私は何の反論もできなかった。すべてその通りだと納得した。それでも尚、私はサリマをいとおしく思うし、トラッキーのために鉄の階段に座り、物語を朗読したいと願う
芥川賞が「感動」というものを必ずしも重視していないことは薄々感じてはいたが、本作を高く評価した高樹のぶ子が、選評で「感動」について語っていたのが興味深かった。概要は、次のようなものである。
文学にとって「感動」は大事だ。どんな種類の感動かはさまざまであり、書かれている中身への共感もあるが、特別な手法に心を揺さぶられることもある。しかし手法にばかり関心が行くと「感心」はしても「感動」には至らない。そうした作品が増える傾向があるのは事実であり、その背景には、個人の実体験が小さいにもかかわらず溢れる情報によって可能となった疑似体験がある。それによって世界は新鮮さを失い、感受性は摩耗し、書くモチベーションも低下する。
その上で、高樹はこう述べる。
そのとき何が起きるかといえば、作者自身の心の動力で読者を揺さぶるという、単純で真っ直ぐな書き方が古びて見え、斬新な手法を模索したくなる。(中略)新しく在るべきは、手法ではなく、自分自身なのだ。(中略)文学も進化して当然だが、それは自分の五感を開き、愚鈍に深呼吸することでしか叶わないのではないか
「芥川賞を読む」:
第1回『ネコババのいる町で』 第2回『表層生活』 第3回『村の名前』 第4回『妊娠カレンダー』 第5回『自動起床装置』 第6回『背負い水』 第7回『至高聖所(アバトーン)』 第8回『運転士』 第9回『犬婿入り』 第10回『寂寥郊野』 第11回『石の来歴』 第12回『タイムスリップ・コンビナート』 第13回『おでるでく』 第14回『この人の閾(いき)』 第15回『豚の報い』 第16回 『蛇を踏む』 第17回『家族シネマ』 第18回『海峡の光』 第19回『水滴』 第20回『ゲルマニウムの夜』 第21回『ブエノスアイレス午前零時』 第22回『日蝕』 第23回『蔭の棲みか』 第24回『夏の約束』 第25回『きれぎれ』 第26回『花腐し』 第27回『聖水』 第28回『熊の敷石』 第29回『中陰の花』 第30回『猛スピードで母は』 第31回『パーク・ライフ』 第32回『しょっぱいドライブ』 第33回『ハリガネムシ』 第34回『蛇にピアス』 第35回『蹴りたい背中』 第36回『介護入門』 第37回『グランドフィナーレ』 第38回 『土の中の子供』 第39回『沖で待つ』 第40回『八月の路上に捨てる』 第41回『ひとり日和』 第42回『アサッテの人』 第43回『乳と卵』 第44回『時が滲む朝』 第45回『ポトスライムの舟』 第46回『終の住処』 第47回『乙女の密告』 第48回『苦役列車』 第49回『きことわ』 第50回『道化師の蝶』 第51回『共喰い』 第52回『冥土めぐり』 第53回『abさんご』 第54回『爪と目』 第55回『穴』 第56回『春の庭』