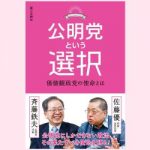佐藤氏から呼びかけた対談
斉藤鉄夫氏(公明党代表)と佐藤優氏(作家・元外交官)の対談集が、このほど第三文明社から刊行された。
ポップなピンク色のカバーで、親しみやすいイメージだ。対談は本年(2025年)3月に収録された。関係者によると、対談を呼びかけたのは佐藤氏であったという。
よく知られたように佐藤氏は日本基督教団に属するプロテスタントのキリスト教徒。しかし、『池田大作全集』全150巻を揃えて読み込み、公明党はもちろん、創立者でもある池田大作・創価学会第3代会長についても多くの言論を発信してきた論客でもある。
その点では、宗教学者や宗教ジャーナリストを名乗りながら池田会長の著作すら読まずに創価学会について語ってしまうような者があとを絶たないなかで、佐藤氏の創価学会理解はその〝格〟を異にしている。
公明党は2024年10月の総選挙で、就任まもない代表まで落選するという〝大敗〟を喫した。その緊急事態のなかで、斉藤氏は本人すら想像していなかった新代表の任に就くことになった。
まず、本書の目次を紹介する。
まえがき(佐藤優)
第一章 最近の公明党、近ごろの自公政権
常に思い出す高校時代の池田先生の言葉
公明党の原点はあくまでフェース・トゥ・フェース
代表特命のユーチューバーが誕生⁉
支援活動には功徳がある
自民党の「心のありよう」を変えられるか
裏金議員の推薦は悪手だったのか
見送られた核禁条約締約国会議へのオブザーバー参加
自民党と外務省の方針を変えられるか
公明党はもっとアピールするべき?
これまでとは質が変わった自公政権
高額療養費制度の二転三転はなんだったのか第二章 大衆政党ならではの政策
なぜ公明党は政治の混乱を避けるのか
公明党が全国の高校の総点検を
高校教育のあり方を検討すべき
過熱する中学受験にどう対応するべきか
維新の教育政策に思うこと
排外主義を許してよいのか
米不足を一時的に防いだ沖縄の〝助け合い〟
物価高対策と〝減税ポピュリズム〟との天秤
公明党の良識がマイナスになる時代⁉
在外被爆者援護対策の実績と課題
〝時刻表鉄(読み鉄)〟の国交大臣
斉藤鉄夫が体現する中道政治とは第三章 いま公明党が進むべき方向
「斉藤さんと話すと元気になる」
〝国民のため〟は建前?
歴史修正主義といかに向き合うか
対話の回路は閉ざさないほうがよい
池田先生の言葉を体現できるか
倫理や自律心が試される政治の世界
〝信教の自由〟が直面する目下の課題
「境涯」という概念を日本政治に持ち込めるかあとがき(斉藤鉄夫)
斉藤代表が発した厳しい言葉
第一章では、まず昨年の総選挙を総括する。斉藤代表が党内総括の結論として言及したのは、「SNS戦略の弱さ」である。この1、2年で選挙におけるSNSの影響力は格段に強くなり、まったくフェーズが変わったといってよい。
従来、SNSは若い人のツールと見なされてきたが、コロナ禍を経て、むしろ60代や70代でも動画などで投票行動を変えるようになっている。
公明党は内輪のメディアや組織が整備されていることもあり、気づかぬうちに発信がことごとく〝内向き〟になってしまっていた。
その結果、SNSを始めたものの、票の拡大を勝ち取るべき〝外側〟の無党派層などに、ほとんど発信が届いていなかったのである。
一方、佐藤氏が強調したのは、公明党の主要な支持者である党員や創価学会員は、先の総選挙を〝負け戦〟と捉えるべきではないというアドバイスだった。
佐藤氏は、総選挙での議席減は、あくまで自民党の「政治とカネ」に関する〝もらい事故〟のようなもので、むしろ事前の厳しい予測に対して公明党は想像以上に善戦したというものだ。
それは、直後の2025年1月におこなわれた北九州市議選で、新人4人を含む候補者13人の全員当選に明らかだと佐藤氏は言うのである。
宗教者である佐藤氏は、支持団体である創価学会の会員が、元気を出せることが何より大事だと考えているのかもしれない。
総選挙後、公明党では新たなSNS戦略として「公明党のサブチャンネル」をはじめ、動画コンテンツを中心に大胆な試行錯誤を始めている。
興味深いことに「公明党のサブチャンネル」は、党員・支持者よりも他党支持層から注目されているようで、コメント欄にも他党支持層からの好意的な声が続いている。
まだ始まったばかりの取り組みではあるが、これまで訴求できていなかった層に、少しずつ公明党の姿や考え方が届きつつあるのならよい傾向だ。
SNSに関して、佐藤氏は若手の国会議員から男女1名ずつ、斉藤代表の特命で「双方向かつタブーなしで視聴者に語りかける」ユーチューバーを党内に作ることを提案している。
本書で佐藤氏が強調していることの一つは、公明党議員の役割として「自民党の心のありようを変えさせる」ことだ。
国会議員や都議会議員による政治資金報告書の不記載問題など「政治とカネ」だけでなく、石破首相の10万円商品券問題など、やはり自民党内部の金銭感覚は庶民感情から乖離している。
佐藤氏はこうした問題は規制したところで必ず抜け道を作ってくるものなので、やはり政治家自身の内的な倫理観を変えていくしかないと考えている。そして、自民党議員の「心のありよう」まで変えていけるのは、友党である公明党しかないと言う。
こうしたことも、宗教者ならではの視点だと思う。「自公連立」の肝は、やはり人間的な交流のなかで、自民党議員や関係者、その支持者らの「心のありよう」に公明党が感化を及ぼしていけるかどうかにかかっている。
やや興味深いやり取りもあった。公明党が強く主張していた核兵器禁止条約第3回締結国会議への日本のオブザーバー参加が見送られた件について話が及んだときである。
政府がオブザーバー参加しないなら、公明党のように自民党が議員を派遣することはできないのかと斉藤代表は石破首相に尋ねたという。石破首相からは感触のよい反応があった。
ところがこれについて、自民党の森山幹事長から公明党の西田幹事長に、「議員派遣はしない」と返答があった。じつはこの時点で石破首相は森山幹事長から何の相談も受けていなかった事実を、斉藤代表は本書で明かしているのだ。
温厚な斉藤代表は珍しく「厳しい言い方になりますが、石破さんにはもう少し党内での発言力を強めてもらわないといけません」と注文を付けている。
佐藤氏は、冷戦時代1985年の中曽根首相とゴルバチョフ書記長の会見に言及し、今は平行線にしか見えない関係もやがて交わるときがくるという国際政治について語る。
今、目の前の出来事だけを見て、政治に失望したり、あるいは公明党に疑念を抱いたりというような短慮に陥ることは愚かである、と。そして、公明党にとって核廃絶は一丁目一番地のテーマだからこそ、どこまでもあきらめずに進むよう佐藤氏は斉藤代表を励ましている。
公明党が想定している「大衆」とは
第二章では、とりわけ物価高と米不足という、現下の国民の最大の関心事についても語り合われている。
佐藤氏は、
先の〝減税ポピュリズム〟にも通じますが、よくも悪くも分かりやすくなければ理解してもらえないんでしょう。「消費税をゼロにします」「手取りが増えます」といったような。だから、「赤字国債を発行してでも減税すればいいじゃないですか」といった声も出てくるわけです。そう考えている人たちにとっては、公明党の良識はむしろマイナスになるんでしょうね。これは公明党が踏ん張らないといけないときということですよ。(佐藤氏)
と語る。
対談は3月であるが、6月の世論調査を見ると、消費税減税を主張しなかった自民党が支持率を伸ばし、主張した野党は軒並み支持率を下げている。
多くの国民は、減税ポピュリズムの危うさを案外理解しているのかもしれない。
佐藤氏は、借金をして減税するなど、もはや政策と言えず、「構造的には国債を発行して戦艦や戦闘機をつくった旧軍(旧日本軍)の発想と同じ」できわめて無責任だと斬り捨てている。
政治をめぐる社会の空気が野党によってポピュリズムに染まりつつあるなかで、公明党の役割とは何か。佐藤氏は続ける。
公明党が想定している大衆とは、理性的に判断ができる一人一人です。烏合の衆ではない。別の言い方をすれば、バラバラで自分のことしか考えていない人間から大衆に育っていくプロセスを支えているのが公明党です。これには時間がかかるので、これまでどおり愚直に良識を訴えていくしかないですね。(佐藤氏)
第三章では、公明党がこれから進むべき道について語らいが進む。
佐藤氏は、今年(2025年)が戦後80年の節目であることに触れ、「歴史修正主義といかに向き合うか」の問題を提起する。
斉藤代表も、東アジアの平和をどのように維持するかが公明党の最重要課題であると語る。
非軍事による国際協力に徹し、国際社会から厚い信頼を得てきた日本の役割、日本への期待はますます大きくなっています。「平和の党」として、「戦後八十年」「被爆八十年」「国連創設八十年」の節目に、いま再び平和の潮流をつくり出していきたいと考えています。(斉藤代表)
佐藤氏は米国の北朝鮮政策に関連して、トランプ大統領は前政権と異なり、対話によって平和を模索しようとしていると見ている。「平和を脅かす勢力とは、むしろ対話の回路を閉ざさないほうがよい」というのが、佐藤氏の考え方だ。
これは、冷戦期に中国やソ連の首脳と対話を続け、キューバのカストロを平和行脚へ促した池田会長の信念とも通じ合うものだろう。
斉藤代表も賛意を示し、公明党の平和政策に反映したいと応じる。
たとえばミャンマーでクーデターを起こした軍政府に対し、日本政府や公明党が「断交」のような強硬措置を取らずにいることを非難する人々が一部にいる。
しかし、関係を断ち切ってしまえば関与する影響力も失ってしまう。ミャンマーでの先の大地震に際し、公明党や日本政府は日本赤十字と連携しての支援や、国際緊急援助隊の医療チーム派遣などを実施した。
厄介な相手、問題の多い相手だからこそ、対話のチャンネルが必要なのだ。
公明議員は創立者の言葉を語れ
佐藤氏が最後に提案するのは、公明党創立者である池田会長が主著『人間革命』の冒頭に綴った、
戦争ほど、残酷なものはない。
戦争ほど、悲惨なものはない。
という言葉を、公明党議員はもっと積極的に使ってもらいたいということだった。
公明党が今までよりも幅広い有権者から支持される政党になるために、目下、「サブチャンネル」などでもタブーのない議論がおこなわれている。
世間の人々が漠然と抱くイメージは、公明党=創価学会=宗教=怪しいというものだ。
しかし、世界には宗教理念を基盤とした政党はあたりまえのように存在するわけで、宗教だから不気味だとか胡散臭いというのは、単なる無知と偏見に過ぎない。
もちろん、公明党が今よりもさらに創価学会の外に開かれていくべきことは自明のこととして、しかし創価学会とのかかわりをなくすことは、党のアイデンティティの否定になる。
佐藤氏は以前から、創価学会と公明党のあいだの〝行き過ぎた政教分離〟を是正すべしと主張してきた。つまり、池田会長によって創立され、創価学会の宗教的理念を土台の部分で共有している「価値観政党」であることを、むしろ自分たちの唯一無二の強みにすべきだということだ。
公明党がその価値観として置いている創立者の理念や創価学会の人間主義は、宗教やイデオロギーの差異を越えて世界の第一級の識者たちが広く共感してきたものだ。
公明党にとって、その「価値観」はアイデンティティであると同時に、他党が絶対にマネのできない強みであるはずだ。
そこに日本社会特有の先入観に基づく誤解があるのなら、その先入観を覆していく優れたコミュニケーションこそが大事なのである。
公明党の価値観を大切に守りながら、そこに思想信条を越えて、多くの人が信頼と共感を寄せられる新しい姿を模索していくしかない。
「あとがき」のなかで、斉藤代表は公明党が主張している「アジア版OSCE」について記している。これはとくに北東アジアの平和構築のために、北朝鮮を含む関係諸国で常設の対話機構を創設しようというものだ。
斉藤代表によると、佐藤氏との対談のあと訪中し(4月22日~24日の公明党訪中団)、中国共産党の要人にこの構想を説明し意見を交わしたという。すると、中国側からも対話・協議の枠組みについては一定の理解が示され、今年秋に予定されている日中与党交流協議会で具体的に議論したいという発言があったというのだ。
6月22日には東京都議会議員選挙があり、7月には参議院選挙が控えている。物価高騰や円安などで国民の不安と不満が高まるなか、政治の空間でも極端な排外主義や復古主義的なナショナリズム、耳触りのよい無責任な減税ポピュリズムが蔓延している。
他方、社会の構造が大きく変わり始めるなか、公明党が昭和の時代から得意としてきた選挙の手法も、さまざまな点で根本的な見直しが必要となってきた。
このことは、支援の現場に立っている若い創価学会員ほど強く実感していることだと思う。
これから数年は、公明党の支持拡大に関しても、さまざまな試行錯誤が続くことになるだろう。行き詰まりに直面しているのであれば、それは公明党と支持者にとって突きつけられた、挑むべき新しい課題なのだ。
日本の政党のなかで、「生命尊厳」「平和主義」「人間主義」といった理念を一貫して掲げ続けてきた「価値観政党」は、公明党しかない。
「公明党という選択」という本書のタイトルは、なかなか示唆的である。
友人知人に公明党を選択してもらう前に、自分自身がなぜ公明党に投票するのか、そこをあらためて問い直し、自分がまず〝選択〟し直す必要がある。
公明党にしかできない政治とはなにか。その原点と未来を考える上で、大いに参考になる一冊だ。
『公明党という選択 価値観政党の使命とは』
斉藤鉄夫・佐藤優定価:990円(税込)
2025年6月10日発売
第三文明社
関連記事:
公明党の「平和創出ビジョン」――2035年までを射程とした提言
「外免切替」デマ、国会で決着――国民の不安解消を求めた公明党
変わりはじめた公明党の発信――他党支持者からも好評
「年収の壁」問題は協議継続へ――与野党の合意形成に期待する
公明党、反転攻勢へ出発――「外側」の意見を大切に
公明党、次への展望(前編)――時代の変化に応じた刷新を願う
公明党、次への展望(後編)――党創立者が願ったこと
自公連立25年の節目――「政治改革」もたらした公明党
公明、「平和創出ビジョン」策定へ――戦後80年となる2025年
なぜ公明党が信頼されるのか――圧倒的な政策実現力
公明党を選ぶべき3つの理由――地方議員「1議席」の重み
2023年度予算案と公明党――主張が随所に反映される
都でパートナーシップ制度が開始――「結婚の平等」へ一歩前進
書評『今こそ問う公明党の覚悟』――日本政治の安定こそ至上命題
G7サミット広島開催へ――公明党の緊急提言が実現
核兵器不使用へ公明党の本気――首相へ緊急提言を渡す
「非核三原則」と公明党――「核共有」議論をけん制
ワクチンの円滑な接種へ――公明党が果たしてきた役割
「政教分離」「政教一致批判」関連:
公明党と「政教分離」――〝憲法違反〟と考えている人へ
「政治と宗教」危うい言説――立憲主義とは何か
「政教分離」の正しい理解なくしては、人権社会の成熟もない(弁護士 竹内重年)
今こそ問われる 政教分離の本来のあり方(京都大学名誉教授 大石眞)
宗教への偏狭な制約は、憲法の趣旨に合致せず(政治評論家 森田実)
旧統一教会問題を考える(上)――ミスリードしてはならない
旧統一教会問題を考える(下)――党利党略に利用する人々