日本史に入り込んだヘラクレス
クリスマスはキリストの降誕を祝う祭祀だが、じつは新約聖書にはその具体的な「日付」がいつだとは出てこない。それで12月25日がクリスマスになったのは、キリスト教が小アジアに伝播していく途中で、おそらくそれらの地域にあった冬至の祭祀と習合していった結果だろうといわれている。 続きを読む

クリスマスはキリストの降誕を祝う祭祀だが、じつは新約聖書にはその具体的な「日付」がいつだとは出てこない。それで12月25日がクリスマスになったのは、キリスト教が小アジアに伝播していく途中で、おそらくそれらの地域にあった冬至の祭祀と習合していった結果だろうといわれている。 続きを読む
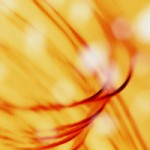
民放のバラエティー番組で「オネメン」を紹介するコーナーがあった。オネメンというのは、〝オネエ系イケメン〟の略語らしい。
「外見は女性を大いに魅了するのに、残念ながら彼らが女性の愛に応えることはない」という女性目線からの設定だ。 続きを読む

今から10年ほど前――ブッシュ大統領の米国がイラク攻撃を始めたころだったから、2003年4月のころである。
芥川賞作家で元共同通信記者だった辺見庸氏が母校の早稲田大学の客員教授になり、マスメディア論を1年間講義したことがあった。そのころ、たまたま縁があり、仕事として授業を毎回傍聴する機会があったのだが、近年まれに見る戦争の始まりと、加熱するメデイア(活字・映像を問わない)を背景に、マスメディアというものが、人々の意識にどのような影響を及ぼすかといった観点から、毎回興味深い授業がなされていた。 続きを読む

「人間が不幸なのは、 自分が本当に幸福であることを知らないからである。 ただそれだけの理由によるのだ」
――ドストエフスキーの『悪霊』の一節である。
「しあわせの青い鳥」を探す旅に出たものの、つかまえることができず、家に帰ったら昔から飼っていたキジバトが「しあわせの青い鳥」に変わっていた、というメーテルリンクの戯曲を思い出す。
幸せは遠くに求めるべきものではなく、なにげない日常生活の中にこそある。しかし、多くの人はその幸せに気づくことができない。……などと言うと、お坊さんの法話のようなクサイ人生訓めいてしまうが、最近私はしみじみ「ほんとうにそのとおりだ」と思っている。 続きを読む

ノーベル平和賞を受賞したケニアのワンガリ・マータイさんは、日本で覚えた「もったいない」という言葉を、環境保護の智慧を含んだキーワード「Mottainai」として世界に発信した。
2009年のラマダン(イスラムの断食)期間中にサウジアラビアで放映された『ハワーティル(改善)』というテレビ番組は、たちまち同国の人々を釘付けにし、シリア、ヨルダン、エジプト、イラクなど周辺のアラブ諸国でも反響を呼んだそうだ。
この番組は、学校で生徒たちが掃除をする、時間を正確に守る、順番に並ぶ、落ちていた財布を交番に届けるといった日本人の振る舞いを、驚きをもって紹介しながら、自分たちの社会も日本を模範に〝改善〟していこうという内容だ。 続きを読む