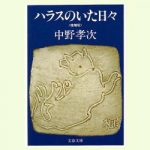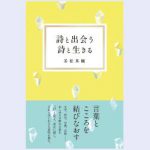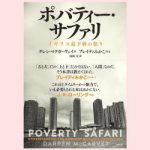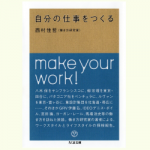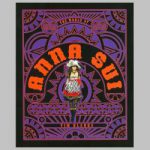僕は、子どものころから家で犬を飼っていて、結婚して家を出るまで、犬のいなかったことがなかった。ところが上京して妻と暮らすようになったアパートはペットを飼うことができなかったので、長く犬のいない生活を送ることになった。
犬がそばにいないので、犬の映画を見たり、犬が主人公の本を読んだりするようになった。そのなかで、名作だとおもったのが、『ハラスのいた日々』だ。著者は、ドイツ文学者の中野孝次。翻訳だけでなく、小説、エッセイ、批評の執筆と幅広く活躍した。
ハラスは、子どものいない中野夫妻の家に来た犬のことだ。「HARAS」(ハラス)――ドイツ人が大型のシェパードにつけることが多い名だという。思いがけず庭付きの家を新築することになり、義妹にお祝いは何がいいか、と訊ねられ、ふと、犬がいい、と応えた。
やって来たのは、大型のシェパードではなく、柴犬の子どもだった。中野は、散歩の相棒にと軽く考えていたのだが、そのうち「たんなる犬以上の存在」になった。作品は、小説仕立てで、その過程をすぐれた文章で綴っていく。 続きを読む