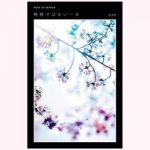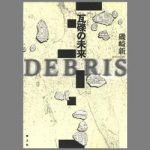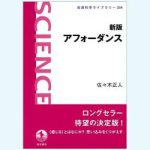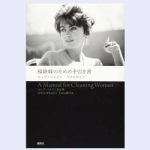今回の本は、『kaze no tanbun 特別ではない一日』である。キーワードは、「tanbun」だろう。日本語表記にするなら、おそらく「短文」。これを、どのように解釈するかが、まず、ポイントになる。
短い文章――短篇小説、エッセイなど、普通に思い浮かべるのは、そのあたりだろうか。編者は、西崎憲。福岡の出版社・書肆侃侃房(しょしかんかんぼう)から発刊された文芸誌『たべるのがおそい』の編集長を務めた人物だ。
もともと作曲から出発し、翻訳をするようになり、のちに小説や短歌を書くようになった。『たべるのがおそい』が話題になったのは、掲載作から芥川賞の候補作が選ばれたことが大きい。 続きを読む