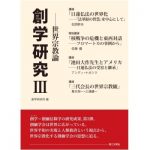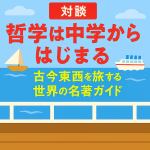来秋までに「中道改革ビジョン」を策定
公明党は11月29日に開催された「全国県代表協議会」で、「政策5本柱」を打ち出し、「中道改革勢力の軸」として出発することを約し合った。
公明党は29日、各都道府県本部の幹部を集めた「全国県代表協議会」を党本部で開いた。連立政権離脱後の党の理念や政策の5本柱を示し、1人当たり国内総生産(GDP)の倍増などを掲げた。来秋の党大会までに「中道改革ビジョン」を策定する方針も表明。斉藤鉄夫代表は「中道改革の旗を高く掲げ、与野党の結集軸として新たな地平を力強く切り開く」と意気込んだ。(『毎日新聞』11月30日)
周知のとおり、公明党は10月10日をもって足掛け26年に及んだ自民党との連立に「区切り」をつけ、石破内閣の総辞職と同時に〝野党〟の立場になった。
自民党は日本維新の会との閣外協力による〝連立〟(国際的にも政治学の世界では閣内協力しない政党間による政権を「連立」とは呼ばないが、自維政権は合意文書で「連立」と呼称している)を組み、高市政権の樹立にこぎつけた。 続きを読む