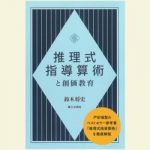100万部超の人気を誇った学習参考書
著者の鈴木将史氏は数学者であり、2022年から2025年まで創価大学の学長を務めた。現在は同大学顧問であり教授である。
1930(昭和5)年6月に出版された『推理式指導算術』は、そこから11年間も版を重ね、累計100万部を超す異例のミリオンセラーとなった。
最終版は1941(昭和16)年8月10日で、じつに「改版改訂126版」となっている。圧倒的な人気を博したことがわかる。
この『推理式指導算術』は当時の中等学校(中学校・高等女学校・実業学校の総称)の受験をめざす小学生の自習のために書かれた書物だった。今でいう受験参考書である。
21世紀の初めごろまでは、年配の学識者や財界人のなかにも、この本のおかげで数学が好きになってずいぶんと助けられたと語る人が珍しくなかったほどだ。
周知のように当時は既に日中戦争が泥沼化しており、1941(昭和16)年12月には真珠湾奇襲によって米英との開戦となる。
昭和15年度からは中等学校の入学試験が廃止されていた。既に1938(昭和13)年には国家総動員法が制定され、1941年2月には学校報国隊が結成されるなど、もはや教育現場は戦争への総動員体制に組み込まれていたのである。
1941年で版が途切れたのは、そのような事情だと思われる。
今も残されている初版本を見ると、著者の名前は「戸田城外」。出版元は「創価教育学支援会」となっている。
この大ベストセラー参考書を著した数学者であり教育者の戸田城外(1900~1958)であるが、後述するように彼は1943年に不敬罪と治安維持法違反容疑で逮捕され、2年の獄中生活に耐えたのち、名前を「城聖」と改めた。
1951(昭和26)年に創価学会の第2代会長に就任し、今日では世界192カ国・地域に広がる在家仏教運動の、日本の基盤を作った宗教家として知られている。
戦前のミリオンセラー数学参考書と宗教運動の取り合わせに戸惑う読者もいると思うので、本書に沿って簡単に背景を記しておきたい。
石川県で生まれ、幼少期から北海道で育った戸田は、1918(大正7)年、尋常小学校本科正教員検定試験に北海道内で1番の成績で合格している。1920年1月に青雲の志をもって上京し、その際に紹介を受けて訪ねたのが、同じ北海道出身の教育者・牧口常三郎だった。
これを縁として、戸田は牧口が校長を務めていた東京の西町尋常小学校に勤務。その後、師と仰いだ牧口の転任に従って自分も三笠尋常小学校に奉職するが、1922年に退職すると保険外交員として働きながら補助学習塾を始めた。
1925(大正14)年には、上大崎の地に「時習学館」を新築している。
一方の牧口にもこの頃、自分が理想とする「子どもの幸福のための教育」理念を世に問いたいという秘めた思いがあった。
戸田は牧口が書き溜めていた手稿を整理し、出版資金も提供して、『推理式指導算術』刊行から5カ月後の1930年11月18日に、牧口の畢生の大著となる『創価教育学体系』第1巻を刊行している。
発行元は「創価教育学会」。牧口の教育理念に「創価教育」という名称を提案したのも戸田であった。
創価教育学会は、言うまでもなく、戦後まもなく戸田によって創価学会と改称される組織である。この奥付の日付(1930年11月18日)が同会の創立の日とされることになる。
『創価教育学体系』と「双子」の関係
こうしてみると、戸田の『推理式指導算術』刊行と牧口の『創価教育学体系』刊行の準備が、ほぼ同時進行していたことがわかる。
両方の出版作業を同時に進めていた戸田先生の中では、扱っている内容や対象となる読者は全く異なるものであっても、2つの書物が一体となり、いわば「理論と実践」の関係にあったものと思います。『推理式指導算術』の発行元が、本来『創価教育学体系』出版を支援するために作られた「創価教育学支援会」となっていることが、この一体感を表しています。(本書)
じつは、『推理式指導算術』の裏表紙には「創価教育学原理による」と記されている。その意味では、『創価教育学体系』より5カ月ほど先んじて、文字どおり最初に「創価」「創価教育」の名を冠したのが『推理式指導算術』であった。
牧口常三郎は、この『推理式指導算術』に「序」と題する序文を寄せている。そこには、
これ余が創価教育学樹立の動機となり、しかもその内容の重要なる一部を占めるものである。余の説かんとする所は、理論上の確信に止まってその真理の実証はいまだ余の企図する能(あた)わざるところなりしも、かねて余の学説を支持せられたる戸田城聖氏が多年の経験を包容せる本書によりてわが学説の万遺憾なき実証と普遍性を見しは余の最も愉快とするところである。
と記されている。
牧口の言う「余の学説」とは、これまで牧口の著作として広く知られてきた『価値論』のみを指すのではないかと著者は指摘する。
むしろ、『価値論』を時習学館における実際の教育に応用しようと試みたのが『推理式指導算術』だったと著者は見ている。
なお、本書の執筆にあたって著者は『戸田城聖全集』第9巻に収録された『推理式指導算術』を引用しているため、上記「序」では「戸田城聖氏」となっているが、当時販売されていた『推理式指導算術』では当然ながら「戸田城外氏」となっている。
このように、刊行の経緯や時期から見ても、牧口による「序」を見ても、戸田の『推理式指導算術』が牧口の創価教育学説の実践であったことは明らかである。それは単なる「理論と実践」というものではなく、
ある意味では「双子」のように世に送り出された2つの書物(本書)
であった。
ところが、『創価教育学体系』が創価教育の原点の書物として広く知られ、翻訳も含めて様々なかたちで出版されてきたのに対し、『推理式指導算術』は単なる戦前の参考書と見なされて、そもそも今日では入手困難になっている。
それは牧口と戸田の師弟が当時に抱いていた思いと乖離するのではないかというのが、著者が本書を手掛けた動機であった。
また、『推理式指導算術』を読み解くことは、そのまま戸田城聖という人と創価教育というものを理解するうえで欠かせないと考えた。
本書の第4章は、とりわけ大きな紙幅を割いて『推理式指導算術』に基づく推理練習が展開されている。
個別具体的な「問」と「解」があり、そのあいだに「戸田先生の推理法解説」が説明されている。これによって、戸田がどのように数学の解き方を捉えていたか、そこにどのように牧口の教育理念が生かされていたかが再現されている。
創価教育学とその実践
なお、著者は本書の終盤で次の点に言及している。
それは今日にあって、「創価教育学」という言葉と「創価教育」という言葉が混在して用いられていることである。
理論や実践に基づいて「教育はこのように行うべきである」という原理や法則を考えるのが「教育学」、そして実際に学習者に対して行われるのが「教育」です。創価教育についても、牧口先生が『創価教育学体系』で様々な観点から展開されている指導原理が「創価教育学」で、その考えを取り入れて創価大学や創価学園などで行われている教育が「創価教育」です。(本書)
こうした点を整理したうえで、著者は「創価教育の実践としての10の観点」を詳細に綴って本書を終えている。
牧口と戸田という教育者の師弟によって生み出された「創価教育」は、戦前ひとたびは創価教育学会として教育者のあいだに共感を広げかけた。
だが、日本は日中戦争に突入し、さらに英米との開戦に突き進んでいく。国家神道を総動員体制の支柱にした国家の暴走とパラレルに、牧口と戸田は「教育改革」から「宗教改革」へと舵を切っていった。
そのために牧口と戸田は、1943年7月、不敬罪と治安維持法違反容疑で逮捕・投獄されるのである。老齢の牧口は1944年11月18日に、獄中でその生涯を閉じている。
この愚かな国家の暴走を許した根源に、国民自身の宗教観の浅薄さがあったと考えた戸田は、生きて出獄したあと、前述したように「城聖」と改名し、終戦まもなく創価教育学会を創価学会と改称して、本格的な「宗教改革」の険路を歩み出すことになる。
ただ、それと同時に戸田の胸中には師から託された「創価教育」の実践への夢と決意が燃え続けていた。
それは時移って、第3代会長となる池田大作によって、幼稚園から大学院までの創価一貫教育の学び舎として具現化する。
戦後の焼け野原で戸田が1人立って再建した創価学会は、世界教団として大発展を遂げた。しかし、創価教育の機関は、名実ともに「創価教育」実践の学舎であって、いかなる宗教教育もおこなわない。
そして今日、創価教育はアメリカ創価大学をはじめ、世界各国でその実践の教育機関を誕生させ、世界市民の育成に寄与している。
各国の教育関係者も頻繁に創価学園や創価大学を訪問し、その教育の成果を学ぼうとしている。牧口と戸田の師弟が1930年に相次いで刊行した2つの書物は、1世紀近い時間を経て、文明も宗教も越えて世界の教育界の共有する知恵になろうとしているのである。
本書が1人でも多くの人に読まれ、やがて各国でも読まれることを切に願う。
「本房 歩」関連記事①:
書評『エモさと報道』――「新聞」をめぐる白熱の議論
書評『人はなぜ争うのか』――戦争の原因と平和への展望
書評『見えない日常』――写真家が遭遇した〝逮捕〟と蘇生の物語
書評『歌集 ゆふすげ』――美智子さま未発表の466首
書評『法華経の風景』――未来へ向けて法華経が持つ可能性
書評『傅益瑶作品集 一茶と芭蕉』――水墨画で描く一茶と芭蕉の世界
書評『もし君が君を信じられなくなっても』――不登校生徒が集まる音楽学校
書評『LGBTのコモン・センス』――私たちの性に関する常識を編み直す
書評『現代台湾クロニクル2014-2023』――台湾の現在地を知れる一書
書評『SDGsな仕事』――「THE INOUE BROTHERS…の軌跡」
「本房 歩」関連記事②:
書評『歴史と人物を語る(下)』――生命を千倍生きゆけ!
書評『ヒロシマへの旅』――核兵器と中学生の命をめぐる物語
書評『アレクサンドロスの決断』、『革命の若き空』(同時収録)
書評『新装改訂版 随筆 正義の道』――池田門下の〝本当の出発〟のとき
書評『希望の源泉 池田思想⑦』――「政教分離」への誤解を正す好著
書評『ブラボーわが人生4』――心のなかに師匠を抱いて
「池田大作」を知るための書籍・20タイトル(上) まずは会長自身の著作から
「池田大作」を知るための書籍・20タイトル(下) 対談集・評伝・そのほか
書評『創学研究Ⅱ――日蓮大聖人論』――創価学会の日蓮本仏論を考える
書評『公明党はおもしろい』――水谷修が公明党を応援する理由
書評『なぎさだより』――アタシは「負けじ組」の組員だよ
書評『完本 若き日の読書』――書を読め、書に読まれるな!
書評『新版 宗教はだれのものか』――「人間のための宗教」の百年史