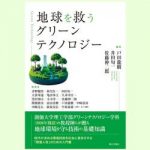日本初のグリーンテクノロジー学科が開設
2025年2月25日、日本政府は「GX(グリーン・トランスフォーメーション)推進法」改正案を閣議決定した。「産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社会システム全体を変革すべく、エネルギーの安定供給・経済成長・排出削減の同時実現を目指す」というものである。
今年(2025年)の日本の夏は、北海道を含む各地で40度越えの気温が連日のように観測されるなど、史上最も暑い夏となった。一方で線状降水帯が同じく各地でしばしば発生し、例年の8月1カ月分の雨が数時間ないし1日で降るというような異常気象も見られた。
これら気候変動の要因が主に二酸化炭素など人類社会が排出したものであることは論を俟(ま)たない。世界平均地上気温の推移と人類が排出してきた二酸化炭素の累積量が相関関係にあることは、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書等で早くから指摘されているところだ。
温暖化対策に関する国際的な枠組み「パリ協定」を踏まえ、日本政府は菅政権時代に所信表明演説で「温室効果ガスの排出量を2050年に実質ゼロにする」という新たな目標を表明している。
2050年までにゼロという目標を定めているのは、世界の平均気温上昇を1.5度までに抑えるためには、2030年までに、二酸化炭素を約45%削減(2010年比)し、遅くとも2050年頃には実質ゼロにする必要があるからだ。
こうした世界の流れを受けて、創価大学(東京・八王子市)は2026年4月に、日本の大学として初となる「グリーンテクノロジー学科」を理工学部に新設する。
ここで掲げる「グリーンテクノロジー」とは、「地球環境への影響を最小限にしながら、持続可能な社会の実現を目指す技術」を指す。
「理工学部にグリーンテクノロジー学科 2026年4月誕生!」(創価大学ホームページ)
「グリーンテクノロジー」は、水資源、エネルギー、輸送、建築、農業、製造、廃棄物処理など、およそ社会全般と言い換えていい幅広い分野にわたる。
同時に大学や実験室の内部に留まるのではなく、社会に技術として実装され、あるいはコミュニティの合意形成や起業などまで含んだ分野横断型で再構築された学問分野になるという。
既に近年の日本では生存の危機を思わせるような酷暑だけでなく、「今までに経験したことのない」という形容詞が冠された豪雨が頻発している。
それによる農作物の被害も大きく、また気温上昇が熱中症など直接的なもの以外にも、多くの疾患の悪化を引き起こしていることが指摘されている。
それらの要因が二酸化炭素の排出であることが明らかな以上、ごく近い将来、カーボンフットプリント(二酸化炭素排出量)は社会的に容認されないものとして広く認識されることになろう。
「地球環境を守る技術」の入門書
本書は、この創価大学理工学部のグリーンテクノロジー学科新設を前に、教授・准教授ら16人の執筆陣によって編まれた、いわば「地球環境を守る技術」の入門書と言える。
創価大学理工学部では、科学技術振興機構(JST)と国際協力機構(JICA)による、地球規模の課題解決に向けた日本と発展途上国との共同研究を推進するプログラムSATREPSなど、大規模な共同プロジェクトが進んでいる。
先述したように、グリーンテクノロジーを社会に実装して効果を最大化するためには、ビジネスの視点も欠かせない。
理工学部グリーンテクノロジー学科では、気候変動、低炭素技術、省エネルギー、循環型社会をキーワードとする知識や技術を身につけ、多様な実験をおこなう。同時に卒業後にグローバルな視点で起業を志す学生のため、海外のビジネス習慣や法律などを学ぶ国際ビジネス論も学ぶ。
ヨーロッパではグリーンテクノロジーを学ぶことは既に広くおこなわれている。
欧米では、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Mathematics(数学)を総合的に学ぶSTEM教育は、そのまま国の幹(Stemという単語には幹という意味がある)との認識で、中東・高等教育にさまざまなプログラムが投入されているという。
創価大学理工学部もこのSTEM教育に注力して人材育成に努めてきた。編者の1人である戸田龍樹教授は「あとがき」のなかで、本書の執筆陣の半数以上がその人材育成の成果だと述べている。
さらに近い将来を見据えて、environment(環境)、Robots(ロボット)、Arts(教養・リベラルアーツ)を、STEMと融合させたeSTREAMに向けた環境整備をおこなうとしている。
本書では、気候変動、食料問題、プロテイン・クライシス(タンパク質供給量の不足)、プラスチック問題など、地球が置かれている状況とグリーンテクノロジーの進展を概観しながら、その課題と解決策について探っていく。
日本初の「グリーンテクノロジー学科」を立ち上げた執筆陣が次世代のリーダーたるべき人々に贈る一書である。
「本房 歩」関連記事①:
書評『推理式指導算術と創価教育』――戸田城聖の不朽のベストセラー
書評『歴史と人物を語る(下)』――生命を千倍生きゆけ!
書評『ヒロシマへの旅』――核兵器と中学生の命をめぐる物語
書評『アレクサンドロスの決断』、『革命の若き空』(同時収録)
書評『新装改訂版 随筆 正義の道』――池田門下の〝本当の出発〟のとき
書評『希望の源泉 池田思想⑦』――「政教分離」への誤解を正す好著
書評『ブラボーわが人生4』――心のなかに師匠を抱いて
「池田大作」を知るための書籍・20タイトル(上) まずは会長自身の著作から
「池田大作」を知るための書籍・20タイトル(下) 対談集・評伝・そのほか
書評『創学研究Ⅱ――日蓮大聖人論』――創価学会の日蓮本仏論を考える
書評『公明党はおもしろい』――水谷修が公明党を応援する理由
書評『なぎさだより』――アタシは「負けじ組」の組員だよ
書評『完本 若き日の読書』――書を読め、書に読まれるな!
書評『新版 宗教はだれのものか』――「人間のための宗教」の百年史
「本房 歩」関連記事②:
書評『エモさと報道』――「新聞」をめぐる白熱の議論
書評『人はなぜ争うのか』――戦争の原因と平和への展望
書評『見えない日常』――写真家が遭遇した〝逮捕〟と蘇生の物語
書評『歌集 ゆふすげ』――美智子さま未発表の466首
書評『法華経の風景』――未来へ向けて法華経が持つ可能性
書評『傅益瑶作品集 一茶と芭蕉』――水墨画で描く一茶と芭蕉の世界
書評『もし君が君を信じられなくなっても』――不登校生徒が集まる音楽学校
書評『LGBTのコモン・センス』――私たちの性に関する常識を編み直す
書評『現代台湾クロニクル2014-2023』――台湾の現在地を知れる一書
書評『SDGsな仕事』――「THE INOUE BROTHERS…の軌跡」