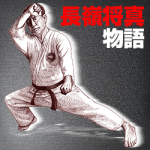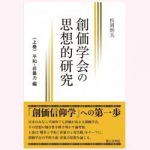2度の経営失敗
1957年8月、長嶺将真はわずか8票差で瀬長亀次郎市長の信任を問う市議会選挙で敗れた。従来は長嶺票に数えられていた「ソシン」とだけ記載した票が10票ほどあって最後まで判定に悩んだというが、運悪くこのときの選挙には同じ名前の候補者がいたことでこの10票すべてが取り消しとなった。そんなハプニングで落選しながらも、それでも長嶺は意気消沈して動きを止めたわけでもなかった。
実際、翌月下旬には、沖縄タイムス紙に沖縄空手道連盟の知花朝信会長と長嶺(副会長)の空手に関する対談記事が上下2回で掲載されている。
さらに10月には長崎市で行われた琉球物産展示会で長嶺が空手演武団の団長を務めるなど、空手に取り組む意気込みは衰えていなかった。 続きを読む