太宰治に『おしゃれ童子』という短篇小説がある。ファッションへの強い執着を持った少年が主人公で、太宰の作品らしい甘い自己愛が描かれている。まだ小学生の主人公が、上着の袖から覗く白いフランネルのシャツが、眩しいくらいに真っ白でなくてはならない、とこだわるところを憶えているのは、実は、僕自身がそういう子供だったからだ。 続きを読む
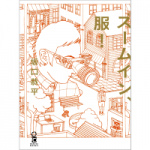
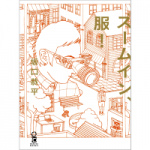
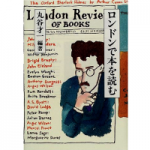
ここでいきなり問題です。僕が生まれて初めて原稿料をもらった仕事は、さて、何でしょう? え? そんなことどうでもいい? 僕にあまり関心がない? (泣きながら)答えは、某新聞の書評です。
あれは確か20代の後半だった。ヘミングウェイとトム・ウルフを担当した名編集者の評伝だったとおもう。知り合った記者が、僕が小説家を志していると分かって、書評をやらないか、と声をかけてくれたのだ。 続きを読む
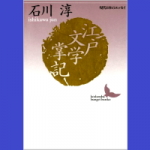
あるとき、僕の小説の特徴のひとつは奇想だと批評家にいわれた。それは本人も自覚していたところなので、なぜそうなったのか考え、子供のころ漫画を読み漁ったとおもいあたった。
漫画には奇想があふれている。アイデアが陳腐であれば読者が満足しない。漫画家は懸命にオリジナルなアイデアを求め、それは奇想のおもむきとなる。僕はそういう漫画を日常的に読み、いつか奇想を思いつくようになった。 続きを読む
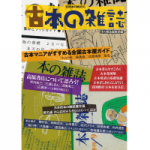
古本屋――それは本好きが最終的に行き着くところ、ある意味で象の墓場のような場所である。
僕の「古本屋」体験を語りたい。このコラムで「町の本屋」を取り上げたとき、僕の「本屋」体験を書いた。家の近くにあるS書房という小さな本屋へ通って、漫画を入り口として文学を読むようになった。S書房の文学の棚が、ほぼそのまま僕の部屋の本棚へ移った。 続きを読む
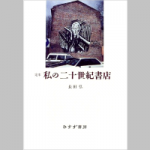
近年になって、だんだん街の小さな書店が減ってきている。多くの在庫を誇る大型書店を探索する愉しみも捨てがたいが、散歩がてら立ち寄ることのできる小さな書店が消えてゆくのはさみしい。
この本の著者・長田弘氏も同じ気持ちだったのではないかとおもう。表題を『私の二十世紀書店』(※リンク先は1999年発売の『定本 私の二十世紀書店』)としたのは、
「私がこれらの本に出会った場所が街の書店においてだったからだ。本の自由というのは、自由な開かれた書店が街にあるということである」
という。この本には、街の書店への愛惜がこめられている。 続きを読む