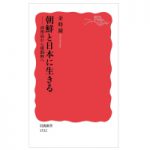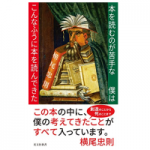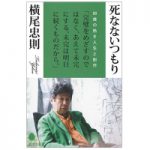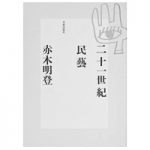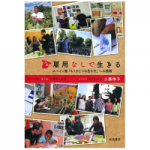子供のころ、実家から少し離れたところに青谷(あおだに)という土地があった。町の人々は、あまり近づこうとしなかった。その土地をめぐる怖い噂もあって、なかへ入ると、容易に出ることのできない、異世界のような印象もあった。
中学に入って、青谷の子供と友達になった。恐る恐る行ってみると、ちょっとした山のなかに、木造の古びた平屋がぽつぽつと並んでいる、静かな土地だった。僕らの住んでいるところと、ほとんど変わらなかった。拍子抜けするほどだった。
そこには朝鮮人と呼ばれる人たちが暮らしていた。僕は、なぜ、彼らが集落をつくっているのか、もっというと、朝鮮人という人々が日本にいるのか、それが分からなかった。 続きを読む