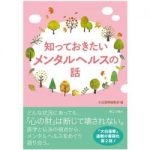「決して焦る必要はありません」
このほど第三文明社から『知っておきたいメンタルヘルスの話』(大白蓮華編集部編)が発刊された。
これは、聖教新聞社発刊の『大白蓮華』に連載された「誌上座談会『福徳長寿の智慧』に学ぶ」(第3回、第4回、第15回~第31回)をもとに加筆・編集し、さらに同誌連載の「希望のカルテ」(2024年7月号~2025年6月号)を、コラムとして加筆・編集したもの。
本書で言う「メンタルヘルス」とは、いわゆる「こころの病気」である。
医療従事者である創価学会ドクター部や創価青年医学者会議のメンバーに加え、回によっては公認心理士、臨床心理士、さらに創価学会の西方青年部長も座談の輪に加わっている。
創価学会の信仰は、科学的知見や医学の立場を軽視しない。むしろ、それらの知見を重視し、適切な対処法や治療法を尊重して、そのうえで仏法者として「生老病死」の現実にどう向き合っていくかを説く。
このことは、本書で取り扱う「こころの病気」に関しても変わらない。本書でも「こころの病気」について、池田大作名誉会長の次のような指導が紹介されている。
長い人生だし、決して焦る必要はありません。専門家に相談して、じっくりと適切な治療を行っていただきたい。
皆、いろいろな状況がある。一律に『こうすればいい』という処方箋はありません。
でも、一点、妙法を持(たも)った皆さんが不幸になることは絶対にないと、私は断言できます。
周りの人は、病気で苦しむ本人を温かく、また長い目で見守りながら、ご家族に真心からの励ましを送っていただきたい。
側 で支えてくださっている方々は大変です。時には工夫して、休息をとっていただきたい。
こころの病を抱えた人を大切にすることは、本当に深い慈悲の境涯を開いていくことです。豊かな人間性の社会を築いていくことです。(以下、引用はすべて本書)
本書の主な構成は、次のようなものになっている。「こころの病気」について、不調を感じた当事者はもとより、家族や周囲の人がどのように受け止め、対処していけばいいのか、座談形式で丁寧に語られている。
序章 「メンタルヘルス」の理解のために
コラム①「こころの病気」は遺伝するのか?
第1章 「こころの病気」と向き合う
第2章 早期発見・初期サインについて
コラム②愛着(アタッチメント)
第3章 受診について――病院選び・医療者との関係など
第4章 診断・治療について
「こころの病気」の種類など
「こころの病気」の治療法など
コラム③依存症
第5章 回復について
第6章 家族・友人のサポートについて
つながりの重要性など
「励まし」とは
コラム④産前・産後のメンタルヘルス
第7章 質問編
①「誤解」を「理解」へ
②予防・早期発見・初期サインなど
③受診・診断・治療など
④回復・休養・復帰など
⑤公的支援など
⑥家族・友人のサポートなど
コラム⑤自己肯定感
終章 「生命の尊厳」が輝く時代へ
「若者の生きづらさ」を考える
ありのままに生きていく
誰もが無限の可能性を持つ存在
誰でもかかる可能性がある
そもそも最近になって急に「こころの病気」が増加したわけではないはずだ。もちろん、現代社会ならではのストレス要因は増えていると思うが、おそらく以前であれば見過ごされてきたものが、きちんと医学的に正しく受け止められてくるようになった面も大きいのだろう。
本書では精神科医から、
「こころの病気」は、生涯を通じて、5人に1人がかかるともいわれ、決して特別な人がなるものではなく、誰にでもかかる可能性があるものといえます。
との解説がされている。
社会一般でも、この「こころの病気」に関しては理解不足から、当事者が不調を感じても、それを〝病気〟だと受け止められない、受診に踏み切れない、周囲に打ち明けられない、周囲も指摘しづらいといった面がある。
こうした「こころの病気」に関する偏見や誤解の要因として、たとえばマスコミなどが「こころの病気」が犯罪の原因になるかのようなセンセーショナルな報道をすることにも、本書は警鐘を鳴らしている。
実際には、「こころの病気」を抱えた人が加害者になることより、むしろ犯罪被害者になることのほうが多いと、本書でも指摘されている。
「こころの病気」はさまざまな要因が複合的に影響しているもので、「心が弱いから」とか、特別な人がなるとか、一概に一生治らないとかいうものではない。
創価学会の機関誌である『大白蓮華』がこの連載をしたのも、とりわけ信仰を持った人の場合、「こころの病気」になったのは〝信心が弱いから〟等と、要因を信仰に結び付けて受け止めることがないようにという配慮からだろう。
信仰は魔術ではない。むしろ、「生老病死」は誰もが逃れられないものであり、だからこそ、その変化と賢明に向き合っていける正しい信仰が必要なのだ。
池田先生は、このように語られています。
『生老病死』だから、だれでも病気になる場合がある。調子がすぐれない場合もある。それを上手に乗り越えていくことである。たとえ病気になっても、『変毒為薬』し、早めに治していく――信心による、賢明な〝生命の操縦〟をお願いしたい。体の具合が悪くなったら、すぐ医師に相談するなり、よく診断してもらうことである。
「依存症」と「ゲーム障害」
収録された「コラム」のなかには、たとえば依存症を取り上げたものもある。薬物やアルコールといった物質への依存症だけでなく、現代特有の新しいものとしてスマホやパソコンでゲーム・SNS・ショート動画の視聴などをやめたくてもやめられなくなる「ネット依存」が深刻化し、専門外来も設立されているという。
また「ゲーム障害」は既にWHO(世界保健機関)の最新診断基準「ICD-11」(国際疾病分類第11版)で、新しい病気として追加されているとのこと。
一方、小児科専門医の記した「コラム」では、愛着(アタッチメント)の形成に関する興味深い記述があった。
愛着の形成において特に重要なのは乳幼児期(0~5歳)だが、近年は共働きやさまざまな事情によって、子どもとかかわる時間が限定されてしまう場合もあることだろう。
しかし重要なのは単なる時間の「長さ」ではなく「質」だという研究もあるそうだ。本書では具体例として「子どもの行動を具体的に称賛する」「子どもの言葉を繰り返す」「子どものまねをする」「子どもの行動を説明する」「親自身が楽しむ」「命令しない」「批判しない」「質問しない(子どもが会話をリードする)」が挙げられている。
さらに、乳児期・幼児期・学童期・青年期それぞれの時期のかかわり方の参考として、
①乳児はしっかり肌を離すな
②幼児は肌を離せ、手を離すな
③少年は手を離せ、目を離すな
④青年は目を離せ、心を離すな
という「子育て四訓」も紹介されている。
「防災グッズ」と同じように
なお、本書はとくに創価学会員が連載の読者の中心であったことから、「こころの病気」のときに勤行・唱題をどうすればいいか、会合に参加すべきかどうかといった問題にも、池田名誉会長の指導を引きながら専門医たちが論じ合っている。
また、「こころの病気」の人に対して〝励ましてはいけない〟と思い込んでいる人が多いことにも言及。相手に不必要なストレスを与えないための配慮が大事なのであって、〝かかわってはいけない〟というわけではないと専門医の立場から明言している。
一概に「こころの病気」といっても、よく眠れないという睡眠障害もあれば、パニック障害、うつ病、摂食障害、統合失調症など、社会生活を送るうえで当事者が大きな困難を抱えるものもあるだろう。
いずれにしても、自分自身や家族、近しい友人や仲間、職場の同僚や部下など、誰がいつ発症してもおかしくないものなのだ。
その意味で本書は、正しい知識を身につけておくことで、いち早く異変を察知し、また誤った対処をしないための入門書として〝常備〟しておいていいのではないかと思った。
人は自分で異変を感じても、むしろ家族など近しい人には「心配させたくない」という心理が働いて伝えにくい場合が多い。異変を感じてからでは、関連書籍を買うことをためらう人もいるだろう。
本書は装丁もタイトルも、毒々しいものにならないよう、よく配慮されている。防災グッズと同じで、いざという時は人生に必ず来るというくらいの気構えで、わが家の書棚に置いておくべき本ではないか。
「本房 歩」関連記事①:
書評『地球を救うグリーンテクノロジー』―創価大学理工学部の挑戦
書評『推理式指導算術と創価教育』――戸田城聖の不朽のベストセラー
書評『歴史と人物を語る(下)』――生命を千倍生きゆけ!
書評『ヒロシマへの旅』――核兵器と中学生の命をめぐる物語
書評『アレクサンドロスの決断』、『革命の若き空』(同時収録)
書評『新装改訂版 随筆 正義の道』――池田門下の〝本当の出発〟のとき
書評『希望の源泉 池田思想⑦』――「政教分離」への誤解を正す好著
書評『ブラボーわが人生4』――心のなかに師匠を抱いて
「池田大作」を知るための書籍・20タイトル(上) まずは会長自身の著作から
「池田大作」を知るための書籍・20タイトル(下) 対談集・評伝・そのほか
書評『創学研究Ⅱ――日蓮大聖人論』――創価学会の日蓮本仏論を考える
書評『公明党はおもしろい』――水谷修が公明党を応援する理由
書評『なぎさだより』――アタシは「負けじ組」の組員だよ
書評『完本 若き日の読書』――書を読め、書に読まれるな!
書評『新版 宗教はだれのものか』――「人間のための宗教」の百年史
「本房 歩」関連記事②:
書評『エモさと報道』――「新聞」をめぐる白熱の議論
書評『人はなぜ争うのか』――戦争の原因と平和への展望
書評『見えない日常』――写真家が遭遇した〝逮捕〟と蘇生の物語
書評『歌集 ゆふすげ』――美智子さま未発表の466首
書評『法華経の風景』――未来へ向けて法華経が持つ可能性
書評『傅益瑶作品集 一茶と芭蕉』――水墨画で描く一茶と芭蕉の世界
書評『もし君が君を信じられなくなっても』――不登校生徒が集まる音楽学校
書評『LGBTのコモン・センス』――私たちの性に関する常識を編み直す
書評『現代台湾クロニクル2014-2023』――台湾の現在地を知れる一書
書評『SDGsな仕事』――「THE INOUE BROTHERS…の軌跡」