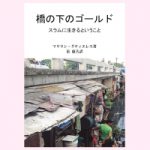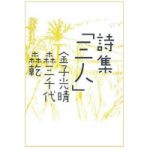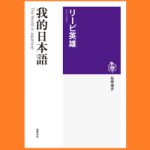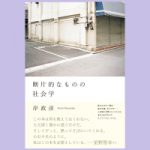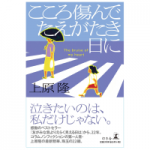フィリピンのマニラにある橋の下で、著者の「私」はメルセディータと出会う。彼女はそこに家を構えて暮らしていた。橋の下で暮らしているのは100家族ほど。電気は違法に引いていたが、電力会社に止められ、ろうそくの炎が唯一の家の中の灯だ。
もともと「私」は教師をしながら、貧困層の人々を支援するボランティアに携わっていた。あるときからフルタイムのボランティアになった。メルセディータと出会って、彼女の半生を記録し始める。
メルセディータ・ビリャル・ディアス=メンデスは、1965年に生まれた。両親は農場で働いていた。6人きょうだいの末っ子だった。貧しい暮らしで、おもちゃがひとつもなかった。 続きを読む