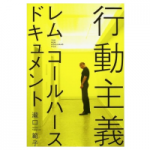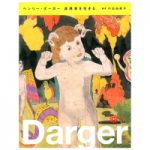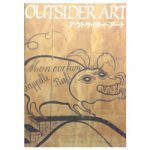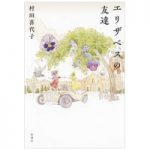子供のころ建築家に憧れた。伯父が建設会社を営んでいた影響もあったかも知れない。何もないところに一から物を築き上げていく仕事が魅力的に思えた。ところが僕には色弱という視覚障害があって、ある種類の色の区別がつかない。
建築家は、電気の配線図などを見ることができなくてはならず、そのために色の区別は必要で、色弱には務まらない。同じように、手旗信号などの色を見分けることができなくてはならない船員にもなれない。実は、船員も憧れの職業だった。
建築家にも、船員にも、なれない。これは、けっこうショックだった。母に文句をいった憶えがある。すると、「おまえはテレビ・ドラマの見過ぎだ。産んでもらっただけありがたいと思え」と鼻で笑われた。なんとハードボイルドな母親か。 続きを読む