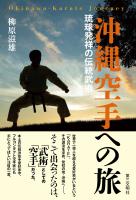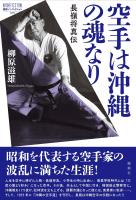「裏分解」の極意
久場道場(沖縄市)では、日頃の稽古では自由組手を行わない。ただし「昇段審査」では組手を義務づけるという。沖縄の剛柔流や上地流の昇段審査ではさして珍しい光景ではないそうだ。
審査のときにいきなりやります。そこで見るのは、戦える心があるかどうか。いざというときに実際に動けるようにするためには、日頃の心構えが重要になります。今までのところ、(組手から)逃げた人はいません。(久場良男館長)

稽古の後半に2回行った型サイファ
沖縄空手の特徴は、基本と型を中心に行うことと語る。自由組手中心の稽古をつづけると、若いときはそれでもよいが、どうしても限界が見えてくる。
「沖縄伝統の鍛え方はけっして間違ってはいないと思います」
30歳を超えたら、自由組手だけでは難しいと繰り返す。ルールありきの組手に慣れてしまうと、ルールのもとで反射的に手足が出てしまい、相手を怪我させてしまう恐れが出てくる。実戦では、あくまで相手の突き、蹴りを封じることを主眼とするとの考え方がある。

オリジナル型「鶴破」(カクハ)の後半場面
古い時代の柔術は、「投げ」に入るために「突き」や「蹴り」が必要でしたが、空手はその逆で、「突き」や「蹴り」で倒せないから、「投げ」に入る。自由組手の最中に、私は逆をとる(逆技をかける)ことがありますが、型を少しアレンジした稽古をすると、すぐにそこに入れるようになります。空手の受け技の変化が、実は空手における投げ技といえます。受けは場合によっては、投げ、押さえ、取りにもなりますよと指導しています。
久場館長の空手は多くのDVDなどで武術性を知られてきた。そこでは「裏分解」という言葉が頻出する。通常の「分解」とどう違うのか尋ねてみた。
「裏分解」は通常の「分解」とは別の意味です。昔の先生は、型のそれぞれの動きに関し、まずは一つの分解(使用法)を教える。さらに相手の技術が上がってくると「本当はこうだよ」と、主に口伝(くでん)で伝えたのが「裏分解」です。本来の沖縄剛柔流でいうところの「解裁」(カイサイ)が、本土ではわかりにくいという指摘がありまして、私は『裏分解』という言葉で説明しています。「解裁」は沖縄剛柔流のみで通じる言葉で、本土の剛柔流では通用しないものです。
型の解釈の違いは、剛柔流内で伝わってきた伝播過程にも理由があると説明する。
極真型を批評する

「鶴破」の下突き
一人の達人から教えを受ける場合、師匠が脂ののり切った壮年期に習った弟子と、晩年の円熟期に教えを請うた弟子とでは型の動作や解釈に違いが生じるのは、どの流派でも見られる普遍的な現象だ。宮城長順の弟子たちにも同じことがいえる。

逆技をマンツーマンで稽古する
比較的早い段階で宮城に師事した八木明徳系と、最晩年に師事した宮里栄一系で同じ型でもだいぶ違うのはそうした理由による。だが同じ師匠から教わった内容である以上、どちらがよくてどちらがダメという判定は下しがたい。その点を久場はこう説明する。
東恩納(寛量)先生の影響が大きい時代、宮城長順先生が中国に行かれた時代など、その時代時代によって受けた技術が微妙に異なることは致し方ないことです。どの時代の動きが正しいかと聞かれることがありますが、型の動作が多少違っていたとしても、突き・蹴りの基本が変わるわけではありません。昔の先生は、まず先に体幹部をつくり、手足は後からという考え方がありました。まずはサンチンで体の芯をしっかり作っていくことが基本です。
関係者には知られたことだが、本土の極真空手は、松濤館空手と剛柔流空手を折衷した稽古体系で、主に剛柔流の影響を強く受けている。極真空手で行っている型サイファとセイエンチンを見たことがあるという久場館長に感想を尋ねてみた。館長は一瞬言いづらそうな表情を浮かべたが、こちらが重ねて尋ねると次のように回答した。
申し訳ないですが、本来の剛柔流から見るとかなり無理のある体の使い方をしています。セイエンチンですが、まずは立ち方で体幹部を作らないといけないのですが、あれほど足を広げてしまうと体幹部を作ることができません。あのやり方だったら(武術的には)やらないほうがいいと思うくらいです。サイファの立ち方も完全に違っています。またサンチンの呼吸法はすべて吐く呼吸になっていて、吸う動作がありません。呼吸法もまったくといっていいほど異なっています。あそこまで違うと、むしろ極真流の型といったほうが好ましい。原理をわからないまま型をやっているという印象です。
本土のフルコンタクト出身の記者としては耳の痛い言葉である。何かの参考になればと思い、敢えてご紹介させていただく。(文中敬称略)

稽古に参加した皆さん。右から2人目が久場館長
※沖縄現地の空手道場を、武術的要素を加味して随時紹介していきます。
シリーズ【沖縄伝統空手のいま 道場拝見】:
①沖縄空手の名門道場 究道館(小林流)〈上〉 〈下〉
②戦い続ける実践者 沖拳会(沖縄拳法)〈上〉 〈中〉 〈下〉
③沖縄空手の名門道場 明武舘(剛柔流)〈上〉 〈下〉
④上地流宗家道場 普天間修武館(上地流)
⑤喜舎場塾田島道場(松林流)〈上〉 〈中〉 〈下〉
⑥上地流空手道拳優会本部(上地流)〈上〉 〈下〉
⑦沖縄空手道拳法会拳武館(剛柔流)〈上〉 〈下〉
【WEB連載終了】沖縄伝統空手のいま~世界に飛翔したカラテの源流:
[シリーズ一覧]を表示する
WEB第三文明で連載された「沖縄伝統空手のいま~世界に飛翔したカラテの源流」が書籍化!
『沖縄空手への旅──琉球発祥の伝統武術』
柳原滋雄 著定価:1,760円(税込)
2020年9月14日発売
第三文明社
【WEB連載終了】長嶺将真物語~沖縄空手の興亡~
[シリーズ一覧]を表示する
WEB第三文明で連載された「長嶺将真物語~沖縄空手の興亡」が書籍化!
『空手は沖縄の魂なり――長嶺将真伝』
柳原滋雄 著定価:1,980円(税込)
2021年10月28日発売
論創社(論創ノンフィクション 015)