高市首相は1月23日、衆議院の解散を決定し、1月27日公示、2月8日投開票となる総選挙がいよいよ始まります。
2月1日発売『第三文明』3月号から連載開始となる佐藤優氏の「人類の羅針盤~池田思想に迫る」連載「第1回」の冒頭部分、新党「中道改革連合」に関する発言部分を先行配信します。 続きを読む


高市首相は1月23日、衆議院の解散を決定し、1月27日公示、2月8日投開票となる総選挙がいよいよ始まります。
2月1日発売『第三文明』3月号から連載開始となる佐藤優氏の「人類の羅針盤~池田思想に迫る」連載「第1回」の冒頭部分、新党「中道改革連合」に関する発言部分を先行配信します。 続きを読む

高市首相は1月23日、衆議院の解散を決定し、1月27日公示-2月8日投開票となる総選挙が本格的に開始しました。
2月1日発売『第三文明』3月号掲載の松田明氏の寄稿「中道改革連合結党の真意とは」を先行配信します。 続きを読む

(2)別釈③
④「止観を修するを明かす」(2)
「煩悩境」の段の別釈は四段に分かれているが、その第四段は「止観を修す」であり、この段はさらに「正しく十乗を明かす」と「異名を会す」に分かれる。今回は「異名を会す」段について紹介する。この段はさらに「煩悩即涅槃の三十六句」、「諸法般若の三十六句」、「四身の三十六句」の三段に分かれる。ここでは、「煩悩即涅槃の三十六句」についてのみ簡潔に紹介する。 続きを読む

1月19日夕刻、高市早苗首相は官邸で記者会見を開き、1月23日に衆議院を解散することを発表した。1月27日公示、2月8日が投開票。解散から16日後の選挙は「戦後最短」である。
通常国会の冒頭で解散するのは、通常国会が1月開会となった1992年以来で初めて。それ以前にさかのぼっても1966年12月に冒頭解散した佐藤栄作内閣以来60年ぶりとなる。
なぜ歴代政権は1月解散を避けてきたのか。理由はさまざまある。
なによりも、国会としては新年度の予算編成がある。これが成立しないと国民への施策も実施できないし、全国の各自治体も対応した予算編成や事業計画が年度内に立てられない。本来、年度内の予算成立は内閣の最大の責務なのだ。 続きを読む
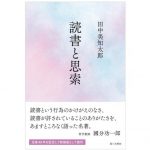
田中美知太郎は、20世紀が始まった次の年、1902年(明治35年)の元旦に生まれ、昭和が60年の節目を迎えた1985年の暮れに没した。
戦後日本におけるギリシア哲学の権威であり、とりわけソクラテスとプラトンの研究では、『ソクラテスの弁明』(1950年/岩波ギリシア・ラテン原典叢書)、『ソクラテス』(1957年/岩波書店)、『プラトン』全4巻(1979~1984年/岩波書店)など、記念碑的な著作を残している。
著作の大半は西洋古典学・哲学に関するものであるが、社会批評や政治批評など領域は幅広く、没後に刊行された『田中美知太郎全集』(筑摩書房)は全26巻におよぶ。 続きを読む