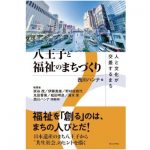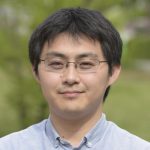住民を巻き込んだまちづくり
東京都で唯一の中核都市である八王子市は、かつては甲州街道最大の宿場町「八王子宿」として栄え、近代の初めには関東各地で生産された絹糸や絹織物などを横浜に移送する流通拠点として重要な位置を占めた。
また、この半世紀あまりは大学のキャンパス移転や新設開学が続き、21の大学・短期大学・高専を擁して、約10万人の学生が集う学園都市としても知られている。
平成に入った頃から、住宅地の郊外への進展、それに伴う大型ショッピング施設の郊外での開業など郊外地域の発展により、八王子駅周辺の大型商業施設が相次いで閉店するなど、中心部の「空洞化」が問題になった。
しかし、その後の新しい都市計画によって中心市街地に若いファミリー層が暮らす集合住宅が増え、商業施設も充実して、現在では「居住者向けの街」として住民を巻き込んだ中心市街地の活性化が進んでいる。(「八王子市中心市街地活性化基本計画」参照) 続きを読む