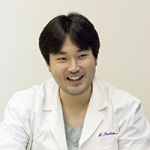25年に及ぶホームレス支援の活動から見えた本当の絆の在り方とは何か。「助けて」と言える社会を見据え、その基盤となる思想を語る。
「絆は傷を含む」という覚悟に立つ
ホームレス支援や困窮者支援の活動を通じて感じることは、「努力が足りない」「怠けている」といった「助けられる側」への自己責任論とともに、「助ける側」に向けても「助けるなら最後まで自分ひとりの責任でやりなさい」という自己責任論があることです。このような自己責任論がある中では、助けることのハードルが上がり、おいそれと人助けなんてできなくなってしまいます。 続きを読む