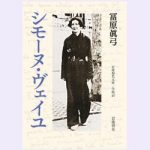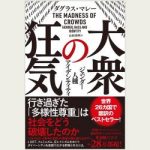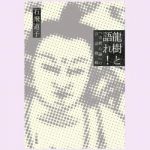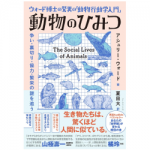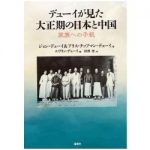革命幻想を打ち破り、精神の変革を志向する
戦争と革命に揺れ、全体主義の台頭と大量虐殺を招いた20世紀。シモーヌ・ヴェイユ(1909年-1943年)はこの暗い時代に誰よりも真剣に向き合い、独創的な哲学を築き上げたことで知られる。徹底した行動と冷静な知性に裏打ちされたその思想は、現代でも大きな影響をもつ。本書は彼女の生きた時代状況と思索の過程を丹念に辿り、その哲学の全体像に迫った「思想の伝記」である。
三四歳で亡くなるまでのほぼ二〇年間に書かれたテクストを通読すると、ヴェイユの思想に根本的な変化はみられない。あるのは熟考と経験のもたらす深化であり重層化である。(本書9ページ)
ヴェイユはフランスのユダヤ人家庭に生まれ、高校では哲学者・アランの薫陶を受けた。エリート養成機関である高等師範学校を卒業し、教育者となった。
彼女が社会に踏み出した当時、ロシア革命や経済不況の影響を受け、社会主義革命への期待がかつてないほど高まりをみせた時代であった。
「正しい思考は正しい行動をみちびき、欺瞞と妥協にみちた人生は生きるにあたいしない」という師匠であるアランの教えを実践すべく、高校教師として働きながら社会主義運動にも真剣に取り組む。その過程でソ連が全体主義体制であることを見抜き、損得ずくの主導権争いに明け暮れる労働組合の惨状を知った。 続きを読む