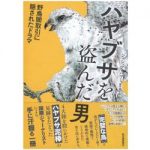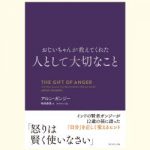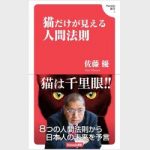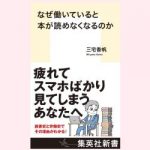鷹狩の歴史と文化
著者のジョシュア・ハマーは、『アルカイダから古文書を守った図書館員』などで知られるジャーナリストである。本書は、イギリスの野生生物犯罪専門の捜査官アンディ・マクウィリアムと五大陸を股にかけたな猛禽類の密猟者ジェフリー・レンドラムの2人を中心にとりあげ、世界的な野鳥の闇市場の実態に迫ったノンフィクションである。
2017年のとある日、何気なく目にした「ハヤブサの卵泥棒」の記事に好奇心をいだいたことから、著者は野鳥の闇市場に興味をもち、関係人物に取材を始める。
取材を通じて明らかになったのは、闇市場の規模は特定の愛好家を対象とした小さなものではなく、巨額の金銭が飛び交う、世界的なネットワークを形成していたということである。
国境を越えて多額の金銭が飛びかう世界には、当然ながら闇がある。猛禽類のブラックマーケットが膨張することになるのだ。飼育下繁殖の鳥よりも、野生状態で捕獲された鳥のほうが強いと妄信するコレクターと、カネになるなら法を犯すこともいとわない輩が闇市場を支える。(本書57ページ)