近代人の典型的な生き方は、学校で学んで、会社で働くことだ。しかし、近年になって学び方と働き方には選択肢が増えてきた。その気になれば、学校や会社という組織に属さないで、学び、働くこともできる。エリック・ホッファーは、そういう生き方の先駆的な存在だったのかもしれない。 続きを読む
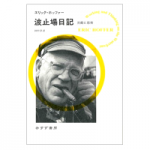
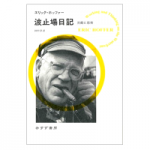
近代人の典型的な生き方は、学校で学んで、会社で働くことだ。しかし、近年になって学び方と働き方には選択肢が増えてきた。その気になれば、学校や会社という組織に属さないで、学び、働くこともできる。エリック・ホッファーは、そういう生き方の先駆的な存在だったのかもしれない。 続きを読む

僕はお菓子が好きで、かつて食後には必ずデザートにお菓子を食べ、危うくメタボになりかけた。そこで、1週間のうち、数日間だけお菓子の解禁日を決めて、その日を「お菓子祭り」と称することにした。
辛いもの、甘いもの、数種類買って来て、全部の袋を開けて少しずつ味見する。妻には、ひとつずつ食べれば、といわれるのだが、やめられない。だって、いちばん愉しい瞬間なのだから。 続きを読む
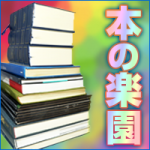
僕とラテンアメリカ文学の出会いを順序立てて語ると、世界文学と日本文学の在り方を交えた長い話になるので、読者を退屈させるわけにもいかないから、要所だけをしるすことにする。
20歳前後の頃のことだ。ふらっと入った古書店で何気なく手にした小説が、ガルシア・マルケスの『百年の孤独』(1967)だった。これはおもしろかった。 続きを読む
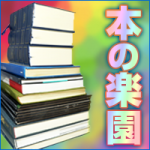
石川淳がエッセーで書いているのだけれど、かつて中国の文人・黄山谷が、士大夫(知識階級)は3日読書をしないと、顔が醜くなり、言葉にも味わいがなくなると言っているらしい。 続きを読む