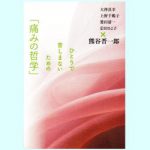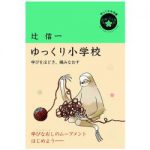朝日カルチャーセンターでの対談をまとめた本というので、読みやすいだろうとおもって手に取った。確かに読みやすい。しかし分かりやすくは、ない。この本をきちんと紹介するには、この本についての本を、もう1冊書かなければならない。
ホストは、熊谷晋一郎。生まれたときの後遺症で、脳性麻痺の障害を持つ。車椅子での生活を送りながら、東大の医学部を出て、医師になった。「当事者研究」の研究、実践もしている。
「当事者研究」とは、医療などの専門家と病をかかえた患者が共同研究者となって、当事者が、「知の消費者」から「知の生産者」になり、知の領域にも関わっていくことだ。おもに精神病や依存症の自助グループから始まった。 続きを読む