市民社会の努力を称える
国連創設75周年の「国連デー」である10月24日、グテーレス事務総長は報道官声明を発表し、「核兵器禁止条約」の批准国が発効に必要な50に達したことを明らかにした。
このなかで事務総長は、核兵器廃絶のため批准した国々に敬意を表し、条約の交渉の促進や批准においてきわめて大きな役割を果たしてきた市民社会の努力を讃えた。また、「条約発効は、これを強く求めてきた核爆発と核実験の生存者たちに報いるもの」と語った。 続きを読む

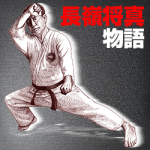
1969年1月、長嶺将真は最初の海外指導に出かけた。
すでに5年ほど前、第1号となる海外指導員をアメリカのニューヨークに送り出し、「沖縄松林流USA本部」の名称で組織化していた。以来、沖縄から次々と指導員を派遣していた。
1967年には長男の高兆(たかよし)をオハイオ州へ送り出した。現在、松林流の海外支部の多くが北米・南米に集中するのは、こうした開拓の成果といえる。
長嶺は最初の海外指導に70日ほどかけているが、生涯において4度の海外指導を敢行している。 続きを読む

日本経済団体連合会(経団連)は10月13日に「主要政党の政策評価2020」を発表した。
ここでは、
自由民主党を中心とする与党は、緊急事態宣言の発令等により国内での新型コロナウイルスの爆発的拡大を防ぐとともに、二次にわたる補正予算を成立させるなどした上で、感染症対策と経済回復の両立に取り組んでいる。さらに、ポストコロナ時代の新しい経済社会を見据え、デジタルトランスフォーメーション(DX)、テレワーク等の新しい働き方の定着等を推進しており、高く評価できる。
としたうえで、公明党の取り組み実績のひとつとして、
治療薬・ワクチンの研究開発の加速、あらゆる事態に備えた医療提供体制の整備
を挙げた。 続きを読む
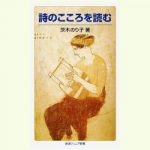
某大手書店の偉い人と会食をしたとき、「文学は売れません」と断言された。分かってはいたが、読者にいちばん近い現場の人に言われて、あらためてがっかりした。しかしその人は続けて、「ところが茨木のり子は売れるんです」と言う。
茨木のり子は詩人だ。僕も名前は知っているし、何篇かの詩は読んだ記憶があった。ただ、日本において、詩は、小説よりも、さらに売れないジャンルである。海外では、詩が売れる国もあると聞く。
しかし、日本では、詩が売れる、と聞いたことはない。僕は、茨木のり子に関心を持った(そりゃそうでしょう)。そして、家に帰って書庫にあった彼女の本を探した。『詩のこころを読む』という本があった。 続きを読む

この記事は『新版 宗教はだれのものか 三代会長が開いた世界宗教への道』(青山樹人著/鳳書院)の発売にともない「非公開」となりました。
新たに「三代会長が開いた世界宗教への道(全5回)」が「公開」となります。
「三代会長が開いた世界宗教への道」(全5回):
第1回 日蓮仏法の精神を受け継ぐ(4月26日公開)
第2回 嵐のなかで世界への対話を開始(5月2日公開)
第3回 第1次宗門事件の謀略(5月5日公開)
第4回 法主が主導した第2次宗門事件(5月7日公開)
第5回 世界宗教へと飛翔する創価学会(5月9日公開)
WEB第三文明の連載が書籍化!
『新版 宗教はだれのものか 三代会長が開いた世界宗教への道』
青山樹人価格 1,320円/鳳書院/2022年5月2日発売
→Amazon
→セブンnet
第三文明社 公式ページ