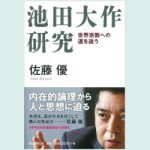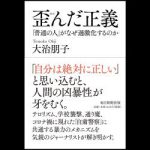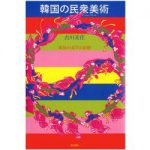「世界宗教化」が進む創価学会
週刊誌『AERA』の43回にわたる連載に加筆して上梓されたもの。厚さ4センチ、全590ページ近い大部である。
著者の佐藤優氏は周知のとおり元外務省主任分析官で、同志社大学大学院神学研究科を修了したプロテスタントの作家だ。
1930年に創価教育学会として誕生した創価学会は、本年(2020年)11月18日で創立90周年を迎えた。
単に日本最大の宗教運動であるのみならず、その支援する公明党は20年にわたって日本の政権の一翼を担っている。
一方で、SGI(創価学会インタナショナル)は192カ国・地域に広がっている。ヨーロッパでは最大の仏教教団であり、たとえばイタリアSGIはカトリックの本場イタリアでも仏教教団として唯一、国家の公認宗教12宗派の1つとして認められている。
創価学会は、すでに「世界宗教化」をはじめているのである。
1世紀に満たない時間で、なぜこれほど社会に影響力をもたらす教団に発展できたのか。 続きを読む