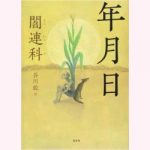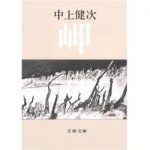《1》裾野市の保育園で起きた事件
静岡県東部の富士山のふもとに位置し、四季ごとに山の変化を楽しめる裾野市。昨今はトヨタ自動車が自動運転を可能にする近未来型都市の造成を進めている注目の街だ。
その裾野市で、「まさかこんなことが‥‥‥」と思わず絶句してしまう衝撃的な事件が起きていた。それは市内の保育園でのこと。1歳児のクラスを受け持つ保育士3人が複数の園児に16もの不適切な虐待行為をしていたという事件で、昨年12月4日に当時保育士だった3人が逮捕された。
明らかになっている園児への不適切な虐待行為とは、暴言を吐く、カッターナイフを見せ脅す、脚をつかんで宙刷りにする、頭をバインダーでたたいて泣かすなどで、およそ口に出すのも憚られるものばかりだ。6月以降、逮捕された3人の虐待行為が目撃されるなどし、職員間で話題になっていたという。
子どもの安全が保障されなければならない場所である保育園で、これらの信じられない行為が行われていた。大変にショックな事件であり、小さな子どもの心への影響も心配だ。すでに、県や市においては当該保育園に対して特別指導監査を行っており、厳正に対処してもらいたい。 続きを読む