「ストレス社会」と呼ばれる現代社会。職場でのストレス原因は、それぞれが持つ〝思考のクセ〟にあると木村英一氏は指摘する。
「ズレ」は当たり前という前提に立つ
何事も問題に直面したとき、その原因を知ることが問題解決への近道になります。では職場におけるストレスの原因とは何でしょうか。一見すると嫌な仕事、嫌な上司、嫌な顧客などがストレスの原因だと考えがちですが、実はそうではありません。 続きを読む

「ストレス社会」と呼ばれる現代社会。職場でのストレス原因は、それぞれが持つ〝思考のクセ〟にあると木村英一氏は指摘する。
何事も問題に直面したとき、その原因を知ることが問題解決への近道になります。では職場におけるストレスの原因とは何でしょうか。一見すると嫌な仕事、嫌な上司、嫌な顧客などがストレスの原因だと考えがちですが、実はそうではありません。 続きを読む

貧困や雇用の問題など時代の変化に不安を覚える若者は多い。一方だからこそ、「しっかり年金の保険料を納めていくべき」と考える人がいる。行政経験を生かし、実践的な教育を行っている増田雅暢氏に〝年金の今〟を聞いた。
65歳以上の高齢者人口が3000万人を突破し、今ほど年金制度に対する国民的関心の高い時代はないと思います。その一方で、年金の仕組みが国民に正しく理解されていないために、「将来、年金制度がなくなってしまうのではないか」といった破綻論が世の中にはびこっています。
その最たるものが「未納率」の問題です。 続きを読む

すでに始まった人口減少社会をどう捉えていけばよいのか。日本の未来に向けての新たな視点を語る。
日本の人口は江戸時代後半、3000万人強でフラットな推移をしていました。それが明治以降、急激に人口が増加し、急勾配のまま伸び続けていきました。そして2004年に1億2784万人に達し、そのピークを迎えます。 続きを読む

「自分は親と同じくらいの生活を送れたらそれでいい」という20代の皆さんに知ってもらいたいことがあります。内閣府などの推計によれば、現在の60代は年金や健康保険料など、支払ったお金が約4000万円もプラスになって戻ってくるのに対して、今の20代は支払ったお金がプラスになるどころか、逆に給付される金額が1000万円近くも少なくなることが明らかになっています。つまり、今の20代は自分たちの親世代と比べてマイナス5000万円近いハンディキャップを背負っていて、親と同じような生活は保てそうにないのです。 続きを読む
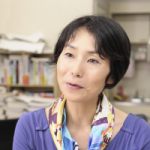
「カード」「保険」「住宅」――20代、30代のライフ・プランニングを考える
若い方からお金に関する相談を受けるとき、私はお金の価値をポジティブに認めることの大切さをお話ししています。世の中にはお金はなんとなく汚いものであり、お金に興味を抱くことが、何かはしたないことであるかのようなイメージがあります。しかしお金は、私たちが商品やサービスという「価値」を社会に提供することで得られた正当な対価です。つまり「たくさんお金を稼ぐ人」は、世の中にたくさんの価値を創造し、大きな社会貢献をしていると考えることもできるのです。 続きを読む