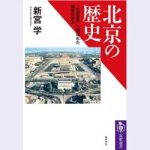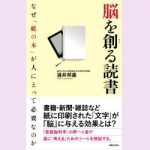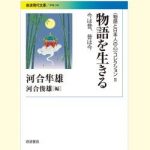第30回 方便①
[1]二十五方便
今回は十広の第六「方便」について考察する。この方便とは、第七章の正修止観で説示される十境十乗の観法の用意、準備条件を意味する。具体的な内容としては、具五縁(持戒清浄・衣食具足・閑居静処・息諸縁務・得善知識)、呵五欲(色・声・香・昧・触の五種の対境に対する欲望を五欲といい、これを呵責すること)、棄五蓋(貪欲・瞋恚・睡眠・掉悔・疑の五種の煩悩を捨てること)、調五事(食・眠・身・息・心の五事を適度に調整すること)、行五法(欲・精進・念・巧慧・一心の五法を実行すること)の、一項目五ヶ条からなる五項目が説かれる。つまり、合計すると、二十五ヶ条が説かれている。
これを二十五方便ということもある(※1)が、天台智顗(ちぎ)の最初期の著作である『釈禅波羅蜜次第法門』(『次第禅門』、『禅門修証』ともいう)巻第二にも説かれており(大正46、483下~491中を参照)、さらにまた、『天台小止観』(※2)にも説かれている。『摩訶止観』の二十五方便の叙述においても、その詳しい説明を『釈禅波羅蜜次第法門』に譲っている場合がある。したがって、この二十五方便の思想は、智顗の少壮の時期にすでに確立され、その後晩年にいたるまで一貫して変わることがなかった基本的かつ重要な思想であったと評せよう。 続きを読む