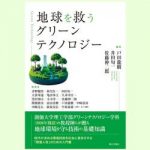半数近くが「自公」基盤の枠組み望む
自民党総裁選挙が目前の10月4日に迫っている。現状では、衆参ともに野党が多数とはいえ、野党の統一候補を首班指名するとは思えないので、おそらく自民党の新総裁がそのまま次の内閣総理大臣に指名されることになる。
ただ、少数与党のままでは安定した政権が作れない。それぞれの総裁選候補者も、表現の濃淡はありつつ異口同音に新たな連立拡大の可能性に言及している。誰が新総理になっても、おそらくいずれかのタイミングで自公にプラスするかたちで、野党を連立政権に迎える公算が強いというのが衆目の一致するところだろう。
FNNが9月20日と21日に実施した世論調査(「FNNプライムオンライン」9月22日)では、今後期待する政権の枠組みについて「自公に野党の一部が加わった政権」と答えた人が46.9%に達した。多くの国民が現在の「自民党+公明党」の枠組みの政権担当能力を、やはり基本的には信頼していることがうかがえる。
一方で、なぜ政権の枠組みにこれほどまで公明党が必要不可欠とされるのか理解できず、不審に思ったり不満に感じたりしている人もいるのではないか。
折しもこのほど、評論家の八幡和郎(やわた・かずお)氏が『検証 令和の創価学会』(小学館)という著作を出した。タイトルには「創価学会」と付いているが、読んでみて、むしろこの本は「公明党」を〝客観的に〟理解するためにこそ適しているかもしれないと思った。 続きを読む