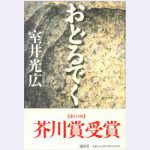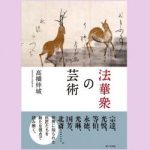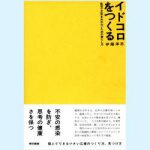読み進めるのが難儀な前衛的作品
室井光広(むろい・みつひろ)著/第111回芥川賞受賞作(1994年上半期)
日本語をロシア文字で表音化した日記
第111回の芥川賞はW受賞だった。前回取り上げた笙野頼子の「タイムスリップ・コンビナート」と、今回取り上げる室井光広の「おどるでく」だ。『群像』(1994年4号)に掲載された作品で、枚数は約119枚。受賞時の年齢は39歳。
この作品を語る上では、作者の経歴を知っておいた方ほうがいい。1955年に福島県南会津郡で生まれ、慶応大学卒業後に大学図書館に勤務。予備校講師などを経て創作を開始しているが、当初その才覚を発揮したのは小説ではなく評論だった。1985年には、群像新人文学賞と早稲田文学新人賞のいずれも評論部門で候補となっており、1988年には、「零の力――J.L.ボルヘスをめぐる断章」で、群像新人文学賞「評論部門」を受賞。そして、その12年後に芥川賞受賞を果たしている。
「おどるでく」は、とにかくわかりづらい。最後まで読み進むのに難儀した。これはわたしがアホだからかとも思ったが、他のさまざまな媒体のレビューを見ても、みなさん相当読むのに苦労している様子が伺える。 続きを読む