少し前のこのコラムで吉田健一の食にまつわるエッセーと短篇小説を取り上げた。しかし彼の書くものは、そればかりではない。デビューしたころは批評家として活躍したし、のちになって長篇小説も書いた。
『東西文学論』は、彼の代表的な評論だ。明治以降に日本人がどのようにヨーロッパから文学を受けとめたかを論じているので、近代の見直しを迫られているいま、新しい時代を考える参考になる。 続きを読む
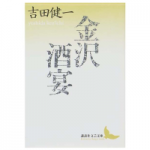
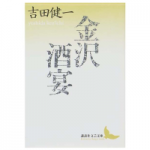
少し前のこのコラムで吉田健一の食にまつわるエッセーと短篇小説を取り上げた。しかし彼の書くものは、そればかりではない。デビューしたころは批評家として活躍したし、のちになって長篇小説も書いた。
『東西文学論』は、彼の代表的な評論だ。明治以降に日本人がどのようにヨーロッパから文学を受けとめたかを論じているので、近代の見直しを迫られているいま、新しい時代を考える参考になる。 続きを読む
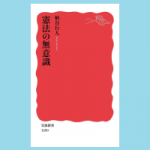
もう20年ほどになるだろうか。日本と韓国の作家のシンポジウムが韓国で催された。日本側の団長的な立場を担ったのが、柄谷行人さんだった。僕はこのときに初めて柄谷さんと会った。
もちろん高名な批評家なのだから知ってはいたし、著作も読んでいた。ただ、生の柄谷さんと接したことはなかった。だから、少しばかり緊張していた。
親しい編集者から聴いた逸話だが、柄谷さんは結婚していたとき、奥さんと揉めると、俺の頭をこんなことに使わせるのは、世界史の損失だというようなことをいったらしい。そんなテンションで、ものを考える人は、僕の身近にいなかった。 続きを読む
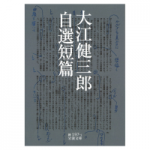
大江健三郎さんの小説を読むようになったのは10代のころだった。同時代の小説家として、世界文学の動向を視野に入れ、新しい文学をつくろうとしている態度に共感し、新作が発表されるたびに注目してきた。
お会いしたことはないが、僕が続けて芥川賞の候補になっていたとき、選考委員をなさっていたので、作品を読んでもらうことになった。確か4回目に落選したときの選評で、「村上政彦は実力を示してきた」と評され、複雑な思いを 抱いたおぼえがある。 続きを読む
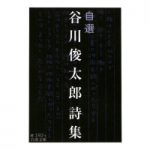
文学を手にし始めた10代のころ、ひとつ悩みがあった。まだ子供だから経済的には不自由だ。しかし、ハードカバーの単行本は高い。だから、読みたい本があっても、それが文庫になるのを心待ちにしたのだが、早く読みたいので、待っているあいだ、ずっと焦れている状態だった。
僕は、ほとんどの文学作品を文庫で読んでいる。文庫は、廉価だし、持ち運ぶにも便利だ。本棚に並んでいるのは文庫ばかりだった。背表紙の出版社を見ると、新潮社、文藝春秋、講談社、集英社などがあったが、そのなかでも特別な存在は岩波文庫だった。 続きを読む
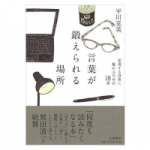
僕は9歳のときに父を喪った。その後は母と祖母に育てられた。
母は、酒場で「ママさん」と呼ばれる勤めをしていた。だいたい昼頃まで寝ていて、夕刻に近くの銭湯へ行き、きれいに化粧をして着物を着る。三面鏡の前で、ぽんと帯を叩いて出かけて行く。帰るのは深夜である。
家族というのは不思議なもので、母と祖母は特に話し合ったわけでもないだろうが、いつか母が「父」になり、祖母が「母」になった。 続きを読む