ふらっと本屋や古本屋をパトロールするときと違って、図書館へ行くときは、だいたい仕事の資料を調べたり借り出したりと、目的が決まっている。それでもときには、「おっ、こんな本があったか」と目当てのものではない本を手に取ることがある。
このあいだ図書館へ行ったとき、ふと、『カフカの生涯』という表題が眼についた。カフカは若い頃から読み親しんだ作家で、近年、マックス・ブロートの手が入っていない全集が出たのを買った。 続きを読む
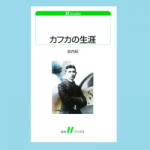
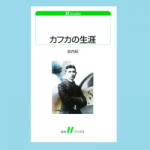
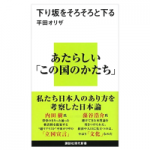
少子化が問題になって久しいが、この議論を見るときにいつも違和感を覚えていたことがある。それは、少子化になると、社会保障などの制度が壊れてしまうから、何とか手を打たないといけないという意見だ。
これは転倒した議論である。そもそも社会の制度は、人に合わせてつくられなければならない。制度に合わせて人をつくろうとするのは、衣服の大きさに体の大きさを合わせようとするようなものだ。 続きを読む
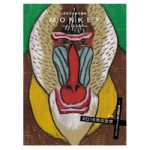
僕は10代の半ばから小説を書き始めた。最初はごく普通の小説を書いていたが、やがてヨーロッパの前衛文学の影響を受け、前衛的な作品に手を染めるようになった。22、3歳のころ、『Mariee’s sample』という作品を書いた。
Marieは、マリーという女性の名と、フランス語の花嫁(Mariee)のダブルミーニングで、ある男の妻になった女性を描いた。ただ、さっき断ったように前衛的な作品で、普通の小説ではない。マリーというひとりの女性の持ち物を写真に撮り、それにキャプションをつけて、カタログ雑誌のように読めるつくりだった。 続きを読む
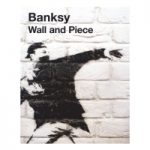
いつのことだったか、あるアーティストがパレスチナの分離壁に絵を描いた、とニュースで知った。壁に描かれた切り取り線と鋏には、政治的なメッセージが込められているように見える。
へー、なかなかおもしろいじゃないか――僕は、バンクシーという、グラフィティ・アーティストとして活躍する覆面作家を、気になるもののリストに登録した。それからときどきメディアがバンクシーを取り上げると、犬が音のするほうへぴくっと耳を動かすように、彼の動向に注意をはらうようになった。 続きを読む
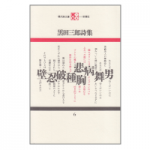
若いころは大人の世界に憧れるもので、僕はホテルのバーのカウンターに坐って寡黙で品のいいバーテンを相手にオンザロックをやったり、白木のカウンターのある小料理屋で熱燗を傾けたりすることを夢見た。
なんのことはない、僕はアルコールがだめだから、結局、大人になっても馴染みの酒場を持つことはできないでいるのだが、むかしはそういう大人が格好いいと単純におもっていた。
もっとも「馴染みの酒場」のように、繰り返しドアを開いて訪れる詩人ができた。その1人が黒田三郎だ。 続きを読む